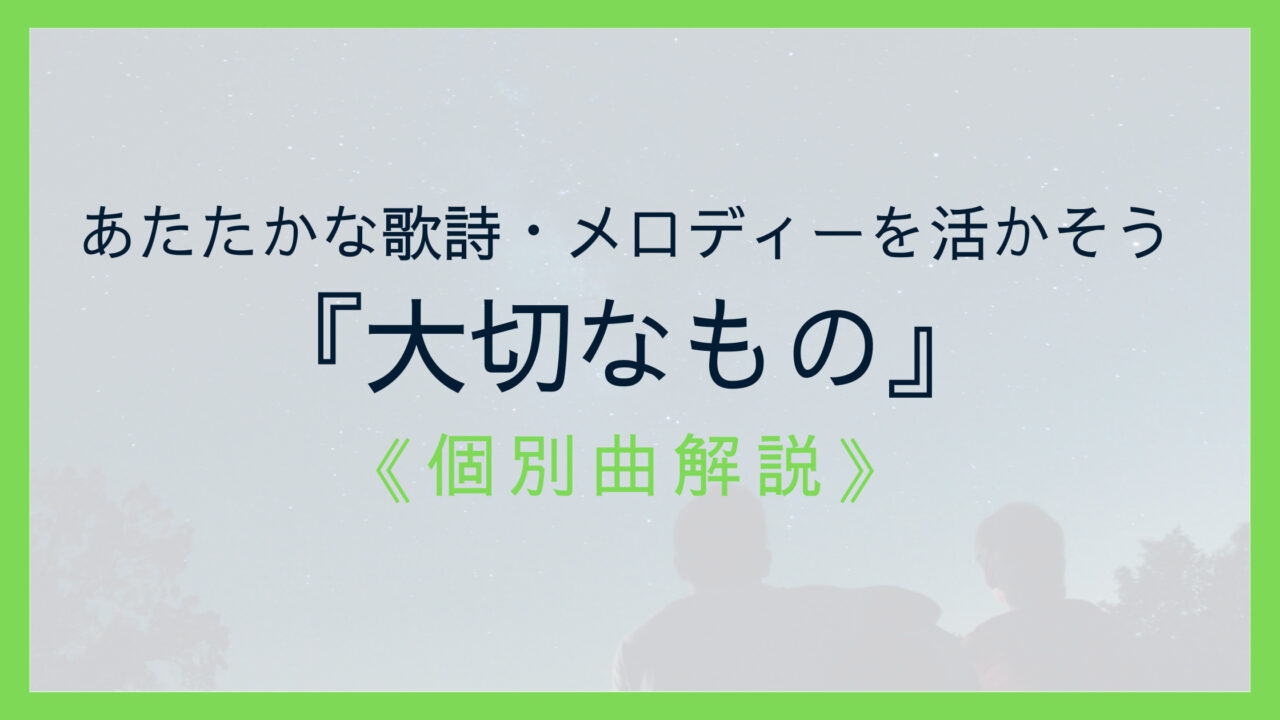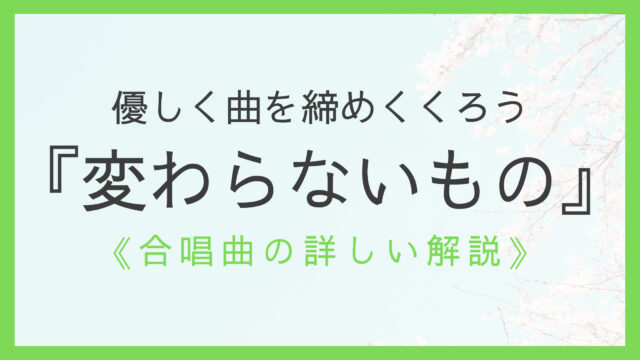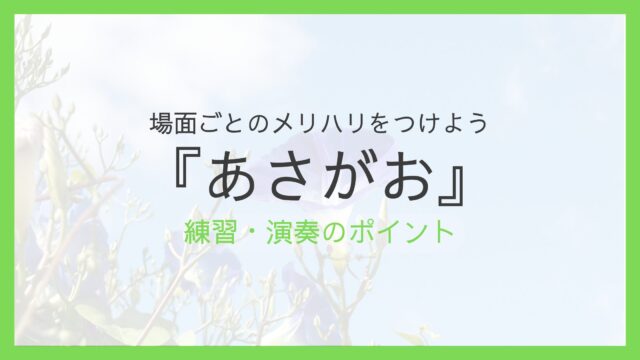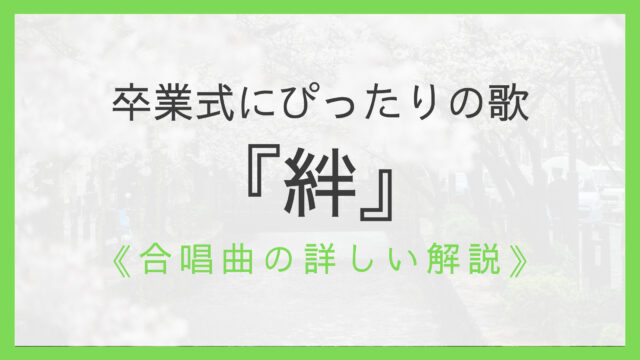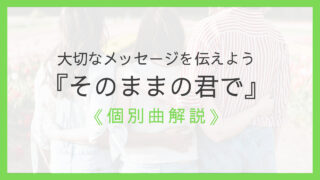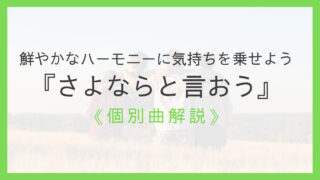こんな方に向けた記事です。
合唱曲『大切なもの』はシンプルながら心温まる作品で、卒業式にもぴったりです。
この記事では『大切なもの』の練習方法や演奏のポイントについて、詳しく解説しています。
この記事を読みながら練習に取り組めば、この曲の良さをよりいっそう引き出すことができると思います。
もくじ
『大切なもの』の練習番号について
練習に取り組む前に、次のような練習番号をつけておきましょう。
- 【冒頭】1小節~
- 【A】6小節~
- 【B】14小節~
- 【C】22小節~
- 【D】30小節~
- 【E】35小節~
練習番号をつけることで練習するときの指示出しがしやすくなります。例えば、「練習番号【B】のアウフタクトから!」などと言った具合です。
それだけでなく音楽全体の構成が分かりやすくなり、よりドラマチックな演奏にも繋がります。
『大切なもの』の歌い方のコツ

ここからは練習番号に沿って進めます。
それぞれの場面でのコツは次の通り。
- 【A】言葉を丁寧に伝えよう
- 【B】クレッシェンドの違いを知っておこう
- 【C】盛り上げてたっぷりと
- 【D】フレーズを意識して
- 【E】ピアノ・ピアニッシモは一番大切!
【A】言葉を丁寧に伝えよう
【A】の場面は、mp(メゾピアノ/少し弱く)の指示があり、歌い上げるというよりは語りかけるように歌う場面です。
ここでは言葉を丁寧に伝えることを意識しましょう。
そのために気をつけてほしいのが次の3つのポイントです。
- 語頭の子音
- 子音のタイミングは早め
- メロディーはレガートに
1. 語頭の子音
言葉を伝える上でまず大切なのが語頭の子音です。
語頭とは単語の1文字目のこと。子音は[k][s][t][n]など、ローマ字で書いたときの[a, i, u, e, o]以外の文字の部分です。
具体例で説明します。一番最初のフレーズでは”そらにひかるほしを”と歌いますね。
ここで伝えたい言葉は”そら”、”ひかる”、”ほし”です。これら3つの言葉が伝われば、聞いている人は歌詩の内容をはっきりと思い浮かべることができるからです。
これらの言葉と語頭の子音は次のようになります。
- “そら”(sora)…[s]
- “ひかる”(hikaru)…[h]
- “ほし”(hosi)…[h]
つまり、[s]や[h]といった語頭の子音を強調することで、それぞれの言葉をはっきり伝えられるということになります。
2番の歌詩についても確認しておきましょう。フレーズとしては”くじけそうなときは”ですね。
- “くじけそうな”(kujikesouna)…[k]
- “ときは”(tokiha)…[t]
というわけで、ここでは[k][t]の子音が大切ということになります。
また、伝えたい言葉の語頭に○印をしておくだけでも、意識が変わって言葉が伝わりやすくなる効果があります。
2. 子音のタイミングは早め
[s]や[h]の子音は歌うときにはタイミングを早めにすることも重要です。
そうしないと子音をしっかり発音したことによってメロディーが遅れてしまうからです。
【A】の場面ではメロディーが始まる直前に8分休符がありますので、食いつきよく(=遅れずに)入りましょう。
3. メロディーはレガートに
もう一つ大切なのことは、メロディーはあくまでレガートに(なめらかに)歌うことです。
言葉を大切にしようとするあまり、語頭にアクセントがきて攻撃的な印象になってしまうことがよくあります。
こうならないよう、子音を強調する場合でもメロディーのラインはキープしましょう。
【B】クレッシェンドの違いを知っておこう
【B】では、まず音量が1段階アップしてmf(メゾフォルテ/少し強く)になります。これによって音楽が前向きに展開していきます。
また、19~21小節にかけて2種類のクレッシェンド(だんだん大きく)が登場します。文字で書いてあるcresc.と、松葉の記号で書いてあるものです。
この2つのクレッシェンドの違いをぜひつかんでおいてほしいと思います。
文字のクレッシェンド(cresc.)
文字による表記のクレッシェンドが書かれる意図としては、音量だけではなく、同時に気持ちの高まりも意図されていることが多いです。
この曲の場合、この先にある【C】向かって気持ちを高めていって欲しいという意味で書かれている、というふうに捉えることができるでしょう。
他に、比較的長いフレーズでじっくりと盛り上げて行きたい場面でも使われます。
松葉のクレッシェンド(<)
こちらのクレッシェンドは、意味通り音量をアップさせてほしいという意図で書かれていることが多いです。
内面的というよりは量的なクレッシェンドと言っても良いかもしれません。
この曲の場合は、ロングトーンでぐわっと盛り上げ、f(フォルテ/強く)の音量に結びつけるイメージです。
【C】盛り上げてたっぷりと
【C】はこの曲ではじめてfの音量が登場し、クライマックスを形成します。
特に最初の2小節の”たいせつなものに”(2番であれば”いつかあえたなら”)というフレーズは、この曲の中でも特に気持ちのこもる部分です。タイトルにもなっていますね。
その良さを引き出すために必要なのが次の3つのポイントです。
- たっぷりとした音量で
- レガートでなめらかに
- ハーモニーを充実させて
1. たっぷりとした音量で
まずはfを表現するためにたっぷりとした音量で、豊かに響かせましょう。
大切なのはブレス(息継ぎ)をしっかり深く取ることです。
また、大きく歌おうとして力みすぎてしまうと、荒々しい歌声になってしまい、曲にふさわしくないばかりでなく、喉を痛めてしまう原因にもなります。リラックスして無理のない範囲で歌いましょう。
また、周りの声と溶け合わせることも忘れずに。メンバー全員でまとまれば豊かなfが作れるはずです。
2. レガートでなめらかに
音量と並んで意識したいのがフレーズの表情です。
fの場面でもレガートに(なめらかに)歌うのがふさわしいと思います。
このように歌うことで歌詩の内容ともリンクして感動的な演奏になると思います。
3. ハーモニーを充実させて
22~23小節は曲中で一番ハーモニーが充実しているところです。
ソプラノのメロディーをアルト・男声がしっかり支えましょう。バランス的にアルトが弱くなりがちですので、しっかり歌ってほしいと思います。そうすることで和音が安定し、豊かに響きます。
練習の際は何回かアカペラ(ピアノパートなしで)で歌ってみてほしいと思います。
お互いの声や空間(練習会場)で鳴っている音に耳を向け、響きを感じ取ってみてください。そしてその響きに自分の声が溶け込むように歌いましょう。
こうすることでより一層美しい和音になっていきます。
【D】フレーズをし意識して
【D】はピアノパートによる間奏となっています。
スラーによってフレーズが示されていますので、まとまり意識して弾くと良いと思います。
例えば31小節目、4拍目裏の右手の8分音符は、スラーによって次のフレーズに繋がっていることが分かります。
この8分音符は前のフレーズの最後の音符ではないことに注意しましょう。
【E】ピアノ・ピアニッシモは一番大切!
43小節目から音量はp(ピアノ/小さく)です。こういった小さな音量で歌う場面ほど、言葉やメロディーを大切に、優しく歌うと良いと思います。
このフレーズでのポイントは次のとおりです。
- 全員でpを作る
- ロングトーンでは音が下がらないように
- デクレッシェンドは消えないように
- 音を切るタイミング
1. 全員でpを作る
43小節目からの”たいせつなものを”というフレーズは全員が同じ音を歌うユニゾンとなっています。
全員で歌うため、人数としては多くなるのですが、pという小さな音量を作る必要があります。
メンバーそれぞれが声を小さな1点に集める、集中させるイメージを持つと良いと思います。
2. ロングトーンでは音が下がらないように
44小節目からロングトーン(伸ばす音)に入ります。
ここでも相変わらずユニゾンなので、全員で1つの音にまとまるよう集中力はと出さないようにします。
また、同じ音で伸ばし続けていると、自然と音が下がっていってしまうことが多いです。そうならないようにピッチをキープし続けることを意識しましょう。
このとき、お腹をしっかり支えて息を送り続けることが重要です。
3. デクレッシェンドは消えないように
ロングトーンの間にデクレッシェンドがあります。
これによって音量をさらにしぼっていき、pp(ピアニッシモ/とても小さく)まで小さくします。
ここは、音が完全に消えてしまわないように注意しましょう。
今回の楽譜の書き方では、伸ばす音が消えていくのではなく、最終的にppで保つような指示になっているからです。
4. 音を切るタイミング
フェルマータの後、合唱だけが音を切り、それと同時にピアノパートの低音の「♭レ」が鳴ります。
このタイミングが肝心。よく聴いて合わせましょう。
指揮者の動きも大切です。手で小さく円を描くような動きで音を切ってください。
まとめ:あたたかな歌詩・メロディーを活かそう
最後に各練習番号でのポイントを振り返っておきます。
- 【A】言葉を丁寧に伝えよう
- 【B】クレッシェンドの違いを知っておこう
- 【C】盛り上げてたっぷりと
- 【D】フレーズをし意識して
- 【E】ピアノ・ピアニッシモは一番大切!
全体としては、『大切なもの』の持つあたたかな歌詩、優しいメロディーの良さを活かせると感動的な演奏になると思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
その他にも役立つ記事がありますのでぜひ参考にしてください。