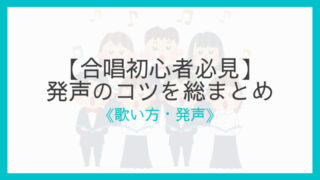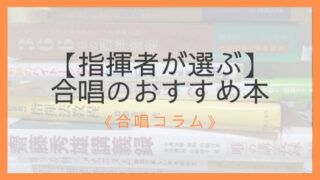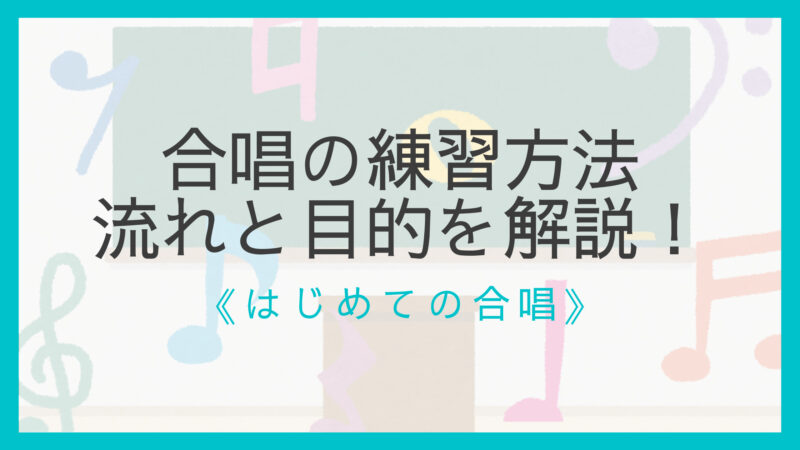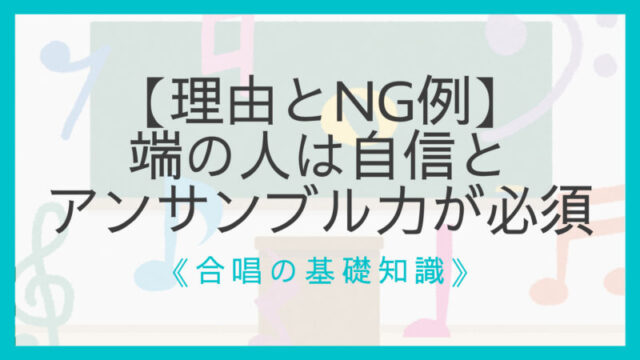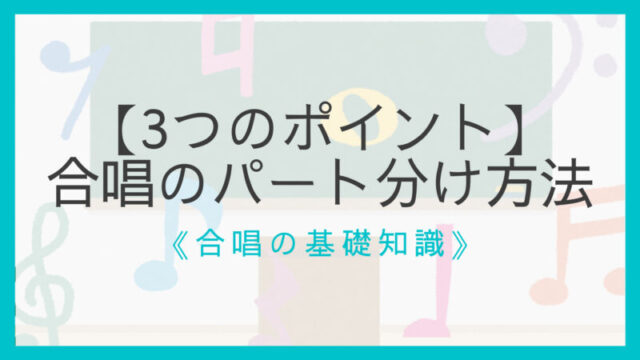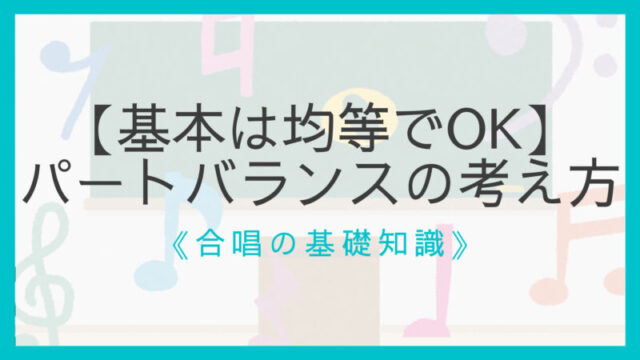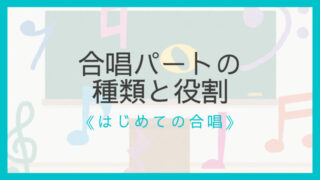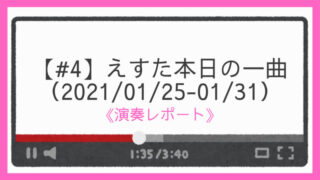こんな方に向けた記事です。
この記事では次のようなことを解説しています。
- 合唱部・合唱団での練習の流れ
- 練習の目的と内容
- よくあるパターン
すでに合唱をしている方や、中学・高校で合唱コンクールに向けて練習をする方も参考にしていただければと思います。
もくじ
合唱の練習方法【流れと内容】
まずは大まかな流れを紹介しておきたいと思います。
合唱の練習は次のようなステップに分けて行われます。
- 体操
- 発声練習
- 基礎練習
- パート練習
- 全体練習(アンサンブル)
1.体操(ウォームアップ・筋トレ)
最初に体操を行います。
目的として次の2つがあると考えています。
- 全身のウォーミングアップ
- 筋トレ
発声に関係の深い肩回りや首をほぐしたり、顔面を動かしたりします。
詳細はこちらの記事(【合唱で役立つ】発声練習前の体操・筋トレメニュー【動画あり】)で解説していますので、合わせてご覧ください。
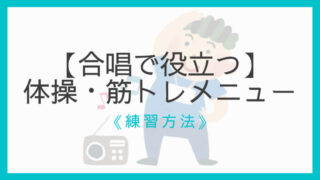
2.発声練習
体操の後は発声練習を行います。
目的としては次の3つがあると考えています。
- ブレス(息)のトレーニング
- 声起こし(声のウォーミングアップ)
- 声づくり(良い声を作るためのトレーニング・ボイトレ)
「3.声づくり」の部分についてもう少し具体的に説明すると、
- 高音を出せるようになる
- レガート(なめらかに)に歌えるようになる
- 跳躍音程(飛ぶ音)をクリアできるようになる
といったことがゴールとして挙げられます。
発声練習でよく行う内容は以下の通り。
- ブレス(s子音)
- リップロール・タングトリル
- ピアノに合わせて声を出す(ア・イ・ウ・エ・オ)
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
3.基礎練習
基礎練習という呼び方はあまり一般的ではないですが、最近はこの練習に力を入れている団体も増えているように思います。
基礎練習をする目的は、合唱で必要な様々な技術・テクニックを練習し、身につけることです。
合唱の技術というと相当多岐にわたるのですが、特に重要なものの例は以下の通り。
- 声の質を合わせる
- ピッチを合わせる
- ハーモニーを作る(ハモる)
このような技術を身につけるために行われている練習といえば次のものが代表的です。
- カノン(同じ旋律を追いかけて歌う)
- 階名唱(=移動ド)
- カデンツ(決まった和音の進行を歌う)
4.パート練習
体操・発声・基礎練習の後はパート練習を行うことが多いです。
自分の担当するパートに別れて練習を行います。
ざっくりとした目的と内容は以下の通り。
- 音取り・譜読み
- パート内で音を合わせる
- 細かい内容の確認・練習
詳しくはこちらの記事(【5ステップ】質の高いパート練習の進め方|PL経験者のノウハウ公開)で解説しています。
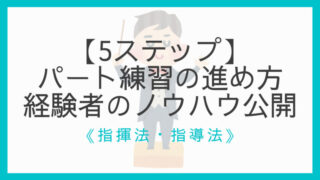
5.全体練習(アンサンブル)
パート練習が終わったら、再びメンバーが合流して全体で練習を行います。
パートが揃うことで、どんな音楽が生まれるのかと、とてもワクワクする時間です。
全体練習での内容例は以下の通り。
- 全体で合わせて響きを確認する
- ハーモニーなどの練習
- 細かい音楽作り
詳しくはこちらの記事(【ポイント6つ】全体練習(アンサンブル)をまとめる方法|合唱指揮者が解説)をご覧ください。
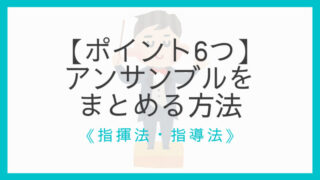
必要に応じて行われる内容
これから紹介する内容は、必要に応じて実施されるものになります。
パート分け
新入部員・団員を迎えたとき、最初の練習で行うのがパート分けです。
「どのパートに入るか?」ということがここで決まります。
パート分けの基準は、歌いやすい音域や声の質、既存メンバーのバランスなどによって判断します。
やり方などについてはこちらの記事(【3つのポイント】合唱のパート分け方法を解説|「ド~レ」が決め手)をご覧ください。
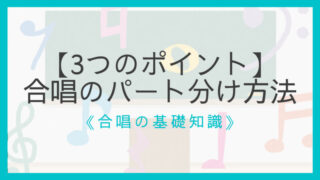
ボイトレ(ボイストレーニング)
普段行っている発声練習に加え、特別なレッスンが行われることもあります。それがボイトレ(ボイストレーニング)です。
声楽家の先生、ボイストレーナーの先生をお呼びして指導をしてもらいます。
練習の流れ:よくあるパターンを紹介
ここまで合唱で行う練習を一通り紹介してきました。
これらのうち合唱団によってやるものとやらないものがあります。
ここでは練習の流れのうちよくある王道パターンを2つ紹介します。
パターン1.学生団で多い
よくある練習内容の流れその1は次のパターンです。
- 体操・発声練習
- パート練習
- 全体練習(アンサンブル)
体操と発声練習をまとめて行い、その後パート練習→アンサンブルという流れです。
中学・高校・大学など学生中心の団体ではパート練習が組み込まれることが多いです。
パターン2.一般団(ハイレベル)で多い
もう一つのパターンがこちら。
- 発声練習
- 全体練習(アンサンブル)
一般団(=社会人中心の団)ではパート練習が省略されることが比較的多い気がします。
曲をとりあえず歌えるようにする段階(音取り)は個人での練習に委ねられているということですね。
【まとめ】合唱の練習方法|流れと内容
それではまとめです。
合唱部や合唱団で普段行っている練習の目的や内容をざっと紹介しました。
まずは全体的な流れを抑えておきましょう。
- 体操
- 発声練習
- 基礎練習
- パート練習
- 全体練習(アンサンブル)
どの団体においてもこれらの内容をベースとした練習メニューになっています。
これを押さえておけば、はじめて合唱の練習に参加する際にも戸惑うことはないのではないかと思います。
歌い方・発声のコツに関してはこちらの記事(【合唱初心者必見】歌い方・発声のコツを総まとめ【上達スピード向上】)でまとめています。