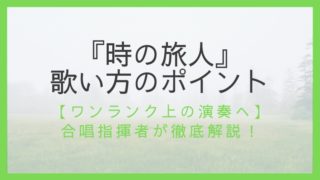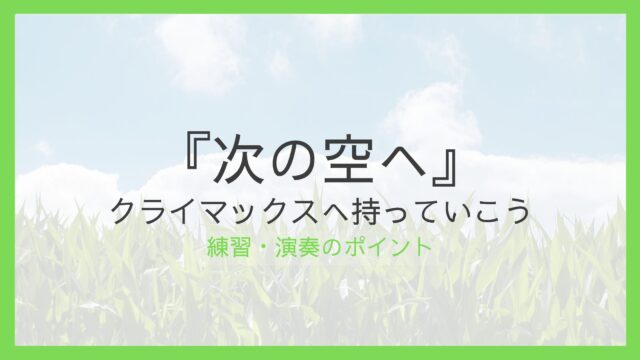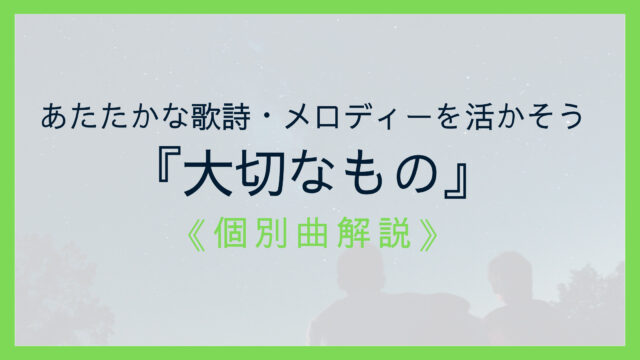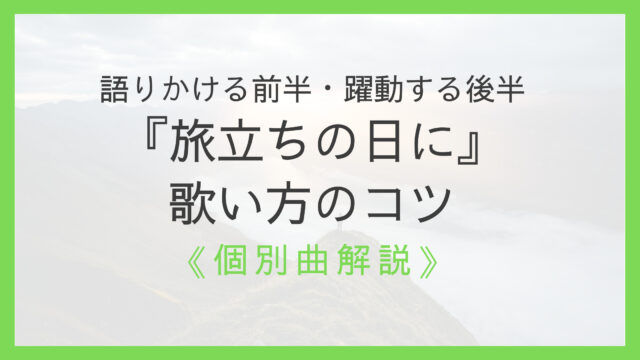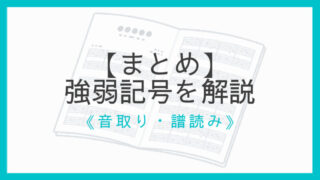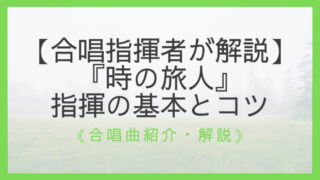『時の旅人』の調・転調・コード進行を考察【曲をより深く理解する】
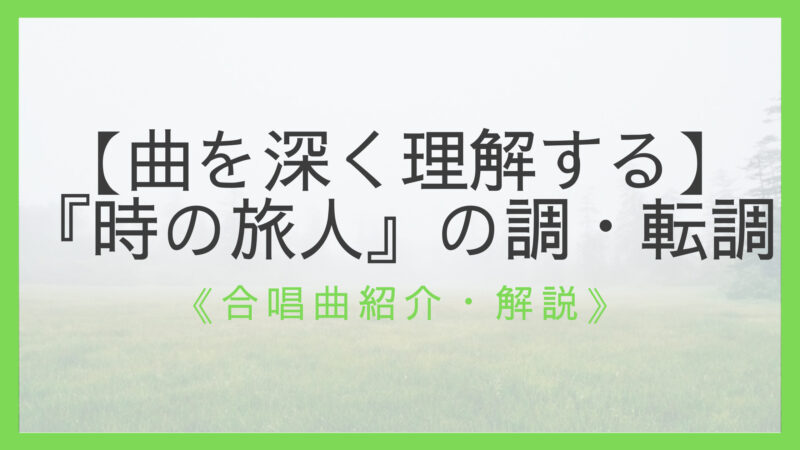

こんな疑問に答えます。
この記事では橋本祥路さん作曲の『時の旅人』について、調とコード進行の観点から分析していきたいと思います。
内容としてはやや難しいかもしれませんが、しっかり考えられると曲をより深く理解することに繋がります。
次の練習番号に沿って解説します。
- 冒頭…1~10小節
- A…11~18小節
- B…19~23小節
- C…24~31小節
- D…32~43小節
- E…44~51小節
- F…52~59小節
- G…60~65小節
- H…66~80小節
もくじ
『時の旅人』冒頭~A…ヘ長調
まず『時の旅人』冒頭~Aについている調号は♭が1つですね。よってヘ長調またはニ短調であることが分かります。
このどちらかを見分けるには2つの方法があります。
- 聞いた印象で見分ける
- 楽譜上の情報(和音など)で見分ける
1.聞いた印象で見分ける
1つ目は実際に聞いてみて判断する方法です。
『時の旅人』の冒頭~Aの部分はどちらかといえば明るい曲調ですので長調だと分かります。よってヘ長調です。
2.楽譜上の情報(和音など)で見分ける
2つ目はやや難しいですが、楽譜上の情報(和音など)から見分ける方法です。この方法だと曲を聞かず判断可能です。
分かりやすいのは3小節目のピアノパートです。
左手の低音でファの音(=ヘ音)を弾いており、これが調の主音だと分かります。ヘ音が主音なのでヘ長調ですね。
ヘ長調の曲の場合、最初の和音もヘ長調(コードネームで言えばF)になる場合が多いですが、この曲ではそうなっていません。やや特別なパターンです。
こういったときは最初の和音だけでなく和音の進行も見てみればヘ長調であることが分かります。
最初の3小節はこのように進んでいます。
B♭ → C7 → F
この進行はヘ長調の
Ⅳ → Ⅴ → Ⅰ
の進行そのものですね。
※実際のコードはもう少し複雑です。
『時の旅人』B…ニ短調
続く練習番号Bはニ短調です。
調号は♭1つのままですが転調していますので見逃さないようにしましょう。
先ほども触れたように♭が1つの場合、ヘ長調かニ短調となります。
ここからガラリと雰囲気が変わり、物悲しい印象に変わっていますね。よってニ短調であることが分かります。
また練習番号Bの最初の和音はDmであること、練習番号Cの1小節前にA7(=ニ短調のⅤ)が登場することからも判断できます。
ちなみに調号が同じ長調・短調の関係を平行調と呼びます。今回の場合ヘ長調とニ短調が平行調の関係です。
この転調は「転調した!」というショックが少なく、自然な進行に聞こえるという特徴があります。
『時の旅人』C…ニ短調
練習番号Cは引き続きニ短調です。
調号が相変わらず♭1つであること、物悲しい雰囲気であることから分かります。
練習番号Cのコード進行に注目してみます。なかなかカッコ良いですね。
Dm7→Gm7→C7→FM7→
B♭M7→Gm7→Em7♭5→A7
ポイントは7のついたセブンスコードです。セピア色、ストイックさ、そんな響きを感じます。テキスト(歌詩)にもマッチしていますね。

『時の旅人』D…ニ長調
練習番号Dから♯が2つの調に転調します。
♯が2つの調としてはニ長調またはロ短調が考えられますが、明るい印象なのでニ長調と判断しましょう。
調の判断材料としてもう一つヒントになるのが、直前の練習番号Cがニ短調であることです。
つまりこの転調ではニ短調→ニ長調と変わっているのですが、主音「ニ」はそのままということが分かります。
主音を同じくする調どうしを同主調と呼びます。同じ主音を持つ調と言う意味です。
このような転調はスムーズに行いやすく、それでいて曲調を一気に変化させるような劇的な効果が期待できます。
物悲しい雰囲気から次第に解放されるように、瑞々しい色彩に変化していく…。そんな場面の描写に貢献している転調です。

『時の旅人』E~G…ニ長調
引き続きニ長調です。
このままE, F, Gまで進みます。
Eのコード進行を分析してみましょう。
D→D/C♯→Bm7→D/A→
G→D/F♯→Em7→A7→…
練習番号E~Gまでこの進行が何度も繰り返されています。
ポイントはベースライン(ピアノパートの左手)で、1音ずつ下がっていくのが分かりますね(レ→ド#→シ→ラ→ソ→ファ♯→ミ→ラ)。
このような進み方は安定感があり、力強く前向きな印象を生み出しています。
『時の旅人』H…ト長調
曲の最後です。♯が1つなのでト長調またはホ短調が考えられます。
明るい雰囲気なのでト長調と分かります。曲の終わりの和音もト長調(コードネームだとG)であることから間違いないですね。
練習番号Hの2小節前から和音進行を見てみましょう。
D→D7→G
となっています。(ソプラノがド♮を歌うところがD7です。)
このD7→Gというのはト長調の典型的な進行(Ⅴ→Ⅰ)となっています。
直前の調(♯2つ、ニ長調)ではドに♯がついていましたが、ここでナチュラルになります。これによってト長調の雰囲気を事前に感じさせる、という仕組みとなっています。
まとめ:『時の旅人』の調
曲全体の調をまとめておきます。
- 冒頭~A…ヘ長調
- B…ニ短調
- C…ニ短調
- D…ニ長調
- E~G…ニ長調
- H…ト長調
こうしてみると、いろいろな調に移り替わりながら曲が進むことが分かります。
『時の旅人』のタイトル通り、まるで旅をしているようですね。
またそれぞれの調・転調の機構(方法)やコードの進み方には、詩の内容との密接な関係が見て取れます。
そこまで考察できると『時の旅人』をよりいっそう深く味わるようになると思います。