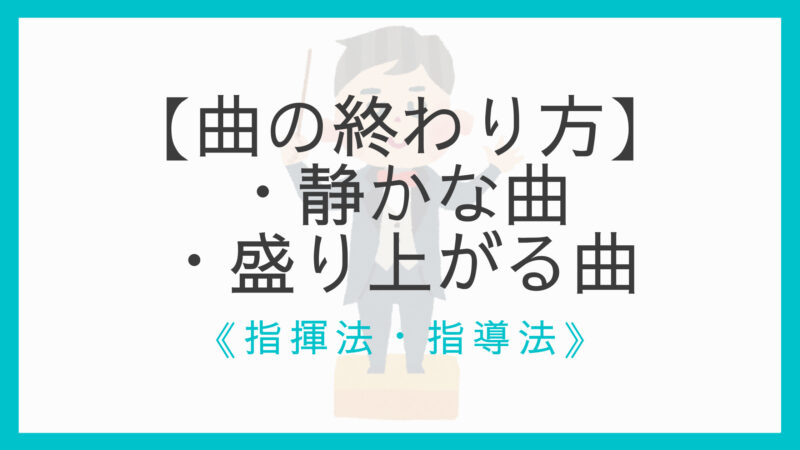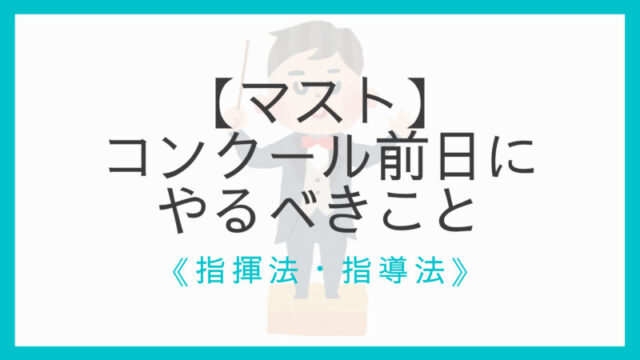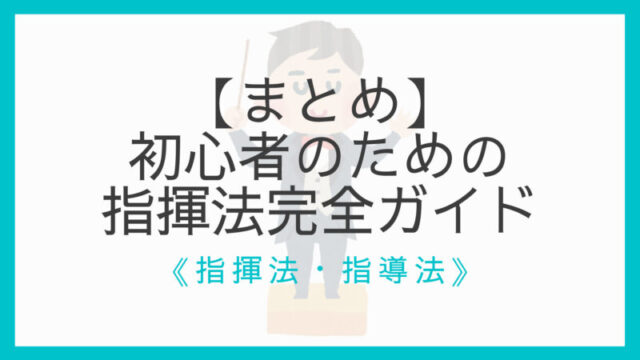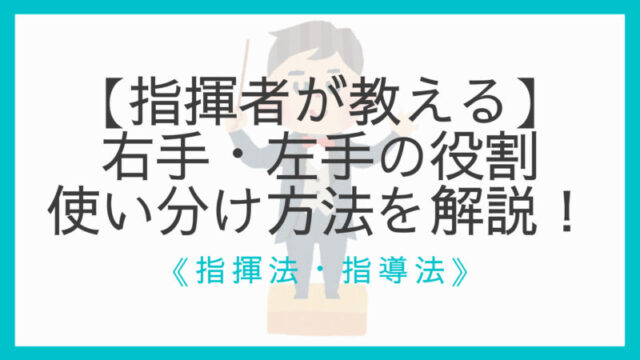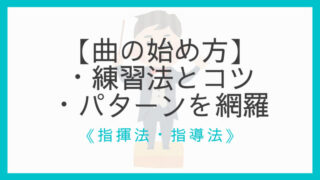こんな疑問に答えます。
曲の最後をしっかり決められると非常にかっこ良いですよね。
ですが実際のところ「どうやって振れば良いの?」という部分が分からないと思います。
そこでこの記事では以下の2つのパターンで、曲の終わりの振り方を解説します。
- A. 静かに終わる曲
- B. 盛り上がって終わる曲
それぞれに指揮法の大切なエッセンスが詰まっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
もくじ
A. 静かに終わる曲【左手の使い方がポイント】
p(ピアノ/小さく)など、静かなロングトーン(伸ばす音)で終わる曲はとても多いです。
ロングトーンでは左手の使い方がポイントになります。
基本の手順【3ステップ】
次の手順で振ってみましょう。
- 最後の音を右手で示す
- 右の手の平を上に向けてロングトーンをキープする
- 伸ばした後、左手で小さく円を描いて音をカットする
2.でロングトーンを示すとき、腕に力が入りすぎていると強い音に見えてしまいます。
静かな雰囲気を表現するには腕の力を抜いて柔らかく見せるのがポイントです。
より高度なテクニック
楽譜の指示によっては次のようなテクニックを合わせて使いましょう。
音量を小さくしていきたいとき(decresc.など)
伸ばしている間に、音量をだんだん小さくしていきたいときに使えるテクニックです。
右手でロングトーンをキープしながら左手を合わせて使います。
- 左手を伏せて下に降ろしていく→分かりやすいデクレッシェンド
- 左手を自分の胸に近づけていく→内面的なデクレッシェンド
ただ腕を動かすのではなく、「こういうデクレッシェンドが欲しい…!」という気持ちを伴うことが大切です。
伴奏と合唱の終わりが異なるとき
合唱が最後のロングトーンに入った後も、ピアノパートが後奏として動く場合が良くあります。
こういったときは右手と左手を使い分けましょう。
- 右手→ピアノパートに対して振り続ける
- 左手→合唱に対してロングトーンを示す
このように使い分けるのがオーソドックスです。
静かな雰囲気を表す音楽記号
静かな雰囲気を表す記号は他に次のようなものがあります。
- p, pp
- smorz.(スモルツァンド/rit.+decresc.)
- morendo(モレンド/rit.+decresc.)
静かな雰囲気で終わる曲の例
合唱曲の例をいくつか挙げておきます。
参考に聞いてみてください。
- 『マイバラード』
- 『天の川』
- 『信じる』
B. 盛り上がって終わる曲【腕の緊張感を見せる】
続いては盛り上がって終わる曲の場合を解説します。
基本の手順【3ステップ】
次の手順で振ってみましょう。
- 最後の音を右手(または両手)で示す
- 腕に力を込め、緊張感を見せる
- 音を伸ばした後、左手で大きく円を描いて音をカットする
2.では腕全体に力を込め、力強さを感じさせることが重要です。
それがプレイヤー(歌い手)に伝わって大きな音量を引き出すことができます。
より高度なテクニック
盛り上がる曲の応用編です。楽譜の指示や自分のイメージによって使い分けましょう。
音量を大きくしていきたいとき(cresc.など)
音量を大きくしていきたいときは、右手の緊張感に加えて左手を活用することで効果的に示すことができます。
- 手の平を上向きにして上げていく→広がりのあるクレッシェンド
- 強くこぶしを握る→力強さ、固さなどの表現
最後の音を短く切って終わるとき
曲の最後がロングトーンではなく、4分音符や8分音符で「ドン!」と終る曲もありますよね。
こういうときに使えるのが「叩き止め」や「反動叩き止め」のテクニックです。
詳しくは書籍『はじめての指揮法(著:斉田好男)』をご参照いただくのが良いと思います。こちら【やりたいこと・悩み別】おすすめ記事・本・アイテム・サービス一覧にて紹介しています。
盛り上がる雰囲気を表す音楽記号
次のような記号があるときに使える振り方となっています。
- f, ff
- cresc.
- allarg.(アラルガンド/cresc.+rit.)
盛り上がって終わる曲の例
合唱曲の例としては次のような作品があります。
- 『Let’s Search For Tomorrow』
- 『名付けられた葉』
- 『はじまり』
まとめ:曲の終わり方はイメージ通りの音が出る方法を選ぼう
「静かに終わる曲」「盛り上がって終わる曲」両方の振り方を解説しました。
実際に振る時はこれらをその通りに振らなければいけないということではなく、表現したい音楽に合わせてアレンジすることになります。
楽譜を読み取った上で「自分はどんな音で終わりたいか?」をイメージすることが大切です。
その他指揮のコツに関しては【まとめ】初心者のための指揮法完全ガイド|合唱指揮者が基礎から解説でまとめていますので、ご参照ください。