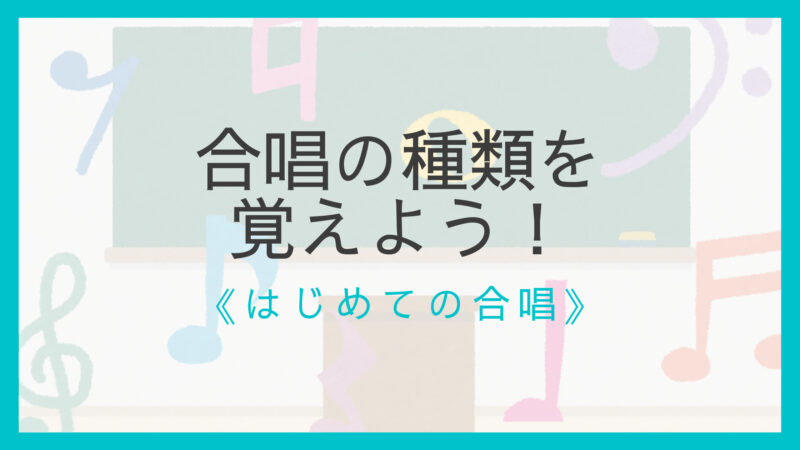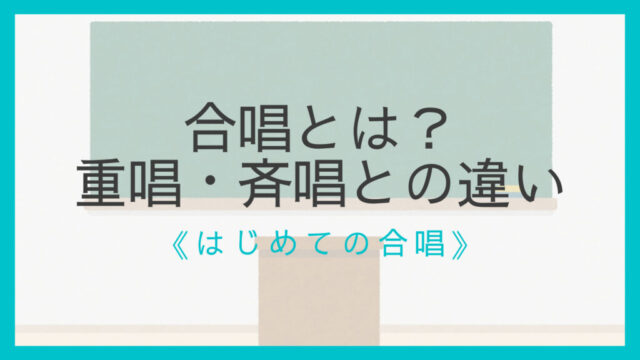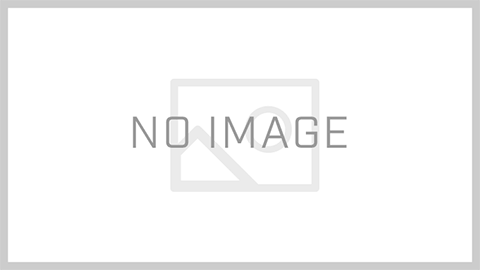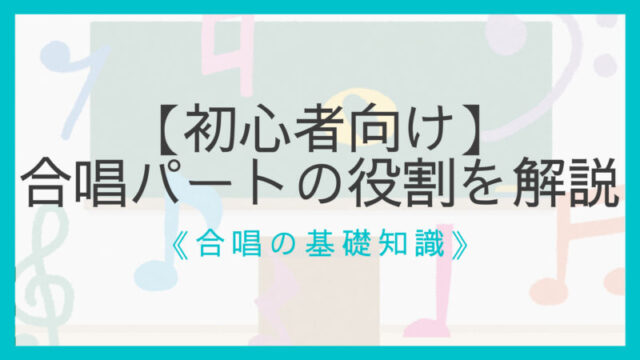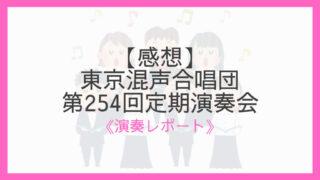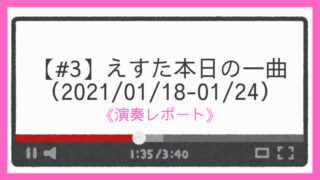そんな疑問に答えます。
- 合唱の演奏形態の分類
- 混声・女声・男声合唱の意味
- アカペラの意味
- 色々な形態の合唱を聞いてみる
今回も一緒に合唱について学んでいきましょう。
もくじ
合唱の種類:声の性質による分け方
では早速、合唱の種類、演奏形態にはどんなものがあるのか見ていきたいと思います。
合唱を分類する方法として、一番オーソドックスなのが「声の性質」による分け方です。
声の性質による分け方は3種類
声の性質というのは、ざっくりと言えば女の人が歌うのか、男の人が歌うのかということ。
おおむね女性の声は高く、男性の声は低いことが多いですよね。
合唱と言うのは、声で作り上げるものなので、「声」が違えば響きも大きく変わります。
これが「声の性質」で合唱を分類する理由です。
声の性質で分けたときの合唱形態としては次の3種類があります。
- 女声(じょせい)合唱=女の人の声で歌う
- 男声(だんせい)合唱=男の人の声で歌う
- 混声(こんせい)合唱=男女両方の声で歌う
合唱の形態を表すときには「女性」ではなく、「女声」という漢字を使います。「声(こえ)」という字ですね。
先ほどはイメージしやすいように「女の人の声で歌う」と書きましたが、実はこれは正しくありません。
合唱の分類をする際に大切なのは生物的な性別ではなく、声の音域(高さ)です。
なので男性であっても高い声が出せる人は女声合唱に参加することもあります。
逆に低い音を歌える女性が、男声合唱に参加することもできるんですね。
こういった場合は結構あるんですよ。
女声・男声・混声合唱それぞれの魅力
声の性質による合唱形態の分類方法が分かったところで、今度はそれぞれがどんな響きなのかが気になりますよね。
もちろん演奏する曲や団体によって魅力というのは変わってくるのですが、ある程度共通する部分もあるのでそれについて解説致します。
女声合唱の魅力・特徴
はじめは女声合唱です。女の人が得意とする高い音域の声による合唱でしたね。
繊細で澄んだハーモニーが魅力で、優しい響きの曲も多くなっています。
上質な演奏ではなんだか眠くなってしまうこともあったり……。
男声合唱の魅力・特徴
女声合唱に対し、男の人が得意とする低い音域の声による合唱です。
重厚な響きや迫力が魅力です。
この迫力を生かした荒々しい曲もあれば、洗練された現代的な雰囲気の曲もあったりします。
混声合唱の魅力・特徴
混声合唱は、女声~男声の音域を広く用いる合唱形態です。
音域が広いため、最も複雑なハーモニーを作れるとされています。
歌われる頻度が高いこともあって、混声合唱の曲は非常にたくさん作曲されています。
そのため、「名曲!」と言われるような作品も混声合唱には多くなっています。
合唱の種類:パートの数による分け方
ここまで「声の性質」で分けた場合の合唱形態を解説してきました。
実は合唱の種類/演奏形態の分け方には他にもいくつかあります。
というわけで次は「パートの数」による分け方を説明したいと思います。
本格的な形態は4部合唱
パートの数で合唱形態を分けた場合、次のようになります。
- 2部(にぶ)合唱…パートの数が2つ。簡単な曲が多い。
- 3部(さんぶ)合唱…パートの数が3つ。中学校で歌う曲に多い。
- 4部(しぶ)合唱…パートの数が4つ。最もオーソドックスで本格的な形態。
※パートの数が5つ以上になる形態もありますが、五部合唱のような呼び方はそれほど一般的ではないように思います。
基本的にはパートの数が多ければ多いほど難しい形態になると考えていただいて大丈夫です。
よく使う言葉「div.」(ディビジ/分かれて歌う)
ちょっと難しい言葉なのでイメージが付きにくいかもしれませんが、div.またはdivisiについて触れておきます。「ディヴィジ」と読みますが、「ディヴィ」ともよく言います。
これは楽譜の中で使われる記号で、「1つのパートをさらに分割して歌ってください」という意味になります。
具体的な例を挙げてみます。
仮に今、1パートを10人で歌っていたとします。
曲の途中でそのパートにdiv.の記号が出てきたとすると、途中からは5人ずつの2パートに分かれて歌う、ということになります。
このようにdiv.があるとパートの数が一時的に増えることになります。そのため全体的には四部合唱の場合でも部分的に5パート以上で歌っているケースが出てきたりします。
参考:40声(=40パート)の合唱曲を紹介します
パートの数が5つ以上になることもあると先ほど書きましたが、なんと40パートで歌う作品もありますので、せっかくなので紹介しておきます。
タリスという作曲家による『Spem in Alium nunquam』です。曲のタイトルの意味は置いておいて、ともかく40パートで歌うというのが驚きですよね。
動画を見てもらうと分かるのですが、この曲はメンバーをいくつかの小さな合唱団に分けて歌っています。小合唱団は8つあり、それぞれが5パートの合唱をしています。8×5=40パートあるというわけ。
合唱の種類:伴奏による分け方
さて、他にはどんな分類の方法があるでしょう。
次は「伴奏」による分け方を解説したいと思います。
アカペラは伴奏のない形態
合唱曲は声だけで演奏するのではなく、時にピアノやオーケストラの伴奏が付く場合があります。
逆に伴奏が付かない場合の形態をアカペラ(または無伴奏)と呼びます。
ピアノ伴奏がある形態の呼び名は特に決まっていないように思いますが、「ピアノ付き」と呼ぶことが多いかと思います。
ピアノ以外の楽器がつく場合
合唱の伴奏と聞いてパッと思いつくのがピアノだと思います。
ですが実は、合唱と一緒に演奏される楽器は他にもたくさんあるんですよ。
いくつか紹介しておきたいと思います。
- ピアノ
- オーケストラ
- パーカッション
- ギター
- オルガン
などなど…
いろいろあります。どんな曲か気になりますよね。
いろいろな種類の合唱を聞いてみよう。
さて、ここまでの内容をいったんまとめておきたいと思います。
合唱の代表的な分類方法は以下の3つがありました。
- 女声合唱=女の人の声で歌う
- 男声合唱=男の人の声で歌う
- 混声合唱=男女両方の声で歌う
- 2部合唱
- 3部合唱
- 4部合唱
- アカペラ(無伴奏)
- ピアノ付き
- オーケストラ付き
実際に合唱の形態を分類する際にはこれらの組み合わせて言い表します。
次の見出しではそれらの例を挙げつつ、曲も合わせて紹介しようと思います。
ピアノ付き女声3部合唱の例
作詩:新川和江/作曲:高嶋みどり、女声合唱とピアノのための《明日のりんご》に収録されている曲です。
女声ならではの柔らかい声と、透き通ったハーモニーが味わえますね。
ピアノパートも大活躍していることが分かるかと思います。
無伴奏男声4部合唱の例
作詩:高見順/作曲:木下牧子、無伴奏男声合唱組曲《いつからか野に立つて》に収録されています。
無伴奏の男声合唱です。もしかしたらアカペラの合唱作品をはじめて聞く方もいらっしゃるかもしれませんね。
ピアノ付き混声3部合唱の例
作詩・作曲:若松歓による作品。中学生向けのレパートリーです。
極端に高い音や低い音が使われておらず、歌い易い曲であるのが分かります。
無伴奏混声4部合唱の例
作詩:さくらももこ/作曲:相澤直人による作品です。
混声ならではの充実したハーモニーですね。
オーケストラ付き混声4部合唱の例
オーケストラ付きの曲も気になるかと思うので紹介しておきたいと思います。
作詩:フライシュレン/訳詩・作曲:信長貴富による作品です。
オーケストラの前奏から始まりますがすぐアカペラになります。
ちなみに歌詩は日本語とドイツ語の両方を歌っています。
まとめ:合唱の種類/演奏形態を覚えよう!
それでは今回のまとめです。
- 合唱を「声の性質」で分類した場合、女声・男声・混声合唱がある。
- 無伴奏の形態をアカペラという。
- 伴奏やパートの数によっていろいろな曲がある。
今回の内容を知っておくと、次のように合唱曲に興味を持つきっかけになると思います。
- 「今日は混声合唱を聞いてみよう」
- 「ピアノ付きの男声合唱はどんな曲があるんだろう?」
曲を聞くことは合唱の経験値になり、上達スピードも上がります。
いろいろトライしてみてください。