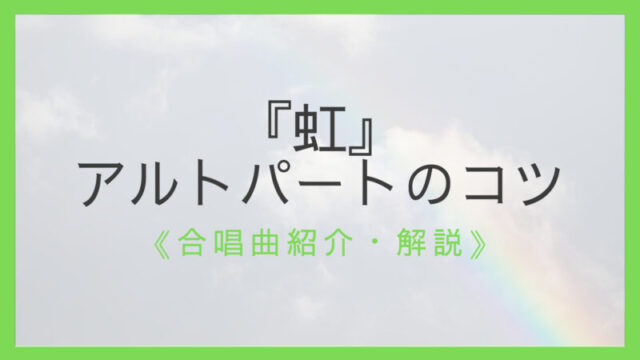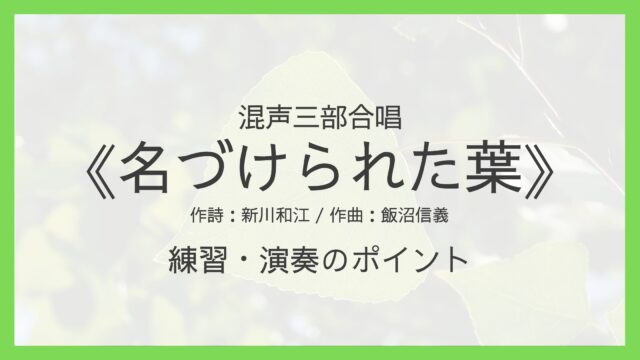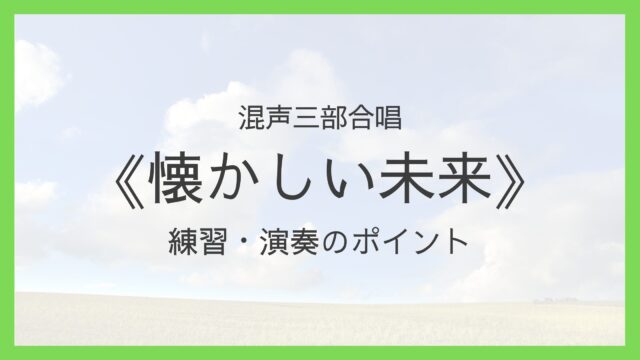【混声三部合唱】『証』練習・演奏のポイント|情熱的に歌い上げよう
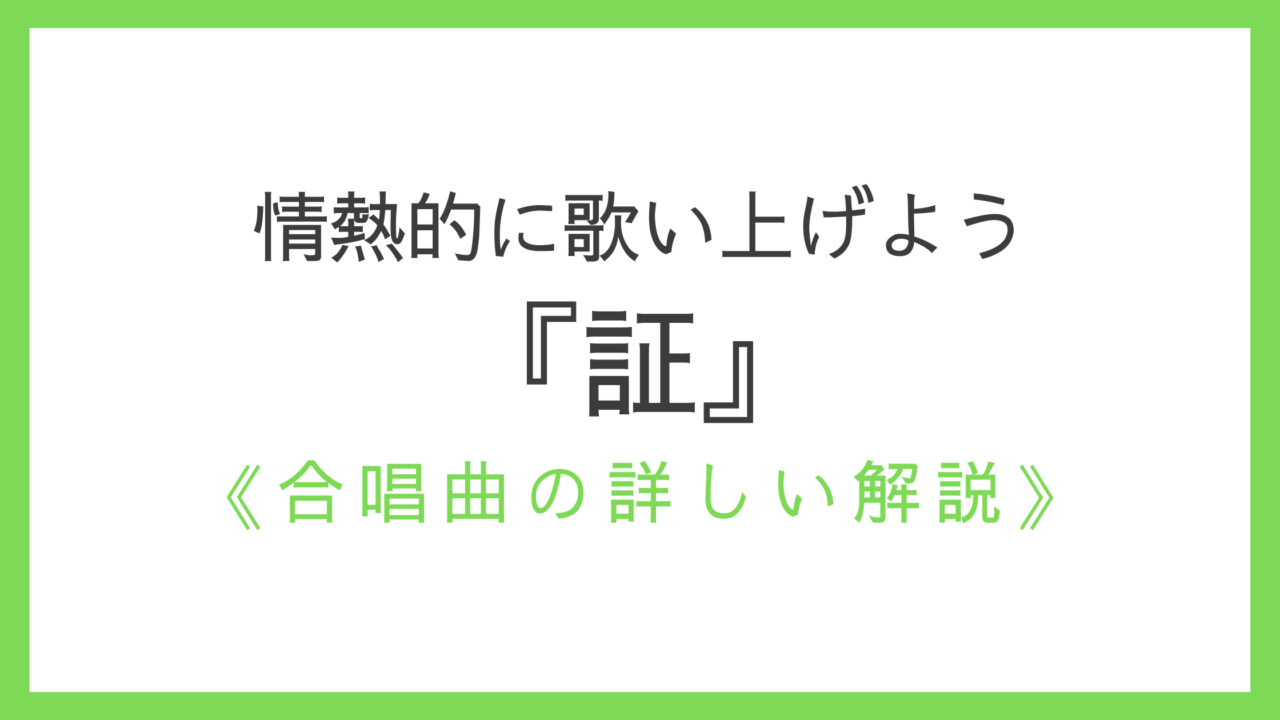
2011年度Nコン中学の部課題曲の『証』(作詞:山村隆太 作曲:阪井一生 編曲:加藤昌則)の解説記事です。
合唱歴15年以上、指揮者の経験をもとに詳しく解説しました。ぜひ参考にしてください。ワンランク上の演奏に繋がるはずです。
「もっと詳しく解説してほしい!」という場合は、お問い合わせからお気軽にご連絡いたください。補足・追記いたします。
もくじ
練習・演奏のポイント
【A】5小節~
小さな音量でも歌詞をしっかり伝えよう
【A】の音量は、ソプラノがp(ピアノ/小さく)となっています。
音量としては小さいのですが、歌詞ははっきりと伝えられるようにしましょう。
歌詞は子音をしっかり目に発音することで伝わります。
[子音の例]
- ”まえを”…m
- ”ふりかえってちゃ”…f
- ”とおざかる”…t
- ”きみに”…k
アルトはサブのメロディーを担当しています。メインとなるソプラノを邪魔しないようpp(ピアニッシモ/とても小さく)となっていますが、消極的にはならないようにしたいフレーズです。
伸ばす長さをそろえよう
【A】だけに限らないことですが、フレーズ終わりの音の長さをそろえることは、合唱の統一感を出す上でとても大切です。
例えば8小節に注目してみましょう。
まず、ソプラノの”あるけない”は、2拍目まで音が伸びています。3拍目には四分休符がありますから、ここに掛からないように音を切る必要があります。
一方、アルトの”あるけない”は3拍目まで音が伸びており、四分休符があるのは4拍目となっています。つまり、ソプラノと同じタイミングで音を切ってはいけないということになります。3拍目の終わりまで音を切らないように気をつけましょう。
【B】13小節~
ソプラノ・アルトでタテをそろうことを意識
【B】からはソプラノとアルトが同じタイミングで同じ歌詞を歌う(=「タテが揃う」)ようになります。
漫然と歌い進めるのではなく、「ここからはタテがそろうんだぞ」ということをお互いのパートが意識しましょう。
そうすることで一体感が生まれ、よくハモるようになります。
アルトのアピールポイントとコツ
【B】では、アルトがしっかり目立ってアピールするべきフレーズがいくつかあるので取り上げておきます。
まずは17小節のアウフタクト(16小節4拍目)、”ぼくは”のフレーズです。ソプラノのメロディーに対し、半拍先行する形でアルトが入ります。
ここは自信を持ってしっかりと入りましょう。そうしないと「間違えてしまったのかな?」とも思われてしまいかねないところです。
むしろ、自分たちがソプラノを引っ張るんだ、という意気込みで歌うと良いでしょう。音量的にはmpですが、音域的に少し低めので、少し大きめと思うくらいでもバランスは取れると思います。
次に18小節の2拍目裏、”ゆめへと”です。
この「ファ♯」の音は非常に取りにくい音だと思います。歌うべき音を頭の中に明確に思い描いた上で、音に上がるようにしましょう。
その上で、<>という記号が付けられています。これは>よりも柔らかなアタック感を持つアクセント記号です。少し目立たせてアピールして欲しい音ですが、攻撃的な感じにはならないようにしましょう。
【C】20小節~
クレッシェンドを工夫しよう
【C】では頻繁にクレッシェンドの記号が登場します。
クレッシェンドは「だんだん大きく」の意味ですが、記号がでてくるたび、毎回大きくしていくと、いつか限界が来て息切れしてしまいますし、音楽的にも一本調子になってしまいます。
そのため、ここでは少し工夫して、クレッシェンドを次の2つに分けて考えてみたいと思います。
- 音量を変化させ、場面どうしを繋ぐクレッシェンド
- 勢いをキープし、休符を活かすクレッシェンド
①としてはまず、21~22小節にかけてのクレッシェンドが挙げられます。mpからmfへと向かうことで、【B】と【C】の場面を繋ぎます。
28~29小節にかけてのクレッシェンドも同様で、mfからffへ向かい、しっかりと盛り上げていくことで、【D】へと繋ぎます。
②として挙げられるのは25小節、26小節、27小節のクレッシェンドです。ここでは伸ばす間に勢いがなくなってしまわないよう、音量やピッチ(音程)をキープするイメージで歌いましょう。
そして、その勢いをその先にある休符に向けて持っていってみましょう。そうすることで歌うところと休むところ(=ブレイク)のメリハリがつきます。
男声は音量バランスに気をつけて
【C】では男声が初登場します。低音部が強化されることで、響きの厚み・ボリューム感が増してきます。
「男声が入ることで生まれる効果」を十分に活かすには、パート間の音量バランスに注意が必要です。
混声三部合唱の男声パートには、次のような特徴があります。
- ソプラノ・アルトに比べてパートの人数が多くなりやすい
- 全体的に音域が高い
そのため、普通に歌ってしまうと自然と男声の音量ばかりが大きくなってしまい、バランスが崩れてしまいます。結果として、最初に説明した「効果」が十分に現れてきません。
そうならないためにまず、男声パートの人は女声の声をよく聴いて、寄り添うようにして歌ってみましょう。また、自分の音と女声の音が合わさったときにどんな音になるのか、ということにも意識を向けてみると良いと思います。
音が高くなっていくようなところでは、特に丁寧に歌うようにしましょう。パートの人数が多いため、一人ひとりが頑張りすぎずとも、十分な音量は出るはずです。量より質を意識してみてください。
また、練習の際にできる工夫として、少しレベルの高いですが、パートの立ち位置をバラバラ(ソプラノ・アルト・男声が固まらずに混じり合った状態)で歌うという方法があります。
こうすることで、いつもはあまり聴けないパートの声がよく聴けるようになり、全体のまとまり感がグッとアップする効果が見込めます。
どうしても男声が大きくなってしまうという場合は、男声を後列に配置する並び方も検討すると良いでしょう。こちらの記事(【7種類+】合唱パートの並び方(オーダー)を工夫しよう|メリット・デメリットも解説)も参考にしてみてください。
また、こちらの曲(【混声三部】《ふるさと(嵐)》(編曲:富澤裕)練習・演奏のポイント)においても、「男声が大きくなってしまう」という悩みに答えています。
【D】30小節~
主役意識を強く持とう
ここからはサビの場面です。主役のメロディーを担当するのはアルトです。
普段アルトの人がメロディーを担当することは少なめですので、主役意識を強く持って歌いましょう。
音量はff(フォルティッシモ/とても強く)で、さらに”激して”という指示もあります。もし十分に音量が出ないときは、この部分だけソプラノから数人応援に来てもらっても良いと思います。
ソプラノはサブの旋律なので、少し人数が減ってもバランスは取れると思います。
言葉のまとまりを意識しよう
【D】をはじめとするサビのフレーズはリズムが非常に複雑です。
こういった場合、「今どんな歌詞が歌われているのか」ということを見失ってしまいがちです。
例えば、最初のフレーズでは”あふれだす なみだが きみを さえぎるまえに”と歌いますが、リズム通りに歌うと、「あふれー」「だすなー」「みだがきー」「みを」「さえー」「ぎるー」「まえ-」「にー」というように、言葉が途切れ途切れで、不自然な歌い方になってしまいます。棒読みのように聴こえてしまう原因の一つでもあります。
このような場合、楽譜に歌詞を「漢字」で書いてみるというのが、第一の対策です。
歌になる前の詞に基づけば、”溢れ出す”、”涙が”、”君を”、”遮るまえに”となります。これだけで、ずいぶん言葉が浮かび上がってきたように感じられると思います。
【E】34小節~
メロディーの交代を意識しよう
【E】の特徴はメロディーを担当するパートが短いスパンで切り替わること。どのパートがメロディーを担当するかは矢印で示されています。
[メロディーを担当するパート]
- ”きずつけあーーっ”…アルト
- ”てはなんども”…ソプラノ
- ”ゆるー”…アルト
- ”しあえたこと”…ソプラノ
自分のパートはどこでメロディーを担当することになるのか、頭に入れて歌いましょう。
パートが切り替わるところでは、メロディーがひとつながりで聞こえるよう、声質やピッチを統一することを意識して練習してみてください。
切り口を揃えよう
37~39小節は、1コーラス目を締めくくる大切なフレーズです。最後まで気を抜かず、伸ばす音の切り口をしっかり揃えて決めましょう。
タイで繋がれた音は、「◯拍伸ばす」という数え方では揃えにくいので、「このタイミングで切る」という考え方のほうが分かりやすいと思います。
39小節では、3拍目に休符がありますから、2拍目いっぱいまで伸ばし、3拍目に掛からないように音を切ります。ピアノパートが四分音符を4回鳴らしますから、それを目印にすることも可能です。
もちろん、指揮の動きに合わせて切っても良いでしょう。
【F】41小節~
音量バランスに注意
【F】は曲頭の【A】と同様のフレーズですが、男声が入ることが異なります。
これによりハーモニーにより厚みが出てきます。【C】でも触れましたが、ハーモニーで重要なことの一つが音量のバランスです。
43~44小節は男声の音域が高く、自然に声が大きくなりやすいフレーズです。そこで少し抑え気味にし、丁寧に歌うと、バランスを取りやすいです。
逆に、42小節あたりは音が低いので、ややしっかりめに歌うと良いと思います。
ここでも切り口に注意
【F】の場面でも、伸ばす音の長さ、切り口を揃えることに注意しましょう。
例えば44小節では、女声は2拍目まで(3拍目に掛からないように切る)、男声は3拍目まで(4拍目に掛からないように切る)、それぞれ伸ばします。パートごとに切るタイミングが異なるのが正解です。
一方、46小節では、女声も男声も3拍目まで伸ばし、4拍目に掛からないように音を切ります。ここでは全員で切るタイミングを揃えることが重要です。
【G】48小節~
ロングトーンの注意点
【G】での注意点は【C】と同様です。
その他、以下のようなロングトーンの箇所でハーモニーを整えることをよく練習しておくと良いと思います。
[ロングトーンの箇所]
- ”ぼくがもしも”
- ”ゆめに”
- ”あきらめたなら”
- ”とおくで”
- ”しかってよ”
パート内の音程・音色が揃っているか、声が混ざり合っているかどうか、バランスはどうかなどといったことを確認しながら練習しましょう。
ハーモニーを確認するためには、アカペラ(ピアノパート無し)で歌ってみるのが非常に効果的です。また、テンポを落として練習してみると、どのような響きになっているのか、うまくいっているのか、そうでないのかということが実感できると思います。
【H】57小節~
アルトと男声で息を合わせよう
ここからは再びサビの場面です。
ソプラノはオブリガート(メロディーを装飾するサブメロディー)をフレーズを担当するため、【E】とは異なり、57~60小節の間はずっとアルトが主役です。
アルトの音量が不足してしまう、ソプラノばかりが聴こえてしまうという場合は、ソプラノのうち何人かがアルトを手伝っても良いでしょう。
また、アルトと男声はタテがそろっているので、タイミングを良くそろえて歌いましょう。
男声はハモリのとき(57小節など)とユニゾン(59小節など)のときがあるのでその点も意識すると、メリハリがつきます。
【I】61小節~
フレーズ終わりの違いを考えよう
【E】では37小節に”しだいに落ち着けて”という指示が書かれていました。フレーズの終わりに向かって、音楽を収束させる意図です。
一方で【I】の64小節には指示はありません。その代わり、続く66小節に”テンポを上げてリズミックに”の指示があります。
この指示自体は主としてピアノパートに向けたものではありますが、全体的な音楽の方向性が示されています。したがって、ここでは音楽を収束させていくのではなく、むしろ前向きに進めていくような歌い方が相応しい場面となっています。
具体的には、66小節のロングトーンを、弱くならずにしっかりと伸ばし切ることが大切です。繰り返しになりますが、ここでもやはり切り際が重要。ここは2拍目いっぱいに伸ばし、3拍目に掛からないように切ります。ピアノパートの四分音符を手がかりにすると分かりやすいです。
このように、続く音楽の内容によってフレーズの締めくくり方を変えましょう。
【J】67小節~
テンポを上げてノリよく弾こう
ここからはPoco piu mosso(ポーコ ピウ モッソ/前よりも少し早く)となります。
シンコペーションのリズムやアクセントを活かしてノリよく弾きましょう。
【K】72小節~
変化を感じて柔らかく歌おう
【K】は大きな変化がある場面です。
[【K】での変化]
- テンポ…Meno mosso(メノ モッソ/前よりも遅く)
- 音量…p~mp
- 歌い方…dolce、legato
- ピアノパート…ゆったりとしたリズム
全体としては、優しく語りかけるような場面となっています。
雰囲気を感じながら歌う、しっとりと歌ってみてください。
ここでも言葉・言葉のまとまりを意識
【K】では男声パートがメロディーを歌います。
【D】で詳しく解説したのと同じく、ここでもを言葉のまとまりを意識しましょう。そうすることで、棒読みっぽさが減り、メロディーを豊かな表情で歌うことができます。
メロディーの歌詞を分解して整理すると、” ”またね”って”、”言葉の”、”儚さ”、”叶わない”、”約束”、”いくつ”、”交わしても”、”慣れない”となります。これを楽譜に書き込んでおくだけでもかなり意識が変わると思います。
こうした上で、各言葉の1文字目を丁寧に強調するように歌うと、よりメロディーが生き生きとしてきます。
【L】76小節~
テンポ感を切り替えて、遅れずに歌おう
TempoⅠ(テンポ プリモ/もとの速さで)があり、ゆっくりになっていたテンポがもとに戻ります。
場面自体も優しい雰囲気から、白熱した雰囲気へ変化します。前触れはほとんどありませんから、乗り遅れずに、瞬間的に反応して切り替えることが必要です。
男声は滑らかに
76~77小節では、男声が女声とは異なり、四分音符の動きをしています。
バックコーラス的な役割になるので、一つ一つの音がゴツゴツとならないように、滑らかに歌うのが良いと思います。
78小節からは女声とタテが揃いますから、一体感を意識して歌いましょう。
クレッシェンドの足並みとブレイクを決めよう
78~79小節にかけてクレッシェンドがあります。
これは【M】から始まる最後のサビ、および転調に向けた助走となる重要なクレッシェンドです。
「どのくらいのペースで大きくするのか」「どこまで大きくするのか」という意識を統一しておくと、非常に迫力のある見せ場のシーンになります。
また、79小節の3拍目の四分休符は大事なポイントです。ここで音のない瞬間(=ブレイク)を作ることで聴いているひとをハッと惹きつけ、続くffを鮮明に印象付けることができます。
再度の繰り返しになりますが、2拍目まではしっかり伸ばすこと(クレッシェンドしながら)、3拍目に掛からないように音をカットすることを忘れないようにしましょう。
同時に、ピアノパートの左手のアクセントも感じ取ってみましょう。
【M】80小節~
転調を明確に、熱く歌い上げよう
ここから♭の数が増えて転調します。サビの部分に関してはニ短調 → 変ホ短調という変化で、半音高くなります。
その分音域も高くなりますので、ボルテージを上げて熱く歌い上げましょう。
この転調は前触れが短く、突然切り替わります。瞬時に切り替えることができれば、聴いている人を驚かせるような効果が出せるでしょう。
【N】84小節~
白熱するサビ
【N】からはいよいよ本当にラストのサビになります。
音量的にもfffと書かれていて、もはや熱狂的とも言えるほど白熱するシーンです。
重要なのはアルトのメロディーを埋もれさせないこと。ソプラノのオブリガートが強すぎるとバランスが崩れてしまいますので、【H】で書いたのと同じく、一時的に何人かのソプラノが手伝っても良いと思います。
ソプラノのオブリガートも重要ではありますが、音域が高いため聴こえづらいということはあまり起こりません。高音域が得意な人がいれば、積極的に歌ってもらうと良いでしょう。
83小節4拍目の、シンコペーションとなる”Ah”の入りはsffz(スフォルフォルツァンド/sfz(特に強く)よりさらに目立たせて)が書かれています。強烈なインパクト、熱さを意識して入りましょう。
【O】89小節~
広がりのあるアタック感で
91小節の”Wa”には、アクセントとsfz(スフォルツァンド/特に強く)、そしてデクレッシェンドが書かれています。
歌い方を整理すると、”Wa”に入った瞬間は強く、目立たせて歌い、その後小さくしていく、となります。
入りの目立たせ方にはいろいろな表現が考えられますが、ここではあまりカツンと固い当て方ではなく、ある程度柔らかさを持った、広がるのあるアタック感、あるいはバウンド感のある歌い方がふさわしいかなと私は思います。
”W”の子音を発音する時の響きを上手く利用すること、すぐに小さくしてしまわずに、ある程度保ってからデクレッシェンドしていくことがコツです。
終わりの雰囲気をイメージした音量で
92小節以降、合唱には特に音量の指定は書かれていません。
そのため、直前のデクレッシェンドの流れを引き継いで歌うことになりますが、曲の終わりの雰囲気をイメージし、それにふさわしい音量で歌いたい場面です。
ピアノパートにpと書かれていますから、これを目安にしても良いでしょう。
お互い聴き合ってハーモニーを響かせよう
ラストは合唱らしいハーモニーが魅力的な場面です。
自分のパートの音をしっかり取るだけでなく、お互いの声を聴きあうことで豊かな響きが生まれます。繰り返しになりますが、ここでもアカペラで和音を確認しておくと良いでしょう。
その後、ピアノパートを入れて歌うときには、今度はピアノの音もよく聴いて、全体的なハーモニーを整えましょう。よく聴くと、ピアノも合唱と同じ音を弾いていることが分かります。
終わりに
最後までご覧いただきありがとうございました。
「もっと詳しく解説してほしい!」という場合は、お問い合わせからお気軽にご連絡いたください。補足・追記いたします。