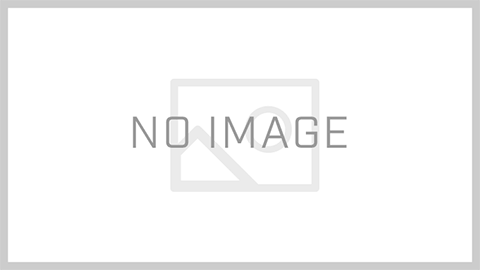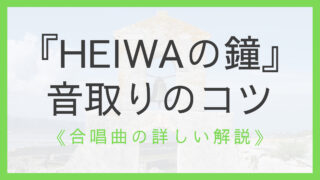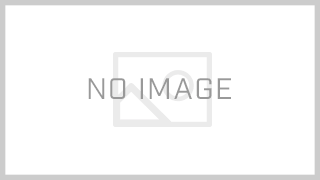信長貴富編曲、「7つの子ども歌」より『通りゃんせ』混声版のポイントと練習の記録をまとめています。
団員向けの記事です。検索などでたどり着いた方にも参考になるかも。
もくじ
練習の記録と指揮者の感想
2023/11/03(初回)
初回でした。
全体の音取り、譜読み。
ざっと通してなんとなくまとまるところまで持っていく。
全体的にテンポがもったりしてしまう。横の流れをもう少し。
男声3部になるところはやや課題。
次回は音をもう一度さらった後に、もう少し流しながら歌う練習します。
2023/11/05(2回目)
全体の音をさらう。
テンポ感がちょっと持ったりしすぎていたので修正、共有。
中間部【C】のポリフォニー部分かなり確認。
雰囲気かなりできてきました。
逆に音とか声とか基本的なところが詰めきれていないので、今後の課題。
2023/12/23(3回目)
事前審査が無事通過。その後始めての練習。主に復習。
1ヶ月以上空いたにも関わらず、なんとなくできちゃっていることが偉い。
が、その分雰囲気で流れてしまいそうなこともあるので要注意。
来年からは詰めていきます。
2024/01/08(4回目)
歌詞+ハミングのところがもう一つ。歌詞を”lololo”に変えて練習するとか工夫が必要。母音唱とか。
最初の1~2ページ(【A】~【B】)くらいはもう少し練習必要。
【C】のポリフォニーはなんとなくうまく行っているけど、もう一つ「すごい!」演奏にはまだなっていない。パートの場所を変えるとかスクランブルにして歌うとかが良いかも。
練習・演奏にあたってのキーワード
イメージを持ってもらうために書き出しておきます。
- 雰囲気/空気感
- 横の流れ
- 立体感/奥行き
- 霧がかかったような、ゆらめき
- ポリフォニー/旋律の浮き沈み
- 子音
練習番号
- 【A】1~ “通りゃんせ”
- 【B】15~ “行きはよいよい”
- 【C】22~ “通りゃんせ”
- 【D】32~ “この子のななつの”
- 【E】36~ “行きはよいよい”
- 【F】39~ “通りゃんせ”
細かめに分けました。
大きく分けるなら次の感じです。
- 前半…【A】【B】
- 中盤…【C】【D】
- 後半…【E】【F】
各場面の説明は後述します。
場面ごとのポイント
練習番号ごとに説明します。
【A】
1小節
最初2小節、ユニゾン。高い緊張感を持って、tの子音、o母音。
3小節
ソロのところ、B.F.の人たちは、よくハモって。Amに雰囲気を。
11~14小節
歌詩パートとB.F.はテンポ感を共有して。あまりモタモタしない。
【B】
15小節
“いきはよいよいかえりは”まで男声ユニゾン。
16小節
“こわい”はオールユニゾン。kの子音をうまく使って、「濃く」
“い”でハモる。H-dur。
17小節
“こわいながらも”は【E】と違ってrit.しないので注意。a母音が開きすぎて緊張感が抜けてしまうので、そうならないように。
19~21小節
rit.とdim.に雰囲気を。遠ざかっていくように。
【C】
この場面の要素をまとめると以下の通り。
- テンポ上がって流れる
- ポリフォニー的(掛け合い)
- 半音進行、
- 浮遊した音進行(着地しない)
これらから、モヤ~っとした空気の中で、複数の旋律が浮かび上がって、また消えていく…的な画が意図されているものと思います。
新しく入るメロディーは少しはっきりと出てください。…がやりすぎると雰囲気なくなるので、さりげなく?
22~23小節
テナーの入りはソプラノとニュアンスを合わせて。
アルトは低くなるほど存在感を増して。
24~25小節
アルト~ソプラノはオルガヌム的。(5度ずれたポリフォニー)
27小節
“天神”のe母音はよく開いて。
30~31小節
D♭7 → Cのコード重要。
B.O.のは入りはソプラノ→アルト→テナーの順になる。
【D】
sub.pからクレッシェンドですが、発声、ピッチが悪くなりがちなので注意。
クレッシェンドは出し惜しみで後半に。
クレッシェンドにともなってテンポが落ちないように注意。
一体感を持って。
【E】
しばらくユニゾン。充実して。
37~38小節
書いてないですが”こわい”にて若干rit.
“こわいながら”くらいでテンポ感を戻していく、つまり若干のaccel.(アルシス的に)。
その後rit.します。この辺でセンスを見せたい。
1拍パウゼ(休み)も緊張感が緩まないよう。
【F】
テンポが戻りますが、遅くなりすぎず。
ソプラノの”通りゃんせ 通りゃんせ”は切れないほうがよいです。
ベースの”Oh”は響き厚く。5度がなっているような音で。