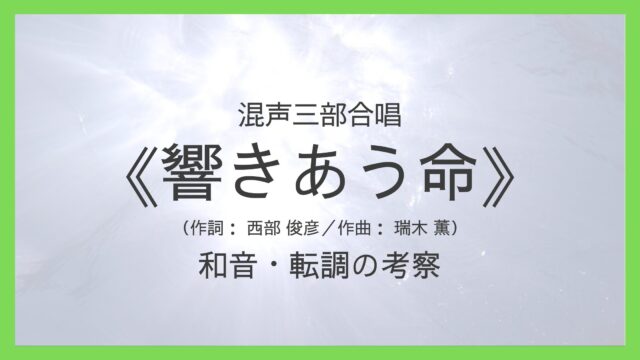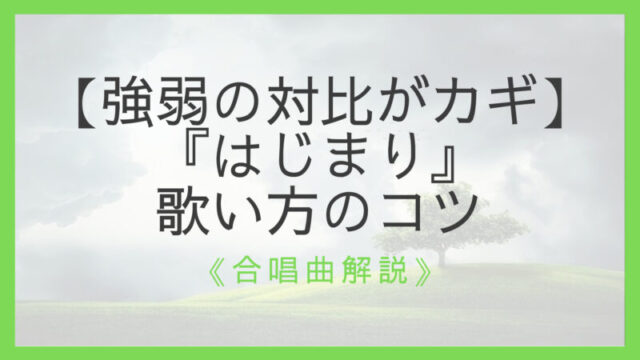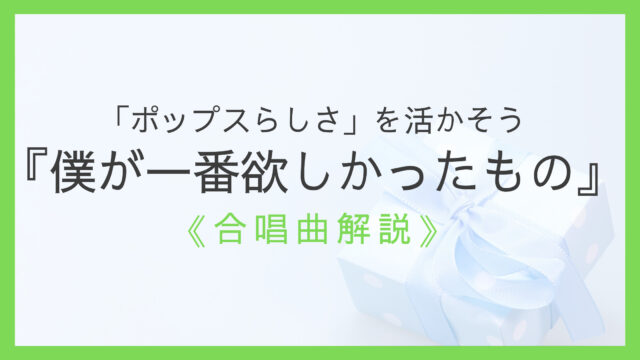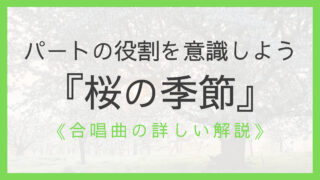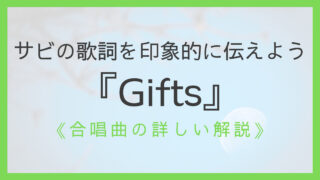合唱曲《HEIWAの鐘》歌い方・練習のポイント|平和への思いを込めて
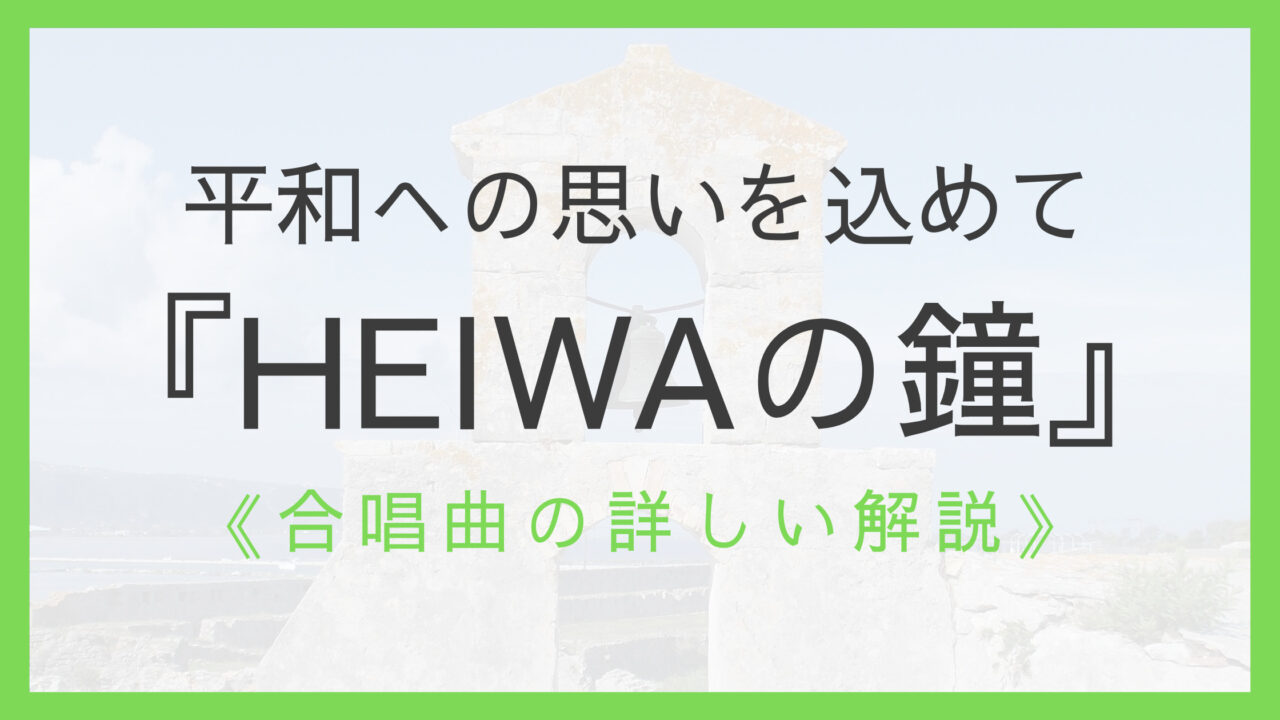
この記事では合唱曲《HEIWAの鐘》(作詞・作曲:仲里幸広 編曲:白石哲也)について、練習・演奏のポイントを詳しく解説しています。
「もっと詳しく解説してほしい!」という場合は、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。補足・追記いたします。
もくじ
練習・演奏のポイント
【A】鐘の響きをイメージしよう
【A】はピアノパートの前奏です。
左手は速めのテンポに乗って、シンコペーションを感じて弾きましょう。
右手の完全5度(「ド」と「ソ」の関係)のハーモニーとアクセントは鐘のイメージで。
【B】3声のハーモニーを充実させよう
【B】は合唱らしい豊かな響きが味わえる場面です。
お互いの声をよく聴き合ってハーモニーを充実させましょう。
ピアノ伴奏がついていますが、アカペラ(ピアノなし)で練習するのが非常に効果的です。
【C】16分音符の言葉をしっかり伝えよう
【C】で多く登場する16分音符では口をしっかり動かして、言葉をはっきり発音することを意識しましょう。
[意識したい言葉]
- “ぶきをもたぬ”
- “とわにかたりつぐ”
これらは意識しないと何を言っているのか分からなくなりがちなフレーズとなっています。
ただし、急ぎすぎずにテンポは守ることも大切です。
両立にチャレンジしてみてください。
【D】なめらかな歌い方を心がけよう
《HEIWAの鐘》はアップテンポのため、全体的に弾むような歌い方になってしまいがちです。
【C】など、その歌い方でよい場面もありますが、【D】に関してはどちらかといえばなめらかな歌い方が相応しいと思います。
ピアノ伴奏の形が変化していることは、そう考える根拠のひとつになります。
“おびやかすことでしか”、”まもることができないと”など、フレーズのまとまりを大きく捉え、細切れにならないように気をつけましょう。
【E】メイン・サブの役割を考えよう
【E】はそれぞれのパートの役割を考えたい場面です。
主役は男声。主旋律を歌います。
女声は副旋律担当。男声に対して合いの手を入れるような役割になっています。
男声のメロディーを感じ取ってから女声が入る、というようにタイミングをはかりましょう。
そうすることで2つのメロディーが絡み合って音楽に変化が生まれます。
音量変化に関して、【E】のはじめにcresc.(クレッシェンド/だんだん大きく)が書かれています。
影響範囲は【F】に入る直前までですが、ずっと大きくし続けようとすると息切れしてしまうでしょう。
そういうときはクレッシェンドのポイントを絞るのが考え方のひとつ。
【F】直前の33~34小節で一気にガーッと仕掛け、パワーを高めていくと、効果的なクレッシェンドになると思います。
【F】明るく、フレーズを大きく捉えて歌おう
【F】はサビ。明るく、たっぷりと歌い上げたい場面です。
歌い方としては、少し弾むような感じになっても構わないと思いますが、スタッカートのようにあまりに切れ切れだと美しくありませんし、言葉の流れが失われてしまいます。
フレーズを大きく捉え、まとまりを意識して歌いましょう。
「44小節や58小節の”ひびくよ”のように、二拍三連の箇所を指揮者としてどう振ればよいか」という質問をいただきました。
たしかに、四拍子で振り続けるのが良いのか、三連符に合わせて振るのが良いのか、迷うところです。
ここで考えたいのは、「指揮者としてどんなふうに歌ってほしいか、どんな音楽にしたいか」ということです。
“ひびくよ”のところを、音符一つ一つにアクセントをつけて、はっきりと歌ってほしい、という場合、三連符それぞれに対して振ると良いと思います。この振り方では、1つ1つの音符のリズム感を際立たせて、迫力ある歌い方をしてほしいというメッセージになります。
そうではなく、”ひびくよ”という言葉をひとまとまりで、つなげるように歌ってほしいときは、四拍子を基本に振ります。このとき、1,2,3,4の3拍目は”ひびく”の”ひ”のところに来ます。ここはきちんと伝えたい言葉なのでしっかりめに振ると良いと思います。一方、4拍目のところには、合唱パートもピアノパートも音符がありませんので、ここはあまりきっちり振る必要がありません。ここを振らないことで、アクセントはつけずに、滑らかに歌ってほしいというメッセージになります。代わりに次の小節の”よ”のロングトーンや、ピアノ伴奏の再開に意識を向けておくのが良いでしょう。こちらのほうがより大人っぽい表現かなと思います。
「どのような音楽にしたいか」ということをイメージして、振り方もそれに合わせて選択・決定していただければ良いかなと思います。
【G】間奏は冒頭のメロディー
間奏は【B】で合唱が担当していたメロディーをピアノパートが弾いています。
【H】最後まで集中して歌い切ろう
【H】は【B】と同様に豊かな響きで。
65小節からのロングトーンは最後まで気を抜かずに歌い切りましょう。
具体的な注意点は次の3点。
- 音量のキープ
- ピッチキープ
- 長さ、切り際を守る
1. 音量のキープ
これだけ長いとだんだんと声が弱くなってしまうことがありそうです。
伸ばす間に、こっそり息継ぎをするカンニングブレス(ローテーションブレス)をしても良いと思います。
カンニングブレスの際には、たくさんの人がいっぺんに抜けてしまうと音が途切れてしまうので、場所がダブらないようにしましょう。
入り直すときはバレないように慎重に。
2. ピッチキープ
音量と同様、伸ばしている間にピッチ(音程)も下がってしまうおそれがあります。
やはりカンニングブレスを活用しましょう。
3. 長さ、切り際を守る
音量・ピッチをキープしたまま、8拍+0.5拍を伸ばしきります。
拍を数えても良いですが、ピアノパートの右手のメロディー(「ミソラーソミソラ!」)をよく聴いて、「ラ!」を聴いたタイミングで切るようにすると分かりやすいです。
指揮者の指示を頼りにしてももちろん構いません。
ポイントの振り返り
- 【A】鐘の響きをイメージしよう
- 【B】3声のハーモニーを充実させよう
- 【C】16分音符の言葉をしっかり伝えよう
- 【D】なめらかな歌い方を心がけよう
- 【E】メイン・サブの役割を考えよう
- 【F】明るく、フレーズを大きく捉えて歌おう
- 【G】間奏は冒頭のメロディー
- 【H】最後まで集中して歌いきろう
「もっと詳しく解説してほしい!」という場合は、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。補足・追記いたします。