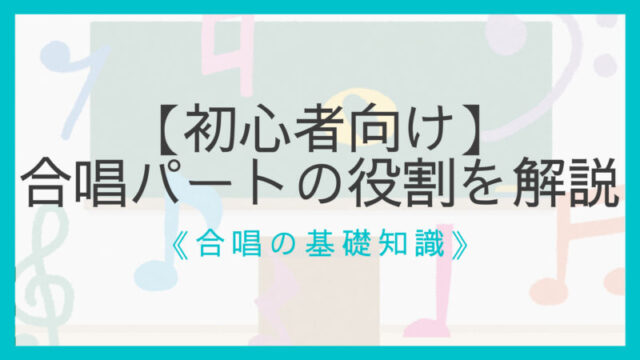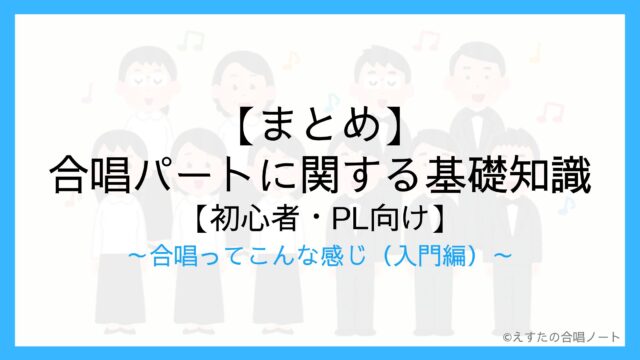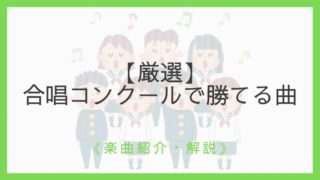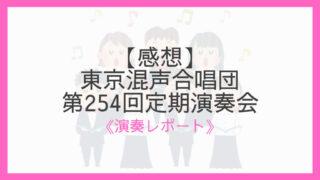合唱とは?「こんな感じ!」を初心者の方にも分かりやすく紹介します
「合唱って、そもそも何?」
「合唱ってなんとなく知ってはいるけど、実際どんな感じ?」
そんな疑問をお持ちの方に向けた記事です。
合唱とは、一人で歌うのではなく、複数の人がパートに分かれて声を重ねる音楽の形。ソプラノ・アルト・テノール・バスなど、それぞれ異なる音域のパートが集まることで、美しいハーモニーが生まれます。
この記事では、20年近く合唱に親しんできた筆者が、合唱の基本からその魅力、始め方まで、これから初心者の方にも分かりやすく紹介したいと思います。
もくじ
合唱とは? 他の音楽とはどう違う?
合唱の特徴って?
最初に、合唱の特徴について整理しておきましょう。ポイントは次の3つです。
- 声で歌う
- たくさんの人が集まってする
- 複数のパートに分かれる
まず「①声で歌う」について。合唱は、人が歌う音楽の形態の一つです。楽器が登場することもたくさんありますが、基本は歌、つまり人の声が主役。声の芸術と言っても良いでしょう。
歌うというと、例えばカラオケでポップスを歌ったり、あるいはバンドでボーカルをやったりということが思い浮かぶ人も多いと思います。そういったジャンルの音楽と異なる点が、「②たくさんの人が集まってする」と「③複数のパートに分かれる」です。
どれくらいの人数で歌う?
「②たくさんの人が集まってする」についてもう少し詳しく見ていきましょう。「たくさん」といいますが、どれくらいの人数が集まると合唱と呼べるのでしょうか。
一般的には、8人以上集まると合唱と呼ばれることが多いと思います。これより少ない場合は、後で述べる重唱という言い方をすることが多くなります。
逆に多い方はと言うと、こちらはは際限がなく、100人とか200人とかで歌う大合唱が行われることもあります。個人的な感覚では、50人を超えてくると「なかなか大きな合唱団だなあ」というイメージです。
また、合唱の新しい形として、近年は「バーチャル合唱団(Virtual Choir)」の取り組みも行われています。これはインターネットを通じて集まった参加者が、一人ひとり歌声を録音し、それを編集して一つの演奏として発表するというものです。なんと100カ国を超える国から、合計10000人以上が集まった例もあるようです。(参考:https://ericwhitacre.com/the-virtual-choir/history/vc6-singgently)
パートって?
次に、「③複数のパートに分かれる」について詳しく見ていきましょう。
パートというのは、歌うときの声の高さ(=声域)によって決まるグループです。高い音を歌うのが得意な人、低い音が得意な人などに分かれ、それぞれ役割分担をし、それぞれ異なる音を歌うことで多種多様の音の響き、ハーモニーが生まれます。これがパートに分かれる意味です。
パートにはどんなものがあるでしょうか。具体例を挙げてみましょう。混声合唱といって、女声・男声の両方が入り混じって歌う合唱の編成の場合、次の4つのパートに別れます。(編成について詳しくはこちら記事(合唱の種類(形態・編成)を覚えよう|声・伴奏による違いと魅力【曲紹介あり】)にて解説しています。)
- ソプラノ…女声の高音パート
- アルト…女声の低音パート
- テノール(テナー)…男声の高音パート
- バス(ベース)…男声の低音パート
①ソプラノが最も高く、続いて②アルト、③テノール、④バスの順に低い音域を担当します。
ここで、「女性・男性」ではなく「女声・男声」という漢字を使っていることに注目しましょう。読み方は「じょせい・だんせい」です。合唱のパートに関していうときにはこのように表します。
一般的に、”女性”と”男性”では”女性”の方が声が高いことが多いです。そのため”女性”が歌いやすい高めの音域のパートを指して女声と呼ぶのです。同様に低めの音域のパートを男声と呼びます。
女声・男声それぞれをもう一度2つに分けると、4つのパートを作ることができます。
女声・男声と書きますが、パートに分かれるときに重要なのはあくまで声の高さなので、実際の性別は問いません。なので、高音が得意な男性はアルトを歌っても良いですし、逆に低音が得意な女性はテノールを歌っても構いません。バスを歌える女性はレアケースでしょうが、声変わり前の”男性”はソプラノを歌えることもあります。ボーイソプラノという言葉を聞いたことがあるかもしれません。
斉唱・重唱との違いは?
合唱に似た言葉として、「斉唱」や「重唱」という言葉を聞いたことがある人もいるかもしれません。これらと合唱はどのように違うのでしょうか。
まず「斉唱」では別のパートに分かれず、全員が同じメロディーを歌います。「国歌斉唱」などという場合は、みんな同じ音を歌っていますよね。
「重唱」は各パートを1人ずつで歌う形態です。先ほど説明したパートでいうと、ソプラノ・アルト・テノール・バスを1人ずつ、合計4人で歌うということになります。
合唱と斉唱・重唱にはこのような違いがあるわけですが、全くの別物というわけではなく、合唱の特別な場合が斉唱・重唱と考えると分かりやすいと思います。
ちなみに、1つのパートを、1人で歌うの場合はどうなるでしょうか。一人だけで歌う形で、独唱(ソロ)と呼ばれます。
特徴から生まれる合唱の魅力
ここまで合唱の特徴として、「たくさんの人があつまって、パートに分かれて歌う」ということを説明してきました。では、そのことによってどんな魅力が生まれるのでしょうか。
その魅力とは、一言でいうと「ハーモニー」です。ポップスなどでもハモることありますが、合唱ではそれと比べて、より豊かで複雑な響きを持っています。他の音楽にはなかなか出すことのできない合唱独特の響きです。
この響きは、何人もの人が集まり、複数のパートに分かれ、同時に異なる音を出し、声を合わせることによって、はじめて生まれるものです。
合唱を「まだ聞いたことがない」という人は、ぜひ聞いてみて、ハーモニーを感じてみてください。次の項で音源をたくさん紹介しています。
また、「まだ歌ったことがない」という人は、ぜひ合唱団の中で歌ってみてください。声を合わせてハーモニーを作ることの喜びは、実際に歌ってみてはじめて感じられるものだからです。ちなみに、私がその魅力を知ったのは、高校の合唱部で木下牧子さんの『鴎』という曲をはじめて歌った時でした。
合唱にはどんな曲がある?
合唱曲にはどのようなものがあるのでしょう。
合唱で歌われる曲には、実はいろいろな種類があります。
学校で歌った懐かしい曲から、クラシックの名曲、ポップスを合唱用にアレンジした作品など、そのジャンルはとても幅広く、歌う場面や目的によって選ばれる曲もさまざまです。
「もっといろいろな曲を知ってみたい!」という方は、こちらの記事(【奥深い】合唱ってどんな曲がある?ジャンル別に紹介【解説あり】)をぜひご覧ください。次の6つのジャンルに分け、たくさんの曲を解説つきで紹介しています。
- 学校で歌われる合唱曲
- ポピュラー音楽(ポップス・アニソンなど)をアレンジした合唱曲
- 唱歌・民謡などをアレンジした合唱曲
- 邦人作曲家による合唱曲
- いろいろな言語の合唱曲
- いろいろな時代の合唱曲
合唱はどんなところで聞ける?
さて、先ほどはさまざまな曲の例を紹介しました。
YouTubeで音源を聴いていただけたかと思いますが、「実際の生演奏を聴いてみたい!」と思われた方もいるのではないでしょうか。やはり合唱は生演奏でこそ本当の魅力が感じられますからね。
演奏を聴ける場としては、主として以下のような機会があります。
- 合唱祭
- コンサート(定期演奏会)
- コンクール
などなど…
実は、公民館や図書館、飲食店などにチラシが置かれていることも多く、少し意識するだけで身近な演奏会の情報に出会えます。もちろん、各合唱団のSNSや公式サイトでも告知が行われていますので、そちらもチェックしてみてください。
初心者におすすめするのが合唱祭です。これは複数の合唱団(数十団体規模ほど)が順繰りに自分たちの演奏を披露していく形のコンサートです。
いろいろな曲、いろいろな団体の演奏が聴ける上に、入場料も安いことが多いです。
「都道府県名+合唱祭」などで検索すれば開催情報が見つかりると思います。
ぜひこういった機会に足を運んで、合唱の魅力を感じてみてください。
合唱にはどうやって参加する?
聴いてみるだけではなく、「実際に参加したい!」と思った人もいるでしょう。
どんな団体がある?
聴くだけでなく、「自分も歌ってみたい」と思われた方ももいらっしゃると思います。
そのような場合、自分が入れそうな合唱団、グループを探してみましょう。
たとえば以下のような団体があります。
- 学校の部活動(合唱部)
- 大学のサークル・部活
- 地域の合唱団
合唱に関わったことがない人からすると、こういったグループの存在は普段意識することがほとんどないかもしれません。
しかし、実は全国には数え切れないほどたくさん合唱団があり、日々練習や本番を行っているのです。
あなたがお住まいの地域にも、きっと合唱団があるはず、まずは「地域名・合唱団」などで検索してみてください。
「これは」という団体が見つかったら、ぜひ練習見学を申し込んでみましょう。実はほとんのどの合唱団においても人手不足が悩みの種だったりするので、初心者の方であっても、かなり熱烈に歓迎してくれるはずです。多くの団体が新入団員を歓迎しています。
合唱部・合唱団でやること【練習~本番までの流れ】
合唱団でやることは主に次の流れになります。
- パート分け…自分がどのパートで歌うか決定
- 発声練習…合唱の基礎となる「声」のトレーニング
- パート練習…パートに分かれて行う練習
- 全体練習・アンサンブル…メンバー全体で合わせて行う練習
- 本番…合唱祭・コンサート・コンクールなど
日常的な練習では②~④を中心に行います。
これらの他にも、ボイストレーニングや合宿があったり、団内コンサートがあったり、はたまた交流会・飲み会などが開催される団体もあります。
合唱団の選び方
初めての場合、合唱団を探す際、どんなことに気をつければよいかがわからないと思うので、簡単にチェックポイントを挙げておきます。
団体のレベル
これはかなり重要です。
「入ったは良いものの曲が難しくてついていけない!」ということになってしまわないよう、注意しましょう。
判断が難しいときは、「今練習している曲」について尋ねてみるのが一つの方法です。全く聞いたことのないような外国語の曲が多い場合は、初心者の方には少しハードルが高い可能性があります。(外国語の曲を敬遠して欲しいわけではないのですが…。)
練習見学や体験会などを通じて、なんとなくでも良いので練習している曲のレベル感を掴んでみてください。
「歌えなかった」というのは、初心者ですから当然ですから大丈夫です。ですが、「何をやっているのか全く訳がわからなかった」という場合は少し様子を見たほうが良いかもしれません。
また、パート練習・ボイトレの有無について聞いておくのもよいでしょう。
パート練習というのは、各パートに分かれてそれぞれの音を練習することです。これがあると初心者の方でも練習についていきやすいです。
ボイトレはボイストレーニングのこと。声楽家の先生を招いて行われることが多いです。合唱は声の芸術ですから、声のトレーニングは非常に大切。初心者のうちに発声の基本をつかめるよう、ボイトレに参加する機会があると良いと思います。
練習場所
合唱団に入ると、月に2~3回、ないし週1回くらいの練習が開催されます。(団によってはもっと多いこともあります。)
そのため、通いやすい場所で練習が行われているかどうかもチェックしておきたいポイントです。
練習頻度
先ほど触れましたが、練習頻度が自分のペースに合っているかどうかも大切です。
毎回の練習に無理なく参加できる頻度の団体を見つけましょう。
また、初心者の場合回数が少なすぎる場合にも注意したいです。というのも、練習と練習の間の期間があまりに空きすぎてしまうと、基礎力がなかなか身につきませんし、覚えた曲も忘れてしまいやすいからです。
ある程度経験を積めば自分で練習できるようにもなりますが、初心者のうちは難しいので、週1回程度は練習のある団体を選ぶのがおすすめです。
おわりに
お読みいただきありがとうございました。
「合唱ってどんな感じ?」ということを、ざざっとまとめてみました。
記事としては長くなりましたが、これでも合唱のほんの入口に触れたに過ぎません。
ですから、「よく分からなかった」「もっと知りたい」と感じられた方も多いと思います。
次の記事から、様々なトピックについて、より詳しく解説していきたいと思うので、お楽しみに。
引き続き、弊ブログをご利用くださりますと幸いです。