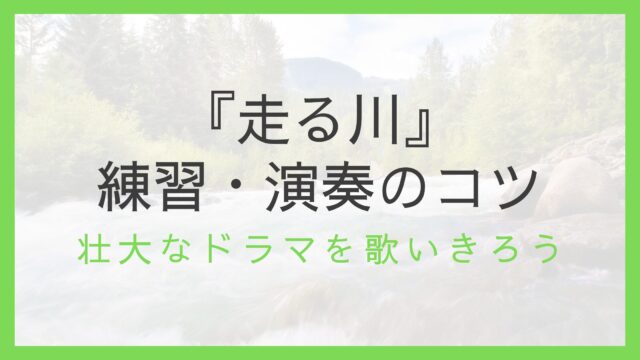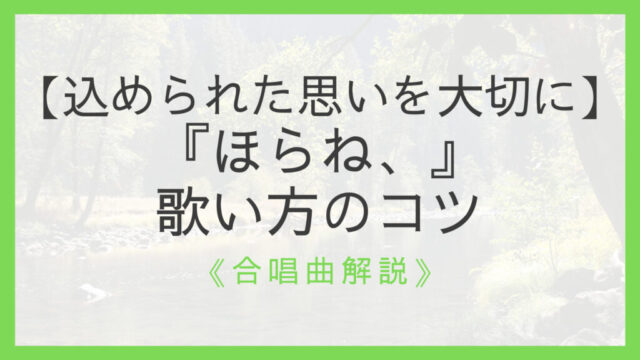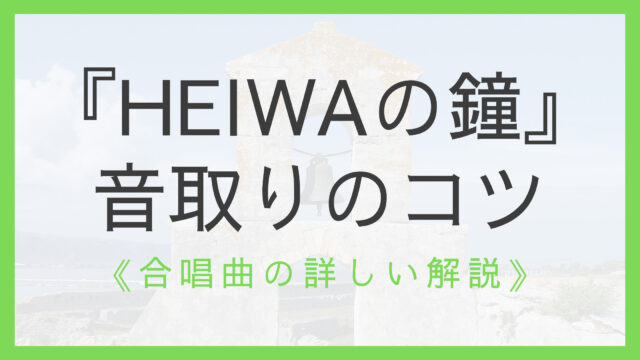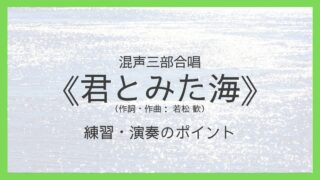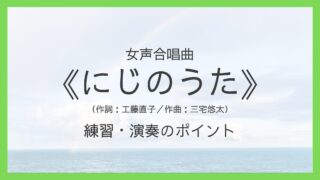【混声三部】《響きあう命》和音と転調についての考察
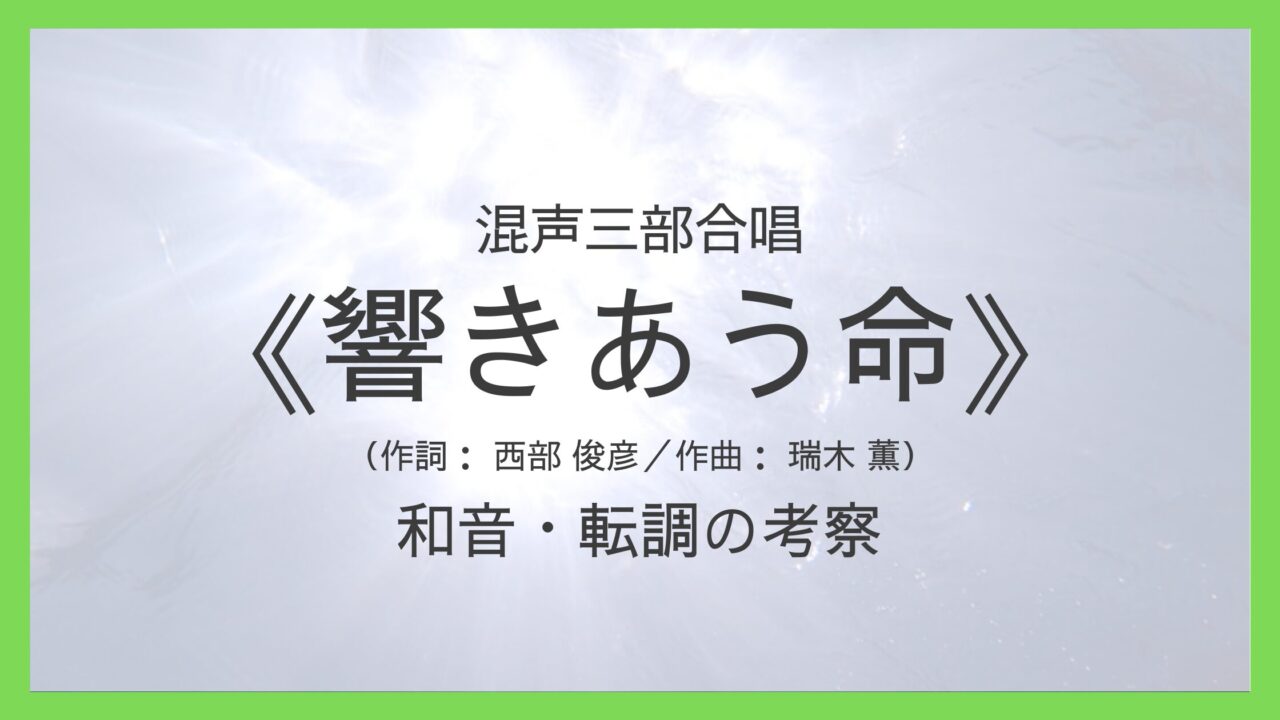
「《響きあう命》の転調について教えてほしい」というリクエストをいただきました。
そこで練習番号ごとに、和音と転調について考察・解説してみたいと思います。
もくじ
《響きあう命》の和音と転調
楽譜に記載されている練習番号ごとに進めたいと思います。
練習番号は場面の切り替わりであると同時に、転調の境目となっていることも多いです。
逆に、練習番号が書かれていない楽譜に、自分で練習番号をつける場合は転調しているところは目印になります。
【冒頭】1小節~
【冒頭】の場面は♯が2つの調です。
この場合、ニ長調か変ロ短調の2通りが考えられます。
どちらかといえば明るい感じを受けること、またDのコード(「レ・ファ♯・ラ」の和音)が中心となっていることから、ニ長調で書かれていると判断します。
【A】4小節~
【A】で早速転調しています。♭が1つですからヘ長調かニ短調の可能性がありますが、やや暗い印象があるのでニ短調となります。
5小節1拍目のコードはB♭M7で、ニ短調におけるⅣの和音にあたります。役割で言えばサブドミナントです。サブドミナントで曲を始めるのは、しばしば見られる手法です。
5~6小節にかけて、B♭M7 → C → Dmと進みます。このDmがニ短調におけるトニック(主和音)となります。
トニックやサブドミナントは和音の役割を説明する言葉です。
トニック(Tonic)=Ⅰ … 曲の「安定」や「帰る場所」となる和音。
ドミナント(Dominant)=Ⅴ … 次に進みたくなる「不安定さ」「高まり」を持つ和音。
サブドミナント(Subdominant)=Ⅳ … トニックとドミナントをつなぐ、中間的な役割の和音。
「Ⅰ=安定の家/Ⅴ=外出へのきっかけ/Ⅳ=その途中の景色」といった比喩で説明されることもあります。
7~8小節ではB♭M7 → C → Dと、最後が明るいメイジャーコードとなっています。ピカルディ終止的な進行で、光が差し込んでくるような印象を受けます。
- Dの和音…「レ・ファ#・ラ」
- Dmの和音…「レ・ファ・ラ」
【冒頭】のニ長調と【A】のニ短調は、長短の違いはありますが、主音(この場合は「二(=レ)」を同じくする同主調(どうしゅちょう)の関係にあります。
同主調では、♯をプラス、♭をマイナスとしてカウントすると、±3の関係になります。
例えば、今回の場合であれば【冒頭】では♯×2なので+2、【A】では♭×1なので-1とカウントし、その差は-3となります。
同主調では主音が変わらないため、転調は比較的容易ですが、長短が切り替わることになるため、大きく曲調が変化します。
【B】15小節~
【B】に入る2小節前の前奏から新しい調へと移っています。♭が1つで、明るい印象を受けるのでヘ長調です。
【A】と【B】では調号は変わりませんが、短調・長調の違いがあります。
このように、調号が同じで長短が異なる調の関係を平行調と呼びます。
ニ短調の主音は「二(=レ)」、ヘ長調の主音は「へ(=ファ)」です。このように主音がスライドするというイメージで捉えると良いでしょう。
平行調は調号が変化しないため転調しやすく、曲調の変化も比較的マイルドです。
【C】23小節~
【C】からもヘ長調が継続されます。
29~31小節でトニック(=F)の和音が現れ、場面の区切りをつくっています。
【D】33小節~
ここから調号なしに変わります。その場合考えられるのはハ長調かイ短調となりますが、ここは暗い曲調ですので、イ短調となります。
33小節1拍目のピアノパートの鳴らす和音がAm(「ラ・ド・ミ」)であることも、調判定の根拠になります。
【D】に入る直前、32小節のピアノパートの右手の16分音符のパッセージに注目すると、シに♮がついています。ヘ長調でもともとあった「シ♭」が打ち消されており、これがイ短調への呼び水となっています。
【E】37小節~
【E】は進行が複雑なため、分割して説明していきたいと思います。
37~38小節
引き続き調号はありませんが、ピアノパートの左手に♭が出てきています。このフラットは「メロディーを少し変化させる」といった種類の臨時記号ではなさそうです。そこでここでは「臨時記号を使った転調」のパターンを疑ってみます。
臨時記号には実は「つきやすさ」があります。順番としては次のようになります。
- ♯のつきやすさ…「ファドソレラミシ」の順(♭の逆順)
- ♭のつきやすさ…「シミラレソドファ」の順(♯の逆順)
※左に行くほどつきやすい
例えば、「ラ」と「シ」の間にある音を表したいとき、「ラ♯」と「シ♭」の2通りが考えられるわけですが、「ラ」に対する♯と、「シ」に対する♭では、後者のほうがつきやすくなります。そのため見かける頻度も多くなります。
なお、はじめから調号として♯や♭がついているような曲の場合、それも加味したうえでつきやすさを考える必要があります。例えば♯が4つの調では、はじめから♯が「ファドソレ」までついていますので、「シ♭」よりも「ラ♯」のほうが現れやすくなります。
調号として♯や♭がたくさんついた楽譜を探してみてください。
♯では「ファドソレラミシ」の順、♭では「シミラレソドファ」の順で調号がつけられていることが分かると思います。
楽譜に戻りましょう。37~38小節では♭が「シ」についています。「シ」は一番♭がつきやすい音です。次につきやすい音は「ミ」ですが、こちらは♮です。このことから、この2小節間は♭1つの調で書かれているのではないか、と仮定します。
コード進行を見てみると、B♭M7 → C → Fとなっています。Fで落ち着いた感じがするので、これをトニック(Ⅰ)としてみます。すると先ほどのコード進行はヘ長調におけるⅣ → Ⅴ → Ⅰのオーソドックスな進行であることが浮かび上がってきます。
以上の考察から、この2小節間はヘ長調で書かれていると結論づけられます。
39~40小節
続いて39~40小節を考えてみましょう。同様にして臨時記号を調べると、ここはどうやら♯系の調で書かれているようです。
♯のつきやすさは「ファドソレラミシ」です。順番に見ていきますと、「ファ」にはつき、「ド」にはついていません。「ソ」と「レ」にもついていますが、それよりも♯がつきやすいはずである「ド」につかないことが分かっているので、これらはいったん置いておきましょう。
そうすると♯1の調、つまりト長調かホ短調の可能性が出てきます。どちらかといえば暗い雰囲気を感じますので、いったんホ短調としてみます。
次にコードを見ると、F♯m7-5 → B7 → Eとなります。これはホ短調のもとではⅡ7 → Ⅴ7 → Ⅰの進行に似ています。違うのはEのコード。本来ならホ短調のトニックはEm(「ミ・ソ・シ」)となるところですが、ここではE(「ミ・ソ♯・シ」)となっており、先ほども登場したピカルディ終止的な進行となっているのです。「ソ♯」はそのための役割があったのですね。
少し戻って39小節の「レ♯」は、ホ調における和声的短音階で現れる音と解釈すればよさそうです。
したがって、39~40小節では「ファ」だけに調号的な役割を持つ「継続的な」臨時記号が使われ、「ソ」「レ」につく♯は「一時的な」臨時記号として使われていることが分かります。
41小節~44小節
【E】最後の4小節です。ここは解釈に相当悩みました。これが正しいとは限らないのですが、私なりの考えを紹介しておきたいと思います。
まず結論としてはこの4小節間をハ長調とみなします。41小節のコード(=C)をトニックと捉えるわけです。
42小節で「ファ♯」が出てきますが、ハ長調におけるドッペルドミナント(=D)の構成音として理解します。42小節のソプラノには「ソ♯」が出てきますが、これは聴いた印象で、メロディーに変化をつけるための「一時的な」臨時記号であることが分かります。
さて、ドッペルドミナントに続く和音は通常Ⅴ、つまりGのコードになるところですが、実際のはB♭7となっています。楽譜は「ソ♯」で書かれていますが、これを「ラ♭」と読み替えれば、ハ長調における同主調、つまりハ短調から借用してきた和音と解釈することができます。♭がつくことによるブルーさと、7度の音がつくことによる複雑さが場面にマッチしています。
44小節はBm7 → D/Eと進みます。D/EはE7sus4の変形した形とも取れ、イ長調でのドミナントの役割を果たします。構成音を比較すると、共通する音が多いことが分かると思います。ドミナントの持つ高揚感や推進力が【F】に向かう盛り上がりを形作ります。
構成音の比較
- D/E: 「ミ・レ・ファ・ラ」
- E7sus4: 「ミ・ラ・シ・レ」
D/Eは【F】に入ってAに解決し、イ長調に転調します。44小節はいわば「転調へ向かう助走」という位置づけですが、ここからすでにイ長調に入っているとみなせば、Bm7 → E という進行はⅡ → Ⅴとなり、典型的なツー・ファイブの進行となります。
【E】から【F】へは、ハ長調 → イ長調という転調が起こっているわけですが、これらの調の関係性は、間にイ短調を挟むとよく分かります。
- ハ長調 → [イ短調(=平行調)] → イ長調(=同主調)
つまりイ長調は、ハ長調に対する平行調の同主調となるわけです。これまでに説明したように、平行調どうし、同主調どうしの転調は比較的簡単に起こります。そのため、今回のようなパターンも少し工夫すれば実現しやすいのです。
転調前と転調後にこのような関係性が見いだせることも、41~44小節をハ長調と解釈した理由になります。
【E】について、すべて転調しているという前提で解説しましたが、転調はしておらず、すべてを借用として解釈することも可能です。
その場合、【E】はこれまでと同じイ短調で書かれており、ヘ長調やホ短調から和音を借りてきていると捉えることになります。
そうすると、【E】→【F】の転調はイ短調→イ長調への同主調間での転調となり、むしろこのほうが作曲者の意図するところかもしれません。
【F】45小節~
ここから♯3つの長調、イ長調へ転調し、明るく前向きな曲調へと変化しています。
転調前のコード進行は【E】で触れた通りです。
45~47小節にかけてベースラインをたどると、「ラ → ソ♯ → ファ♯ → ミ → レ」と順次下降していっています。安定感のある進行です。
【G】53小節~
引き続きイ長調です。
ここはトニックであるAではなく、サブドミナントのDM7からフレーズが始まります。
非常にスピーディーで、推進力のある進行となっています。
【H】57小節~
再び調号なしとなります。
60小節を除けば臨時記号はつきませんので、ハ長調またはイ短調で書かれていると捉えて良いでしょう。そうすると、【G】との関係は同主調ともなります。
長調か短調かでいうとはっきりしないところがありますが、メロディーを見ると「ラ」の音を中心にしていることが分かりますので、イ短調の方をここでは採用したいと思います。(登場するコード(G、F、C)から、ハ長調と判断することもできそうです。)
【H】は次の調に向かうための複雑なコード進行をしています。
まとめると次のようになります。
G6 → FM7 → Dm7 → CM7 → Bm7 → Cm7 → F7
やや強引な進行ですが、「ソ → ファ → (ミ) → レ → ド → シ」下降していくベースラインが進行に説得力を与えています。
下線の引いた「Cm7 → F7」の進行は変ロ長調におけるツー・ファイブ(Ⅱ → Ⅴ)進行となっており、次なる転調を導きます。
【I】61小節~
先ほど書いたように、変ロ長調に転調します。明るい調で、【F】と同じく前向きな音楽となっていきます。
ベースラインに関しても同様で、「シ♭ → ラ♭ → ソ → ファ → ミ♭ → レ → ド」と順次下降していきます。
64小節後半~65小節では、ベースラインが「ファ → ファ♯ → ソ」と半音ずつ上行していき、短調のコード(Gm)を導きます。ここで一瞬、影のある響きを用いて引き締めることで、その後のクレッシェンド~ffでのカタルシスをいっそう高めています。
【J】71小節~
調号は変わりませんが、ここからはト短調となります。変ロ短調との関係は平行調です。
71小節の1拍目で、ピアノパートが「ソ」(=ト音)を強く鳴らすことが、ここからト短調になることを印象づけています。
ここでのコードは、通常Gm(「ソ・シ♭・レ」)を用いるところですが、ぶつかる和音「ソ・ラ・レ」を用いることで、激しさと力強さを表現しているように思います。
まとめ
さいごにまとめとして、場面ごとの調を振り返っておきたいと思います。
- 【冒頭】ニ長調
- 【A】ニ短調
- 【B】ヘ長調
- 【C】ヘ長調
- 【D】イ短調
- 【E】ヘ長調 → ホ短調 → ハ長調
- 【F】イ長調
- 【G】イ長調
- 【H】イ短調
- 【I】変ロ長調
- 【J】ト短調
《響きあう命》を実際に練習・演奏されるときには、「ここでこのような和音・転調が使われているのはなぜだろう?」ということを、歌詞や他の音楽的要素(メロディーや強弱)と照らし合わせて考えてみてください。
より深く、説得力のある表現ができると思います。
練習・演奏でのポイントはこちら(混声三部《響きあう命》練習・演奏のポイント|作曲家の工夫を読み取ろう)で解説していますので、合わせてご利用ください。
また、なにか質問がありましたら、お問い合わせよりお気軽にご連絡いただければと思います。