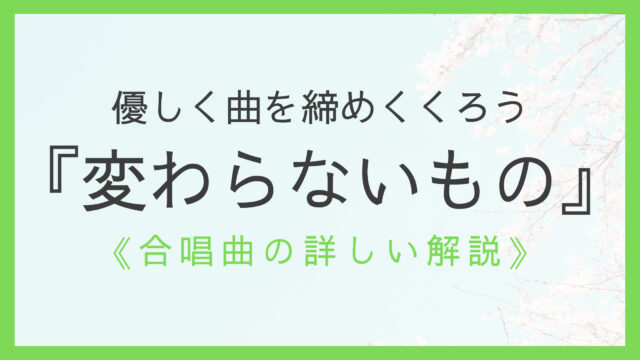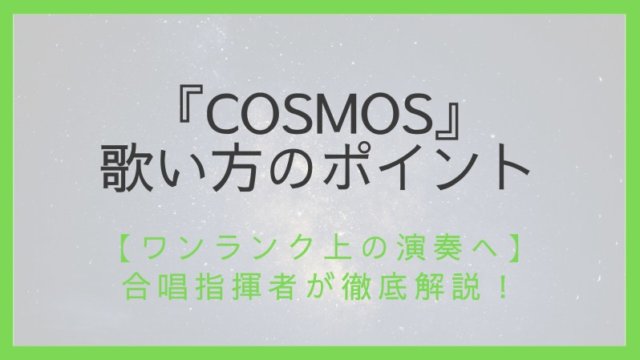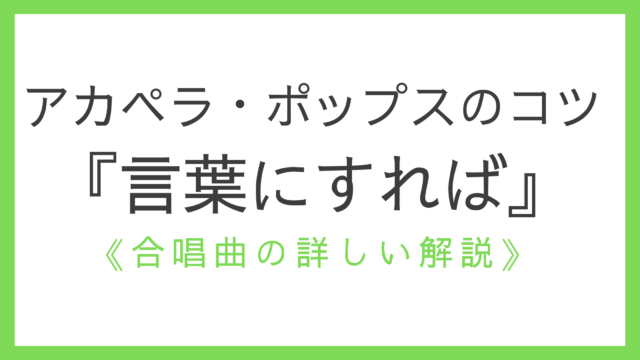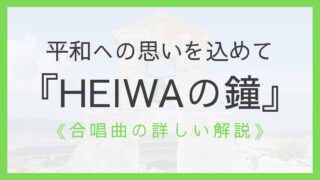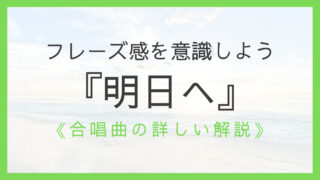合唱曲《Gifts》練習・演奏のポイント|サビの歌詞を印象的に伝えよう
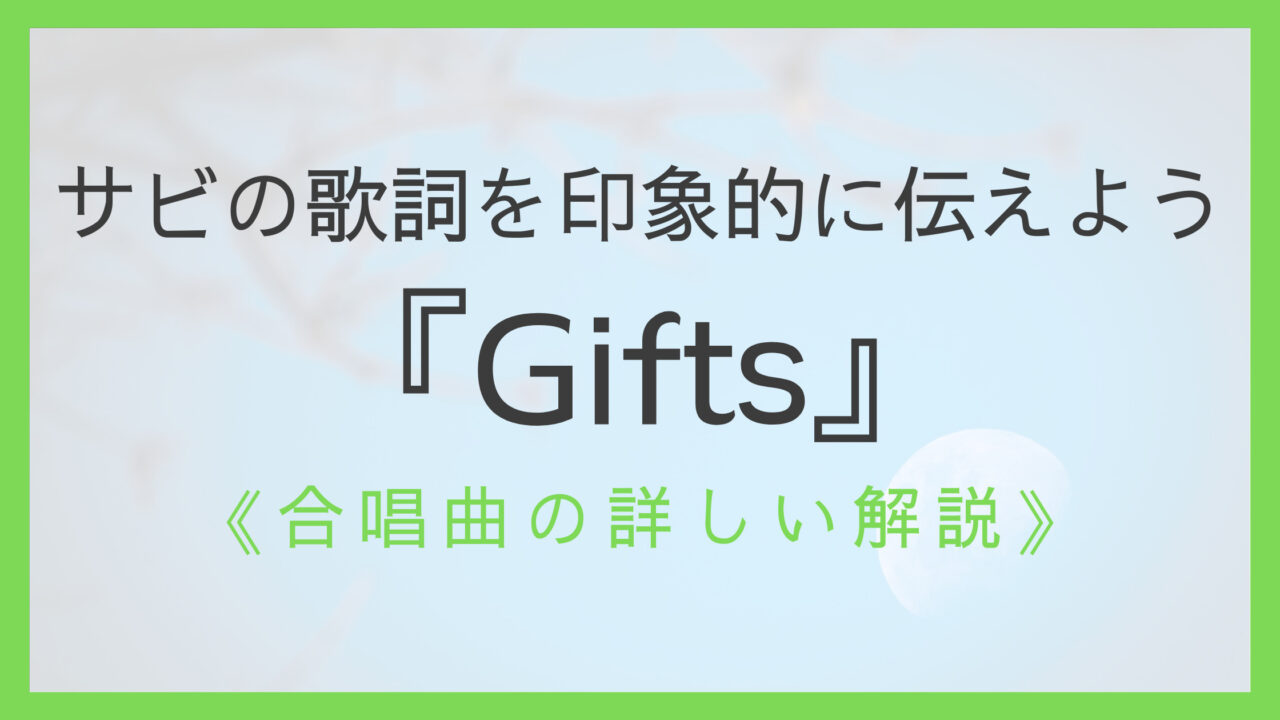
《Gifts》はSuperflyの越智志帆さんが作詞、作曲家の蔦谷好位置さんが作曲し、それを大田桜子さんが合唱曲に編曲した作品です。Nコン中学の部2018年度の課題曲でもあります。
この記事では練習する上でのポイントを詳しくまとめています。この記事を読みながら練習すればワンランク上の演奏に繋がるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
もくじ
合唱曲《Gifts》練習・演奏のポイント

【A】メロディーを丁寧に歌おう
【A】の場面ではまずアルトが、続いてアルト+男声がメロディーを歌います。このメロディーを丁寧に歌いましょう。第一印象がここで決まります。
ここでのポイントは次の3点です。
- 低い音をよく狙って
- 付点のリズムを正確に
- アルト・男声で聴き合って
1. 低い音をよく狙って
このメロディーではとても低い音(「ラ」)から歌い出します。
こういった場合はあらかじめ音をしっかりイメージして、よく狙って歌い出すことが大切です。
声が出にくい人も多いと思うのですが、だからといって闇雲に声を出そうとすると、音が外れ、全体の響きがどんどん濁っていきます。
逆によく狙って歌うことで、音がそろえばメロディーをクリアに聞かせることができるようになるはずです。
パート練習では、入りの音(=「ラ」)で伸ばしてみて、正確に歌えているか、音がそろっているかをチェックすると良いと思います。
音域がかなり低いですので、どうしても音量が出にくいことがあると思います。その場合、【A】の部分に限ってソプラノの一部の人がアルトのメロディーを手伝ってもよいでしょう。ソプラノはメインのメロディーを引き立てるオブリガートの役割で、音量もpですので、人数が少なめでもかまいません。
また、パートの人数バランスが悪い場合、女声が前に並ぶオーダー(並び方)にすることを考えても良いでしょう。
2. 付点のリズムを正確に
“かげんの”、”つきが”などのメロディーは付点8分音符+16分音符のリズムが特徴です。
このタイミングを正確に歌えるよう練習しておきましょう。
このようなリズムを攻略するコツは、エイトビート、つまり8分音符を意識することです。例えば【B】ではピアノパートが8分音符を刻んでくれており、自然に8分音符を感じることができると思います。このような箇所では13小節のようなリズムも歌いやすく、苦労は少ないはずです。
そのことを【A】にも応用してみましょう。練習の際にはテンポを示すために4分音符を叩くと思います。それを8分音符で行ってみましょう。これによりタイミングを取りやすくなるはずです。この場合、付点8分音符+16分音符での16分音符は叩くタイミングと重ならないのが正解です。
慣れてきたら8分音符で叩くのをやめ、再び4分音符にします。このときも8分音符の単位でリズムを感じることを忘れずに、また急ぎすぎずに歌いましょう。
3. アルト・男声で聴き合って
6小節からはアルトに加えて男声もメロディーに加わり、低音の重厚感が加わります。
お互いの声をよく聴き合って、一本の線にまとまるようなイメージで歌いましょう。
オクターブユニゾンで、全く同じ音を歌うわけですが、どちらかといえば主役はアルト。男声はアルトの声をかき消してしまわないように、寄り添うようなイメージで歌いましょう。
アルト・男声の合同でパート練習をしてみても良いと思います。
【B】音楽の変化を感じて
【B】では次のことに気をつけましょう。
- リズムとテンポの変化を感じて
- メロディーの受け渡し
1. リズムとテンポの変化を感じて
【B】からはテンポが若干早くなるので、まずはそれを頭に入れておきましょう。(とは言うものの極端に速くして、という指示はないので程よく。)
またピアノパートの伴奏形に注目すると、これまでは比較的ゆったりとしたリズムだったのが、【B】からはスタッカートの8分音符を刻むリズムになっています。
これらのテンポ・リズムの変化をしっかり感じて歌いましょう。
2. メロディーの受け渡し
【B】では、細かいスパンでメロディーを担当するパートが入れ替わります。1パートがずっとメロディーを歌い続けるのではないことに注意しましょう。
まとめると以下のとおりです。
- “そのないもの”…主にアルト
- “ねだるクセ こころは”…ソプラノ
- “いじけちゃうよ”…主にアルト・男声
- “あのこに”…主にアルト
- “なりたくて”…ソプラノ
- “じしんの”…ソプラノ・男声
- “カケラもないこと”…ソプラノ
こういった場合、「今一番目立つべきパートはどこか?」ということを考えながら練習することが大切です。
【C】思いを込めて歌い上げよう
ここからはサビになります。f(フォルテ/強く)でしっかり盛り上がりを作りましょう。
それと同時に、「大事な言葉、伝えたい歌詞はどれかな」ということを意識してみましょう。
“ちち”や”はは”といった言葉はぜひ伝えたい言葉です。16分音符で短いですが、はしょらずに、丁寧に歌いましょう。
これらの言葉を少し強調して歌うようにすると、楽譜にある”思い込めて”に繋がってきます。
【D】役割を意識してタイミングをはかろう
ここからは2コーラス目になります。
ここではパートごとの役割に注目してみましょう。
38~41小節では、ソプラノがメロディー、アルトはソプラノに対するハモリ。
それに対し男声はメロディーの隙間を埋めるようなはたらきをしています。
[例]
- 女声:”ひとの”で伸ばす → 男声:”Uh”で入る
- 女声:”なみを”で伸ばす → 男声:「ソ♯ラ♯」と動く
続く42~45小節では、男声は歌詞でメロディーを追いかける役割に変わります。
[例]
女声:”みんな” → 男声:”みんな”
女声:”それぞれ” → 男声:”それぞれ”
どちらのパターンにしても男声はメロディーをよく聴いて、入るタイミングをはかることが大切です。
聴き合わうことをせずに自分のタイミングで歌ってしまうと、どこかチグハグで噛み合わない印象になってしまいます。
【E】掛け合い・合流の流れをつかもう
【D】に続いてこの場面でもパートの役割に注目してみましょう。
【B】で書いたとおり、ここでもメロディーを担当するパートが細かく入れ替わります。
男声は1小節遅れで歌い出し、”こころは”、”いないから”から合流するという流れです。
このように「ずれる → 合流」というパターンは頻出ですので、まずはこの流れを頭に入れておきましょう。
そして合流するところでは、「ここでタイミングがそろうぞ」と一体感を感じることが大切。
そうすることでメッセージの力強さも加わってきます。
【F】言葉を伝えるポイント
2回目のサビです。歌い方は1回目(【C】)と同様ですが、言葉を伝えるポイントをもう少し詳しく説明したいと思います。次の3点です。
- 裏拍の食いつき
- 子音の強調
- “あぁ”の歌い方の工夫
1. 裏拍で食いつき
《Gifts》では8分休符や16分休符で始まるフレーズが多くなっています。
【F】の場面では例えば”こえが”、”えいがが”などの部分です。
(休符にはなっていませんが、”ききたい”、”ないた”も裏拍です。直前が付点音符のため。)
このような裏拍始まりのフレーズでは遅れないように気をつける(=食いつき)ことが必要になってきます。
2. 子音の強調
子音というのは例えば「カキクケコ(ka ki ku ke ko)」というときのkなどのこと。
kの他にs, t, n, h, mなども子音です。
言葉を伝えるためにはこの子音がとても大切。
“ききたい”、”こえが”のk、”ないた”のn、”ほんや”のhなどの子音を少し強調するとグッと歌詞が聞き取りやすくなります。
3. “あぁ”の歌い方の工夫
“あぁ”という歌詞は感嘆詞で、それ自体に意味はありませんが、気持ちの乗った重要な言葉です。
「あー」といった感じで棒読みにならないよう、ニュアンス・表情を持って歌いましょう。
【G】ダイナミクスレンジをアピールしよう
【G】は前後の場面をつなぐブリッジ。
“軽快に”と書かれているように、少し歌い方を変えてみましょう。ピアノパートの8分音符を感じることも忘れずに。
音量的にはmp → mf → fとしだいにクレッシェンドしていく作りになっています。
このダイナミクスレンジ(音量の幅)をしっかりアピールできると良い聴かせどころになります。
どのタイミングでどれくらいまで持っていくかをメンバー内で共有しておくと良いでしょう。
【H】クライマックスに向けて気持ちを高めよう
【H】からは最後のサビに入ります。
ここから転調(ニ長調 → 変ホ長調)し、キーが半音上がります。それにより音域が上がるので自動的に盛り上がる仕組みです。
85小節からはff(フォルティッシモ/とても強く)で、この曲最大の音量となります。
ここでクライマックスになるように計算して全体を構成しましょう。音量だけでなく、ここで歌われる歌詞・言葉に対する気持ちも強く持つと、それが歌声に表れて感動的な場面になると思います。
その後、最後のシーンでは終わりに向かってmf → mp → pと小さくしていき、曲を締めくくります。
祈りのような気持ちで、”ねがいをこめて”、”あなたがあなたでありますように”という歌詞を表現しましょう。
ポイントの振り返り
- 【A】メロディーを丁寧に歌おう
- 【B】音楽の変化を感じて
- 【C】思いを込めて歌い上げよう
- 【D】役割を意識してタイミングをはかろう
- 【E】掛け合い・合流の流れをつかもう
- 【F】言葉を伝えるポイント
- 【G】ダイナミクスレンジをアピールしよう
- 【H】クライマックスに向けて気持ちを高めよう
「もっと詳しく解説してほしい!」という場合は、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。補足・追記いたします。