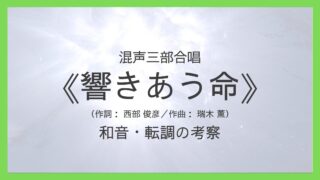【混声三部】《君とみた海》練習・演奏のポイント(作詞・作曲: 若松 歓)
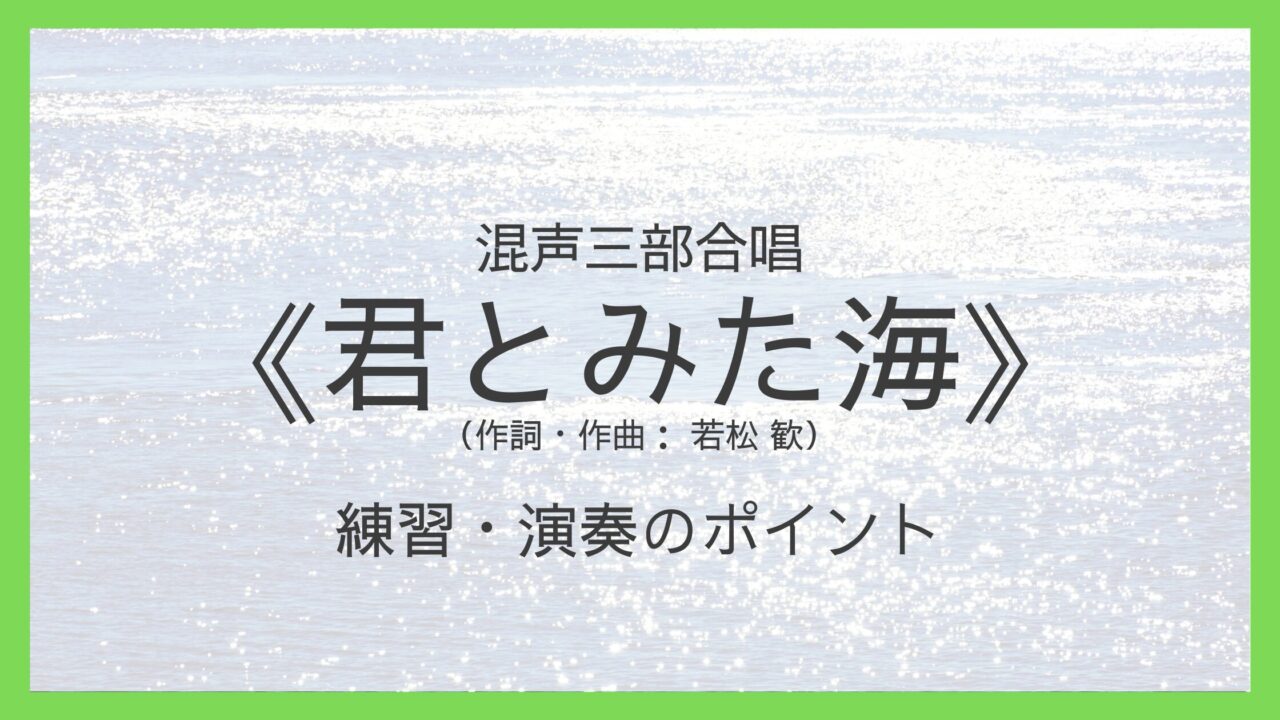
《君とみた海》はさわやかさと切なさ、そして力強さをあわせ持った素敵な作品です。
この記事では《君とみた海》の演奏に役立つポイントを、練習番号に沿って具体的に解説しています。
この記事を参考に、ぜひ練習・演奏に挑戦してみてください。
《君とみた海》練習・演奏のポイント
練習番号(【A】【B】…)に沿って解説していきます。
なお、解説の都合上、38小節を【C’】、47小節を【D】としています。
【前奏】1小節~
雄大な海のイメージで
冒頭ではいきなりff(フォルティッシモ)の音量が登場しています。
「とても強く」を意味する記号ですが、単に大きく弾けばよいというわけではありません。
ここでは「雄大な海」をイメージして弾いてみましょう。
左手の低音のアクセントは海の深さ、右手のアクセントは水面に反射する光のきらめきのように。
フレーズ感の作り方
前奏部分の右手には、1小節ごとにスラーでフレーズのまとまりが示されています。
細かな6連符をこなすことだけにとらわれず、大きな流れを意識しましょう。
合唱を自然に導こう
5小節からデクレッシェンドが始まり、f → mf → mpと次第に音量を落とし、背景として引き下がっていきます。
自然に合唱を導くようなイメージで、場面を収めていきましょう。
【A】8小節~
ユニゾンをよくそろえて
【A】の合唱パートはユニゾンでメロディーを歌います。
全員が同じ音を歌うことになりますので、音をよくそろえることを意識して練習しましょう。
注意しておきたいのはリズムと言葉です。特に16分音符の裏拍の食いつきには注意が必要です。
「食いつき」の箇所
- はちがつの
- からだ
- ふるさとの(2番)
- こころ(2番)
こういった箇所では遅れないようにし、子音(h,k,f)も早めに歌うことを忘れないようにしましょう。
【B】16小節~
転調を鮮やかに
【B】では変ニ長調からホ長調へと調が変わります。
「ここで雰囲気が変わるぞ」ということを知っておき、鮮やかに切り替えられるよう、イメージしておきましょう。
ポイントは女声の”Uh”。直前に歌っていた「ミ♭」から「ミ♮」に変わります。この「ミ♮」の音は、【A】には使われていなかった音で、転調を印象づけています。
男声の入りも、音をしっかりイメージして、さらに音量をmf(メゾフォルテ/少し大きく)へと一段階上げてクリアに入りましょう。
ハーモニーのバランス
ユニゾンだった【A】に対し、【B】ではハモリが加わります。これも転調と並んで大きな違いです。
例えば18小節では、ソプラノと男声がメロディー、アルトがハモリを担当します。人数が少なくなるアルトは少ししっかりめに歌うことを意識しましょう。そうすることでハーモニーのバランスが取りやすくなります。
続いて22小節では女声(ソプラノ+アルト)がメロディー、男声がハモリを担当します。ここでは男声の音が比較的高く、目立ちやすくなっています。そのため、男声は女声に寄り添うようにして、繊細に歌うとよくハモります。乱暴に歌うとメロディーをかき消してしまうので注意しましょう。
【C】25小節~
短調に厳しさを感じて
【C】では再び転調があります。調号としては【A】と同じですが、ここは変ロ短調、つまり暗い調となります。
暗い響きとffの音量からは、海の厳しさが感じられます。歌詞の内容と合わせて、それにふさわしい表現をしてみてください。
さかのぼって、24小節のピアノパートは転調の前触れとも言えるコード(G♯sus4 → G♯ → F7)を弾いています。このコード進行の響きをよく感じておくことが【C】での転調を決めるポイントです。
調号(ト音記号・へ音記号とのところについている♯や♭)は一つで2通りの調を表すことができます。
例を挙げてみましょう。
- 調号なし…ハ長調/イ短調
- ♯1つ…ト長調/ホ短調
- ♭1つ…ヘ長調/ニ短調
最終的に長調なのか、短調なのかは実際に聞いてみたときの印象や、主音(その調の中心的存在)となる音によって判断します。
今回のように♭が5つの場合は、変ニ長調または変ロ短調を表します。
【A】では明るい感じがするので変ニ長調、【C】は暗い感じがするので変ロ短調と判断できます。
曲を聴かずに楽譜上から判断する場合、私はフレーズの最初の最低音に注目することが多いです。
【A】では8小節のピアノパートの左手が「レ♭=変二音」を弾いているので、それが調の中心的な音と分かり、調も変ニ長調だと分かります。
同様に【C】の25小節では、「シ♭=変ロ音」を弾いているので、変ロ短調だと分かります。
こちらの記事(【簡単】音楽の調の見分け方|主音を見つける方法2つ【語呂合わせあり】)も参考にしてみてください。
ハーモニーの確認
調と合わせて確認しておきたいのがハーモニーです。
【C】最初の”うみよ”はコードで言えばB♭mとなっています。
B♭mの構成音
- 第5音「ファ」…アルト
- 第3音「レ♭」…ソプラノ
- 根音「シ♭」…男声
“うみよ”で伸ばして、ハーモニーを確かめてみましょう。
男声の「シ♭」は和音を支える根音となりますので、しっかりと歌うとバランスが取れます。
また、和音の練習をするときはアカペラ(ピアノパートなし)で行うと、声のハーモニーをよりよく感じられます。
音程は合っているけどあまりハモった感じがしない、というときは、ウの母音が潰れてしまっていて響きが足らないことが考えられます。口の中の奥行きを意識して、よく響かせるように意識してみましょう。
ブレイクを大事に
32小節1拍目の合唱パートは4分休符となっており、ピアノパートのアクセントが響きます。
こういった休みを「ブレイク」と呼ぶことがありますが、ここで空白の時間を作ることで、次の”かがやいてる”が文字通り輝き、印象的なフレーズになります。
直前、31小節のクレッシェンドの足並みや、その後のブレス(息継ぎ)のタイミングをしっかりそろえると、ブレイクがより活きてきます。
【C’】(38小節~)
ffを作り直そう
【C’】ではサビのフレーズが繰り返されます。
ここでは再びffを作り直すようなイメージで、盛り上がりをつくりましょう。
他とは違う動きをアピールしよう
39小節のソプラノのように、他のパートと異なる動きをしているフレーズはアピールしどころです。
パートが分かれるので人数が少なくなってしまいますが、存在感が欲しいところです。
クライマックスと強弱表現
44小節からが曲全体を通してのクライマックスシーンです。
mfでいったん音量を落とすことで、聴いている人を引きつけるような効果が期待できます。
そこからのクレッシェンドはレンジ(音量の幅)を広く、また急速に大きくしていくことで見せ場を作りましょう。
ラストのffは一番盛り上げて歌いたいところです。充実した響きで歌いましょう。
和音の確認
45小節ではアルトと男声が分かれ、複雑な和音を形作ります。コードネームで言えばE♭m7-5,9となります。
この和音を正確に決めるのは非常に難しいのですが、次のようにして順に進めていきましょう。
- 1パートずつ確認する
- 2パートずつ組み合わせてどんな音になるか試す
- 全体で合わせる
難しい和音ですが、その分複雑で深い響きを持っています。このような和音に作曲家のどのような思いが乗せられているか、考えてみても良いと思います。
【D】47小節~
ラストの和音を決めよう
【D】からは後奏に入ります。
54小節の合唱パートも忘れずに確認しておきましょう。合唱だけだとFmの暗い和音ですが、ピアノが入ると全体ではD♭M7の少し複雑な和音になります。
D♭M7の構成音
- 第7音「ド」…アルト
- 第5音「ラ♭」…ソプラノ
- 第3音「ファ」…男声
- 根音「レ♭」…ピアノ(左手)
アルトの歌う「ド」の第7音が、やや切ない雰囲気を醸し出す音です。
「レ♭」の音とぶつかっているので、釣られないようにするのに必死かもしれませんが、できればピアノパートの響きも感じながらそこに溶け込ませるようなイメージで歌えるとよいと思います。
強弱はmp → p → ppとなっています。mpは少し大きめに入ると、その後のデクレッシェンドで差をつけやすいと思います。柔らかいアクセントを伴っても良いと思います。
最終的にppまで落としますが、完全に消えてしまわないのもポイント。フェルマータはたっぷり長く、十分な余韻を作りましょう。
終わりに
最後までご覧いただきありがとうございました。参考になれば幸いです。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。
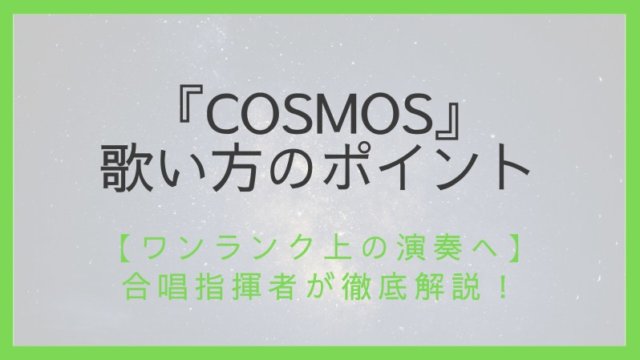
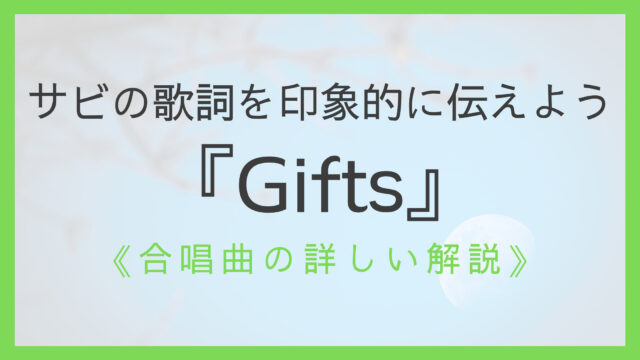
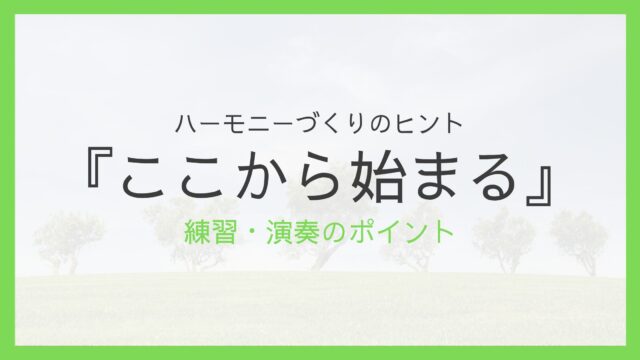
練習・演奏のポイント-68a719eb6cb59-320x180.jpg)