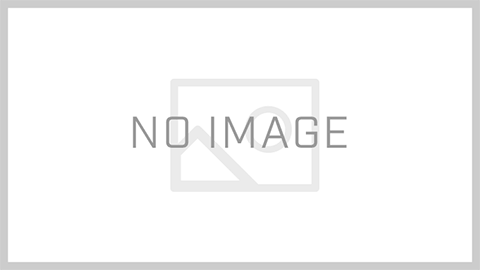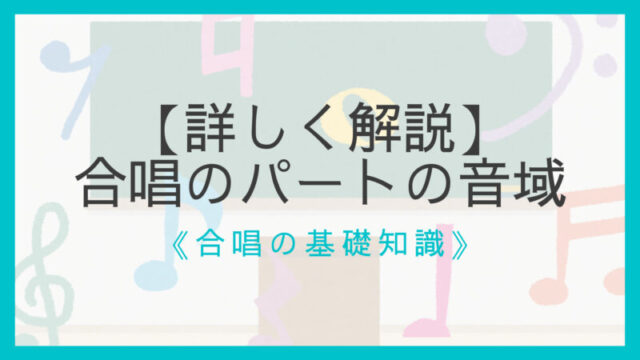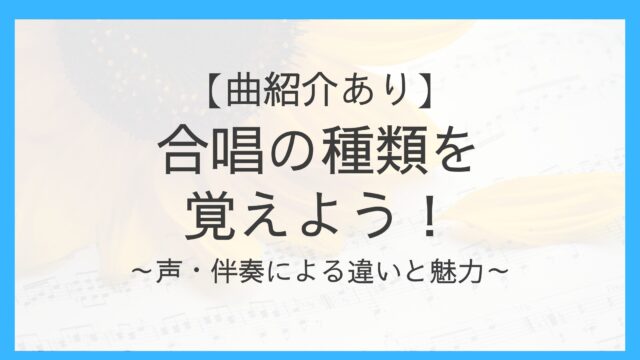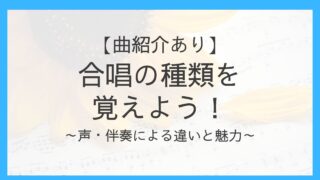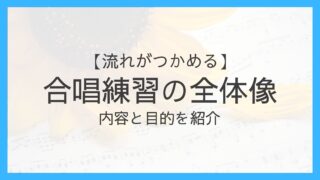【SATB】合唱パートの種類と呼び方|混四・混三・女声・男声での違い
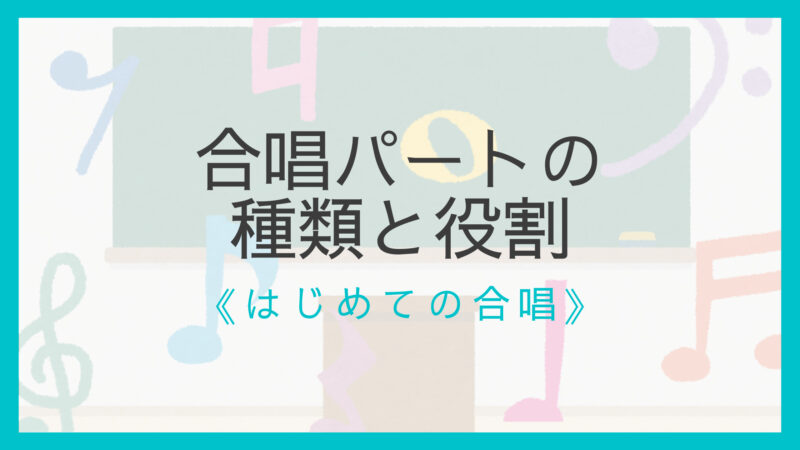
「合唱ってなんとなく知っているけれど、パートのことまではよく分からない…」
そんな方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そうした方に向けて、合唱の「パート」について分かりやすく解説します。
パートの名前や役割を知ると、実際に合唱曲を聴いたときに「今歌っているのはソプラノかな?」といったことを考えながら聴けるようになり、ぐっと楽しみが広がります。
また、もし自分が合唱部や合唱団に入ることになったら、「自分はどのパートを歌うのかな?」と想像するのもきっと楽しいはずです。
それでは早速、合唱のパートについて見ていきましょう。
もくじ
混声合唱の場合
合唱では全員が同じ音を歌うのではなく、何人かずつのグループに分かれて歌います。このグループのことをパートと呼びます。
異なるパートでは担当する音の音域、つまり歌う音の高さが違います。
それぞれのパートが異なる高さの音を歌うことで、合唱ならではの豊かなハーモニーが生まれるのです。
まずは男声・女声が混じって歌う、混声合唱でのパートを紹介します。
混声四部合唱の4パート【SATB】
混声四部合唱は、4つのパートからなる混声合唱の形態です。一般的に混声合唱と言えばこの形態を指します。
それぞれのパートの名称、楽譜上での表記、略称、主な役割を紹介します。
なお、パート全体のことを指す時、それぞれの略称を用いてSATB(エス・アー・テー・ベー)と呼ぶこともあります。この読み方は、英語表記「SATB」をドイツ語風に読んだもののようです。
ソプラノ/Soprano(略称:S, Sop.)
混声合唱においては、女声と男声のパートがあり、それぞれが2つずつに分かれることで合計4パートに分かれます。
ソプラノはそのうち、女声の高い方のパートで、最も高い音域を担当します。
メロディーを担当することが多く、演奏を聴いている際、最もよく聴こえるパートがこのソプラノです。
アルト/Alto(略称:A, Alt.)
アルトは女声のうち、低い方のパートです。
合唱の大きな魅力であるハーモニーを作る上で非常に重要な役割を担います。
テノール または テナー/Tenor(略称:T, Ten.)
テノールは男声のうち、高い方のパートです。テナーと呼ぶこともあります。
アルトのようにハーモニーを担当することもあれば、ソプラノのようにメロディーを担当することも多いパートです。
メロディーを歌っている時のテノールは結構目立つので、比較的聴き分けやすいパートだと思います。
バス または ベース/Bass(略称:B, Bas.)
バスは男声の低い方のパートです。最も低い音域を担当します。ベースと呼ぶこともあります。
どっしりとした声質で、ハーモニー全体の土台を支えるような、いわば縁の下の力持ち的なパートです。
混声三部合唱の3パート
先ほどは混声四部合唱でのパートを紹介しました。次に中学生で歌うレパートリーで多い、混声三部合唱についてです。
混声三部合唱では、ソプラノ、アルト、男声の3パートに分かれます。
ソプラノ、アルトは先ほど混声合唱の4パートで紹介したものと同様。
異なるのは男声で、四部合唱のときのように2つには分かれず、男声パート(略称:M)としての1つのパートを担当します。略称のMはMaleを意味します。
この男声パートは、変声期に差し掛かり、発声が不安定になりやすい中学生男子でも歌いやすいように、という配慮から考え出されたものです。そのためテナーほどの高音、バスほどの低音は要求されません。
その一方で、混声四部合唱におけるテナーとベースの両方の役割を併せ持つ側面があり、時にメロディーを歌い、時に和音を支えます。その意味で、上手に歌うのは意外と大変なパートです。
通常、混声三部合唱と言えば、上記のようにソプラノ・アルト・男声と、女声が2つに分かれることが大半ですが、中には女声・テノール・バスと、男声が2つに分かれる混声三部合唱の作品も存在します。
例えば『地球の詩』(作詞・作曲:三浦真理)や『OMNIBUS STAR 光年の旅』(作詞:西 世紀/作曲:鹿谷 美緒子)は、混声三部合唱の部分が女声一声+男声二声となります。(女声も分かれる部分があります。)
女声が少なく、男声の多いクラスではこのような曲を選ぶと良いでしょう。
混声二部合唱の2パート
混声三部合唱よりもさらにパート数が少ない、混声二部合唱という形態の曲もあります。
その場合、女声・男声に分かれます。
女声合唱の場合
ここまでは女声・男声が混じって歌う混声合唱のパートを紹介してきました。それに対し女声だけで歌う形態が女声合唱です。
なお、「女声」という言葉はあくまで音域とパートを表す言葉であり、実際の性別は問いません。そのため「女声合唱」に男性が参加することも可能で、実際にそのような団体もよく見かけます。
女声三部合唱の3パート
女声合唱で最もポピュラーな形態が、女声三部合唱です。次の3パートから成ります。
ソプラノ/Soprano(略称:S, Sop.)
女声合唱でのソプラノは、混声合唱のときと同じく最高音を歌うパートで、メロディーを担当することが多いです。
メゾソプラノ/Mezzo Soprano(略称:Mz, MzS)
メゾソプラノは女声合唱における真ん中の音域を担当するパートです。混声合唱におけるアルト的な役割と言ってよいでしょう。
略してメゾと呼ぶことが多いです。このメゾは、メゾフォルテ、メゾピアノなどと言う時と同じで、イタリア語で「中間の」という意味を表します。
アルト/Alto(略称:A. Alt.)
女声合唱においてはアルトが最低音を担います。そのため、混声合唱におけるバスと同様の役割です。
女声合唱に「男性」が参加する場合、このアルトパートに入ることが多いです。アルトには「女性」にとっては出しづらい、非常に低い音域を要求されることがあるのですが、「男性」から見るとちょうど歌いやすい音域だったりします。そのため、「男性」が入ると非常に心強い戦力となるのです。
女声四部合唱の4パート
女声合唱においても、4パートに分かれる女声四部合唱という形態の曲があります。
その場合、高い方からソプラノⅠ、ソプラノⅡ、アルトⅠ、アルトⅡのように表記されることが多いです。
男声合唱の場合
女声合唱に対し、次は男声合唱です。言わずもがな、男声だけで歌う合唱形態です。
男声合唱では次の4パートに分かれることが多いです。
混声合唱におけるテナー、バスがそれぞれ2つに分かれるというイメージになります。
なお、女声合唱で触れたのと同様、「女性」が参加することも可能です。
男声四部合唱の4パート
男声四部合唱と書きましたがあまり馴染みのある言い方ではなく、単に男声合唱と呼ぶことが多いです。
ほとんどの場合、次の4パートで歌います。
トップテナー/TenorⅠ(略称:TⅠ, Ten.Ⅰ)
男声合唱において最も高い音域を担当します。
メロディーを歌うことが多く、混声合唱におけるソプラノ的な役割に似ています。
単にトップと呼ぶこともあります。トップテノールという言い方もできなくはありませんが、あまり聞きません。
男声合唱に「女性」が参加する場合、ここに入ることが多いです。
男声合唱のトップテナーは、非常に高い音域を要求されることがあり、歌うのも非常に大変です。ですが、「女性」にとっては出しやすい普通の音域のため、非常に助かるという訳です。
セカンドテナー/TenorⅡ(略称:TⅡ, Ten.Ⅱ)
2番目に高い音域を担当し、ハーモニーを作るための音を担当することが多いです。
混声合唱におけるアルト的な役割と言って良いと思います。
単にセカンドと呼ぶこともあります。トップと同じくセカンドテノールという言い方はあまり聞きません。
バリトン/Baritone(略称:Bar.)
高い方から3番目、低い方から2番目の音域を担当するパートです。
混声合唱におけるテナーと同じく、時にハーモニーを、時にメロディーを担当しますが、テナーと比べて音域が低く、より重厚で男らしい印象の声質です。
バリと略して呼ぶこともあります。
バス または ベース(ローベース)/(略称:Bas.)
最も低い音域を担当するパートです。
混声合唱のバスと同様に、主に合唱全体を支える役割を持ちます。
バリトンが分かれていることを明示するためにローベースと呼ぶこともあり、その場合、ローベと略したりもします。
男声三部合唱の3パート
多くはありませんが、男声でも三部合唱の形態で歌う曲は存在します。
その場合、テノール(テナー)、バリトン、バス(ローベース)に分かれることがほとんどです。
同声合唱の場合
曲の中には同声合唱と分類されるものもあります。
同声合唱というのは、女声合唱と男声合唱をまとめた呼び方です。
曲の形態を表す言葉としては、小学生を対象にしたレパートリーにおいても使われます。これは、小学生ではまだ変声期が訪れていない人が多く、声区としては女声合唱となるためです。(この場合、児童合唱として分類されることもあります。)
同声合唱として書かれた作品は、女声合唱としての演奏が想定されている場合と、女声・男声のどちらで演奏することも可能な場合があります。
例えば、女声二部合唱として歌う場合はソプラノ・アルト、男声二部合唱として歌う場合はテノール・バスに分かれます。
まとめ:合唱パートの種類
合唱におけるパートの解説をしてきました。
混声合唱・女声合唱・男声合唱それぞれでパートの分け方が変わるので、自分の興味がある形態のものをまずは覚えると良いでしょう。
また、各パートの呼び方は所属する団体によって呼び方に違いがあると思いますので、先輩諸氏にも尋ねてみてください。