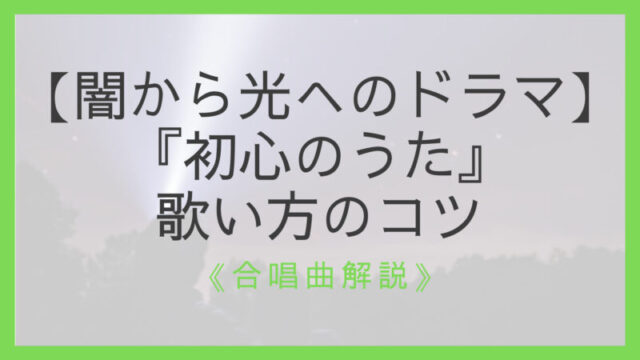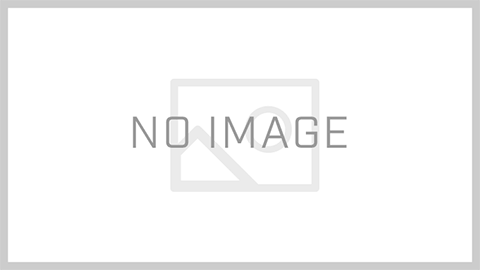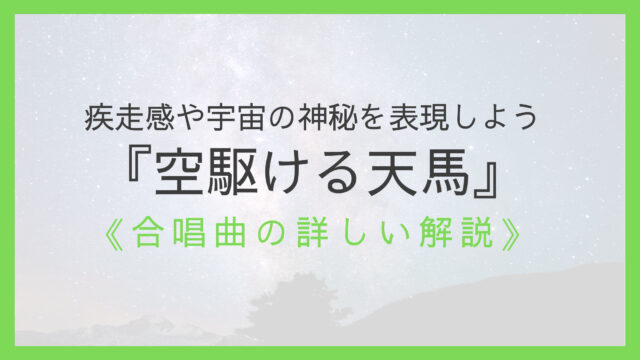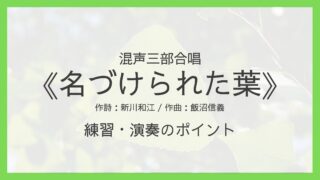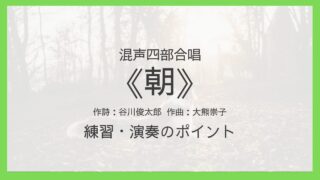【混声三部】《空は今》(作詞・作曲:山崎朋子)練習・演奏のポイント
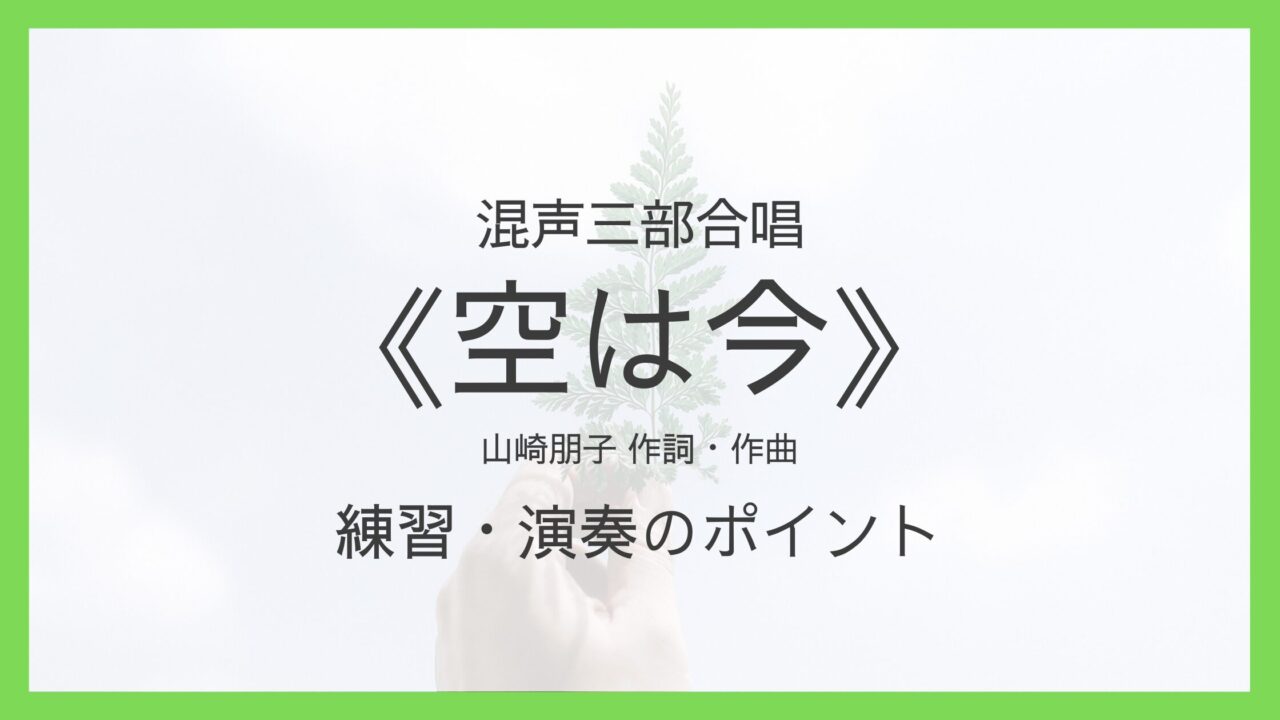
《空は今》はさわやかさと切なさ、そして力強さをあわせ持った素敵な作品です。
そんな《空は今》について、練習・演奏のポイントについてまとめました。
この記事を参考に、ぜひ練習・演奏に挑戦してみてください。
もくじ
練習のコツ・演奏のポイント
楽譜に記載されている練習番号(【A】【B】…)に沿って解説を進めていきます。内容を楽譜に書き込むのもおすすめです。
【A】…5小節~ “(そらはい)ま”
【A】は”何色ですか”、”青いですか”というように、相手に対して問いを投げかけるようなシーンです。問いかける相手は誰なのか、どんな人なのかを具体的にイメージして歌ってみましょう。
“そらはいま”の歌い出しは音を取るのが少し難しいです。直前のピアノパートのアルペジオ(和音をキラッと弾く動き)をよく感じて、そこからはじめの音が思い浮かべられるように練習しましょう。
強弱はmf(メゾフォルテ)となっています。意味としては「少し強く」ですが、乱暴にならないよう丁寧に。ここでは3パート(ソプラノ・アルト・男声)がすべて同じ音を歌うユニゾンになっているので、あまり頑張らずとも音量的には十分です。逆に音域が少し高めのところでは、音が大きくなりすぎないよう、少し抑えめを意識しても良いと思います。
9小節には<(クレッシェンド/だんだん大きく)があります。ここでは歌うときの息の流れを、”あおいですか”のフレーズに向かって持っていきましょう。先ほどmfは大きくなりすぎないように少し抑えめにと書きましたが、ここでは自然に盛り上がっても構いません。魅力的なメロディーですので、のびのびと、音の広がりを感じて歌ってください。”あ”→”お”への跳躍(音が飛ぶこと)を滑らかに、かつ音を引きずらないように歌うのが最大のポイント。難しいフレーズですが、挑戦しがいがあるフレーズです。
続いて”はてなくすきとおるように”では、”あおいですか”で大きくなった分を少し戻し、落ち着いて歌います。音符の上につけられている横棒のような記号はテヌート(音の長さを保って)です。ここでは、一つ一つの言葉を噛みしめるように大切に歌いましょう。このとき少しだけテンポがゆったりとしても良いでしょう。
12小節のロングトーン(伸ばす音)では>(デクレッシェンド/だんだん弱く)して、主役をピアノパートに受け渡します。
13小節からは間奏に入りますが、リズムが細かくなり音楽に動きが出てきます。それに応じて少しテンポを前向きに速めても良いでしょう。
【B】…17小節~ “かぜのなかで”(”あけないよる”)
【A】の最後で少し触れましたが、ピアノパートのリズムが細かくなっていますので、合唱パートの人もこれを感じながらテンポに乗りましょう。
音量がmp(メゾピアノ/少し弱く)になっているのも【A】との違いです。ここは歌い上げるというよりは、言葉を語りかけるように歌い、聴いている人にしっかり伝えることを意識しましょう。
合唱では言葉の最初の文字を少しはっきり目に発音すると、聴いている人に歌詞が伝わりやすくなります。例を挙げてみます。
- “かぜのなかで”
- “ときのながれ”
- “じだいが”
- “ながれてゆく”
ただし、言葉を強調することでメロディーの流れを失ってしまうのもよくありません。
難しいですが、それぞれを両立できるよう練習してみてください。
【C】…25小節~ “(あ)たらしい”
【C】では、24小節の終わりにcresc.(クレッシェンド/だんだん強く)が書かれています。
クレッシェンドは、例えば9小節に出てきたように、<の松葉の記号で書かれることもあります。それに対してcresc.と文字で書かれている場合は、<もよりもじわじわと長い期間をかけて盛り上げていって欲しい、という作曲者の意図が含まれていることが多いです。ここでのクレッシェンドは最終的に【D】のf(フォルテ/強く)まで向かいます。
クレッシェンドする際には、「どこに向かうか」「どれくらい大きくするか」「どれくらいのペースで大きくするか」ということをメンバー全員で共有することが大切です。ただ闇雲に大きくしていけばよい、というわけではないのですね。先ほど触れたように、それを考えるヒントは楽譜に必ず書かれていますので、よく読み取ってみてください。
26~28小節にかけての”いのちをつないでいくこと(みらいとよべるひはくるよ)”のフレーズは、アルトと男声がメロディーを担当します。この2パートは主役の意識を持ってしっかり歌うこと、お互いの声をよく聴きあって音を合わせることを気をつけましょう。ソプラノはアルトよりも高い音を歌いますが、メロディーにハーモニーを添える役割ですので、少し抑えめに、メロディーに柔らかく寄り添うようなイメージで歌いましょう。
28小節の4拍目には四分休符がありますが、これが実は重要です。ここで3パートがそろってブレス(息継ぎ)を取ることで、音楽が引き締まると同時に【D】からのfを歌うだけのエネルギーとなります。
【D】…29小節~ “ここで”
ここからはfになります。ポップスで言えばサビの場面です。
最初はソプラノ&アルトの”ここで”が音楽を引っ張ります。四分音符が主体となるメロディーはこの曲では初登場。たっぷりと歌って、”いきている”、”いきていく”という歌詞の力強さを表現しましょう。なお、主旋律はソプラノで、矢印によってそれが示されています。
次に、遅れて男声が”ここで”と入ります。ずれて入ったことが聴いている人に伝わるよう、少ししっかり目に入りましょう。
そして30小節、あるいは32小節で3パートが合流し、タテがそろいます。タテがそろうというのは、リズムと歌詩のタイミングが一致すること。このように、「ずれて入る→タテがそろう」というパターンは合唱曲ではよくあります。そろったところで一体感が出せるように、「ここからそろうぞ」と見通しておくことが大切です。
35小節の“てらして”はハーモニーをよく感じてみましょう。《空は今》はユニゾンが多い曲なのですが、ここでは3パートが異なる音を歌ってハモっています。ハーモニーを確認するには、ピアノパートはお休みしてもらい、合唱だけで(アカペラで)歌ってみるのが効果的です。
36~37小節の”いま”にはテヌートが書かれています。さらっと簡単に歌ってしまわずに、言葉を大切にして、「まさに今!」というようなソリッドな(確固とした)イメージを持って歌いましょう。
2カッコに入る38小節では、伸ばす音に注意してください。1カッコよりも1拍分長くなっています。また、伸ばしている間に弱くならないように、次の場面へ繋がるような方向感を持って歌いましょう。
【E】…39小節~ “ここで”
【D】と同じくサビ的な場面です。特に何も書かれていませんが、あらためてfを作り直すような気持ちで。むしろアンコール的にプラスアルファ盛り上げるようなイメージで歌っても良いでしょう。
【F】…47小節~ “(そらはい)ま”
冒頭【A】のフレーズが再現される場面ですが、【F】ではピアノパートの伴奏形が異なります。伴奏形が変わると音楽の雰囲気がガラッと変わってきますので、それを感じながら歌いましょう。
【F】の主役のメロディーは男声ですが、女声とのメロディーの掛け合い・絡み合いも大切です。お互いが「どんなメロディーを歌っているのかな?」ということを聴き合いながら歌うと、複数のメロディーが整理され、立体的な音楽になっていきます。
50~51小節にかけての”そらはいま あおいですか”というフレーズでは、主旋律が男声→ソプラノと受け渡されます。ここでも【D】のように矢印によってメロディーを担当するパートの入れ替わりが示されています。メロディーが自然につながって聴こえるよう意識しましょう。
52~53小節にかけてはrit.(リタルダンド/だんだん遅く)が書かれています。少しずつテンポを緩めていき、曲の終わりの雰囲気を醸し出すようなイメージで。
54小節のロングトーンは全員が同じファの音を歌いますので、ピタッと音をそろえることが大切。また、>(デクレッシェンド/だんだん弱く)で音楽を収めていくことを意識しましょう。
54小節ではテンポ(四分音符=88)があらためて指定されています。直前のrit.で落としたテンポをもとに戻して、という意味では通常a tempo(ア テンポ/もとの速さで)が使われます。あえてこのように書かれているのは、さかのぼって13小節や【B】でCon moto(コン モート/動きを持って)的にテンポを速めた場合、ここで再度テンポを落ち着けて、という意図があるのではないかと思います。つまり、TempoⅠ(テンポ プリモ)的な使い方がされているということです。
終わりに
最後までご覧いただきありがとうございました!
この記事を参考に、良い演奏ができることを願っております。
なにか質問がありましたら、お問い合わせからお気軽にご連絡いただければと思います。