【初心者向け】合唱ってどこで聴ける?|合唱祭・コンサート・コンクール

合唱に少し興味を持った方の中には、
「もっといろいろ聴いてみたい!」
「やっぱり生の演奏を体験してみたい!」
と思う方も多いのではないでしょうか。
では実際に、合唱はどんな場所で聴けるのでしょうか。
この記事では、初心者の方でも足を運びやすい演奏会から、コアな合唱ファンが注目する大会まで、代表的な場をわかりやすく紹介します。
合唱には、生の音でこそ伝わる魅力があります。興味を持たれた方は、ぜひ一度、会場でその響きを感じてみてください。
もくじ
演奏会・コンサート
合唱を生で聴ける場として、まず思い浮かぶのが「演奏会」や「コンサート」です。
大きなホールで行われる本格的な公演から、地域の公民館など身近な会場での催しまで、形はさまざまです。
プロやハイアマチュアの公演は有料のこともありますが、入場無料で楽しめる演奏会も多くあります。
ここでは、代表的な2つの形をご紹介します。
演奏会・コンサート(単独)
ひとつの団体が単独で主催する演奏会です。
「〇〇定期演奏会」「△△コンサート」などの名称で開かれ、学校の合唱部や大学合唱団、社会人合唱団、プロ合唱団など、幅広い団体が開催しています。
全国には数えきれないほどの合唱団があり、毎週末のようにどこかでコンサートが開かれています。
入場料は、アマチュア団体で無料〜3,000円程度、プロ合唱団では4,000〜6,000円程度が目安です。
時には海外の合唱団を招聘してのコンサートが開催されることもあります。チケットの競争率は高くなりますが、海外の合唱を聴くことができる貴重な機会となっています。
合同演奏会・ジョイントコンサート
2つ以上の団体が合同で行う演奏会です。
ジョイントコンサートと呼ばれることもあり、各団体がそれぞれのステージを担当したあと、最後に合同ステージを披露する構成が一般的です。
プログラム例:
- 1st stage … 〇〇合唱団
- 2nd stage … △△コーラスクラブ
- 3rd stage … □□クワイア
- 4th stage … 三団体合同演奏
単独ステージではそれぞれの団体の演奏を聴き比べできること、合同ステージでは大編成ならではのスケール感や、演奏機会の少ないレアなレパートリーを楽しめることなどが魅力です。
また、出演する側にとっても、集客や運営、チケット販売などの負担を分担できるというメリットがあります。
合唱祭・コーラスフェスティバル
「いきなりコンサートに足を運ぶのはハードルが高い…」と思われる方も多いのではないでしょうか。そんな方におすすめなのが合唱祭やコーラスフェスティバルです。
合唱祭やコーラスフェスティバルは、各地域で開かれる大規模な合唱イベントです。
中学校・高校の合唱部、大学合唱団、社会人の合唱団、合同ステージ、さらにプロやセミプロまで幅広い団体が代わる代わる出演し、7~8分程度の持ち時間の中でそれぞれのレパートリーを披露します。
一日いるだけで、さまざまな団体や曲を一度に聴けるのが合唱祭の魅力です。東京都合唱祭は特に規模が大きいことで有名で、例年300団体超が出演します。ちなみに2025年は6日間にわたって開催されました。
入場は無料〜1,000円程度。入場退場のタイミングも自由なことが多いので、都合のつく時間だけ聴いてみるのも良いですし、もし知り合いが出場するということがあれば、その団体が出場する時間を狙って聴きに行くのもおすすめ。あわせて前後の団体と聴き比べるだけでもずいぶん多くの演奏に触れることができます。
単独公演よりも肩ひじ張らずに楽しめるので、「まずは雰囲気を味わいたい」「いろいろ聴き比べたい」という方におすすめです。
まずは「〇〇県 合唱祭」で検索して、日程や会場を調べるところから始めてはいかがでしょうか。
コンクール・コンテスト
コンクールやコンテストは、合唱団が演奏の完成度や表現力を競い合う舞台です。通常の公演とはひと味違う、緊張感に満ちたハイレベルな演奏を味わうことができます。
審査は、指揮者や作曲家、声楽家、音楽評論家など、5〜9名ほどの専門家によって行われ、最後に各賞が発表されます。
演奏後に講評や順位が公表される場合もあり、自分の感想と審査結果を照らし合わせることで、「良い演奏とは何か」を考えるきっかけにもなります。さらに、合唱の上達に欠かせない「聴く力」を磨く場にもなるでしょう。
コンクールにはいくつか種類があります。次に、代表的なものをいくつか紹介します。
NHK全国学校音楽コンクール(通称:Nコン)
NHK全国学校音楽コンクール(Nコン)は、小・中・高校の児童生徒を対象にした全国規模の合唱コンクールです。
テレビ放送でもおなじみなので、ご存じの方も多いでしょう。「合唱コンクールといえばNコン」という方も少なくありません。
大会は都道府県大会から始まり、勝ち抜いた団体がブロックコンクール(例:関東甲信越ブロック)に進出します。さらにその代表が、渋谷・NHKホールで開催される全国大会へと進みます。全国大会で最優秀に選ばれた学校には、金賞が授与されます。
ステージでは、毎年決められる課題曲と、各校が自由に選ぶ自由曲を演奏します。課題曲が毎年新しく作曲されるのも、Nコンならではの特徴です。
近年の課題曲では、詩人や作家、脚本家(穂村弘、朝井リョウ、辻村深月など)が作詞を担当したり、人気アーティスト(いきものがかり、SEKAI NO OWARI、緑黄色社会など)の楽曲が採用されたりと、幅広い世代が合唱に親しめる工夫がされています。
これまでに生まれた《虹》《手紙》《Yell》《言葉にすれば》などの課題曲は、コンクールを超えて多くの学校で歌い継がれ、今も人気のレパートリーとして親しまれています。
全日本合唱コンクール
日本全国の合唱団が参加する、伝統あるコンクールのひとつが全日本合唱コンクールです。「NHK全国学校音楽コンクール(Nコン)」に並ぶ、国内屈指の舞台として知られています。
主催は全日本合唱連盟と朝日新聞社。1948年に第1回大会が開催されて以来、約80年の歴史を誇ります。
Nコンとの違いは、小・中・高校生だけでなく、大学生や社会人を含むあらゆる合唱団が出場できる点です。
そのため部門も多彩で、小学生・中学生・高校生部門のほか、28歳以下の若手による大学ユースの部、少人数の室内合唱の部、大人数による混声合唱の部、そして同声合唱(女声・男声)の部があります。
小学生・中学生部門では自由曲のみを演奏し、課題曲はありません。高校以上の部門では課題曲と自由曲の両方を演奏します。
課題曲は、毎年編纂される合唱名曲シリーズから選ばれます。シリーズには混声・女声・男声それぞれ4曲ずつ、計12曲が収録されており、16〜17世紀の古典から現代曲まで幅広い時代の作品が含まれています。どの曲を課題曲として選ぶかも、聴きどころのひとつです。
出場団体には金賞・銀賞・銅賞のいずれか(または無賞)が与えられ、金賞団体の中から上位大会への代表が選ばれます。
都道府県大会を勝ち抜いた団体は支部大会へ、支部大会を勝ち抜いた団体は全国大会へと進みます。
全国大会の出場枠はごく限られているため、金賞を受賞しても次の大会に進めない場合があります。このような金賞を、俗に「ダメ金」と呼ぶこともあります。
全国大会では、各支部の代表が一堂に会し、日本最高峰の演奏が繰り広げられます。会場は毎年全国各地を持ち回りで開催され、音楽を競う場であると同時に、合唱団同士が交流する場にもなっています。
開催都市には合唱人が全国から押し寄せ、会場周辺のホテルが満室になるのも、今や風物詩です。
その他のコンクール・コンテスト
ここでは、その他の代表的なコンクール・コンテストをいくつかご紹介します。
声楽アンサンブルコンテスト全国大会
2〜16名の少人数で表現力を競う、ハイレベルな大会です。
福島県福島市のふくしん夢の音楽堂で開催されます。
アンサンブルとしての完成度、響きの純度が問われる大会として知られています。
宝塚国際室内合唱コンクール
各部門では、8〜24人の少人数による合唱を競います。
その名の通り国際コンクールで、海外からの参加団体も多く、世界的にも高い評価を得ています。
少人数でも緻密な音楽性を追求する「室内合唱」の名門大会です。
東京国際合唱コンクール(TICC)
2018年に創設された、比較的新しい合唱コンクールです。
同声・混声・室内合唱など多彩な部門構成と、点数制による審査が特徴です。
審査は、音程・リズム感・演奏解釈・発声および声のブレンドの4要素から成るテクニカル・エレメンツと、表現力を点数化したアーティスティック・インプレッションの合計点で評価されます。
宝塚国際室内合唱コンクールと同様に国際大会で、審査員も世界各地から招かれます。
非常にハイレベルな大会となっています。
まとめ
合唱を聴ける場は、ここで紹介したもの以外にもたくさんあります。
街頭でのコンサートやチャリティーイベントなど、思ったよりも合唱を聴くチャンスは多いものです。
もちろん、YouTubeなどで気軽に演奏を聴くこともできますが、やはり音楽の魅力は生の演奏を聴いてこそ味わえるもの。
まずは気軽に聴きに行ける合唱祭などで、ぜひ“生の音”に触れてみてください。
さらに興味が深まってきたら、コンサートやコンクールにも足を運んでみましょう。
素敵なレパートリーやハイレベルな演奏に出会える、感動的な体験になるはずです。
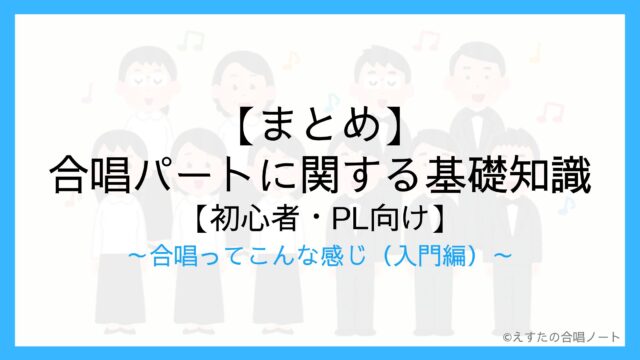
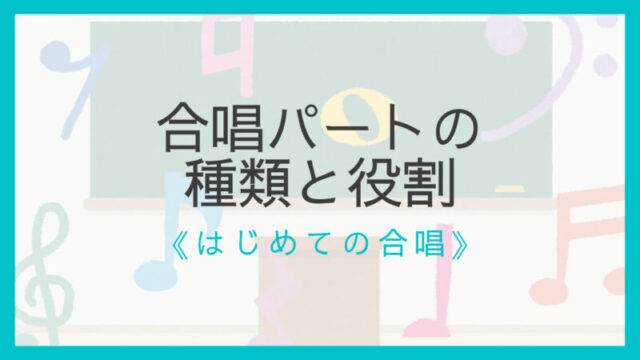
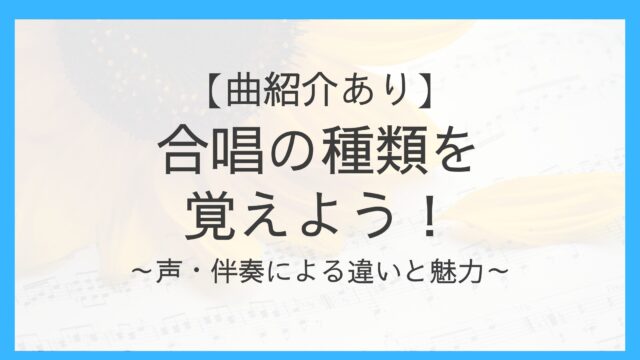
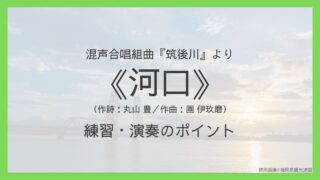
》練習・演奏のポイント-320x180.jpg)
