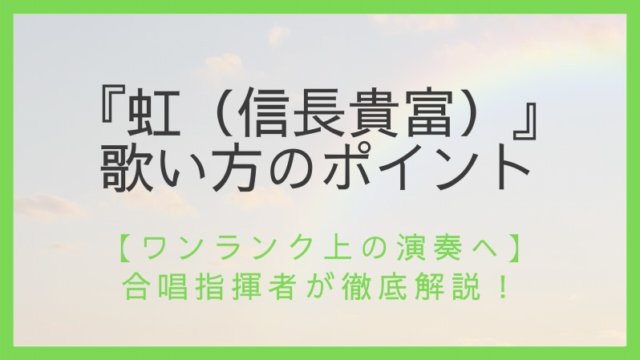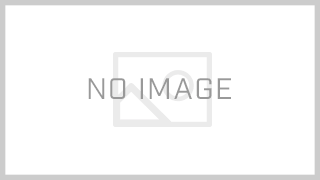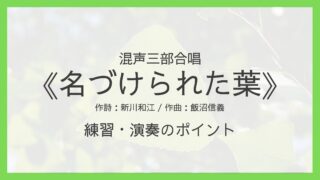【混声三部】《懐かしい未来》練習・演奏のポイント
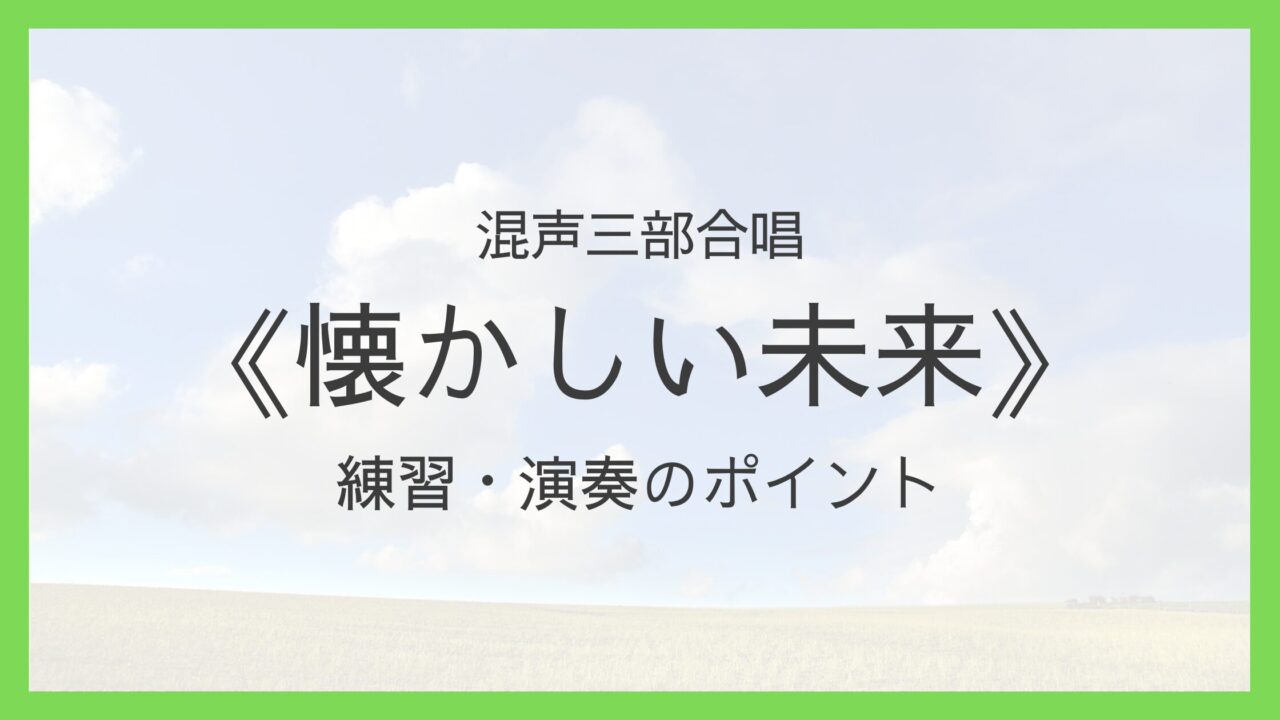
《懐かしい未来》は、2022年1月1日にリリースされた、上白石萌音さんの楽曲。第100回全国高校サッカー選手権大会の応援歌です。
この記事ではそんな《懐かしい未来》(合唱編曲:田中達也、混声三部合唱)について、練習・演奏でのポイントをまとめました。
参考になれば幸いです。
もくじ
練習・演奏のポイント
ここからは楽譜に書かれている練習番号(【A】【B】…)に沿って進めていきます。
各場面ごとに繰り返し磨き上げていけば、よりクオリティの高い演奏ができるようになっていくと思います!
【A】…”なつかしいみらい”
【A】の部分は何より歌詞をしっかり伝えることがポイントになります。
特に歌い出しの”なつかしいみらい”は曲のタイトルでもあり、かつ印象的な一節なので聴いている人にクリアに届けたいところです。
練習で確認しておきたいのは各フレーズの最初の1文字目。例えば”なつかしいみらい”であれば”な”、”ここはいつか”であれば”こ”です。
合唱で歌詞を伝えたいと思ったとき、一番重要になるのがこの1文字目です。1文字目が伝わると、全体で何を言っているのかが伝わりやすくなります。
ほかの文字ももちろん必要なのですが、歌詞を伝えようとするあまり、すべての文字をしっかり歌おうとすると、メロディーの流れや表情を邪魔してしまい、逆効果になってしまうことがあるので注意が必要です。
《懐かしい未来》ではこの1文字目の音が非常に低い音程から始まることが多くなっています。低い音を届かせるには、まずは正確な音で歌うこと。音がしっかりとそろうと低くてもきちんと聞こえます。しっかり狙って、歌うべき音をイメージしてから歌い出しましょう。
ソプラノの人にとっては、低すぎて歌いにくい人もいると思いますが、【A】の部分に関してはアルトもいっしょに同じ音を歌ってくれています。このように、この田中達也さんによる編曲では、歌い出しの低い音が無理なく届くよう、アルトや男声に協力してもらえるように工夫されています。
他の例を挙げると、8小節の”あるいたみち”の”あ”は非常に低い音(ファ)となっていますが、ソプラノ・アルトの2パートで歌うようになっています。ここまで低いとアルトの人にとっても出しにくいと思いますが、女声全員で協力しあって一つの音を作り、音を届けましょう。
ただし、無理に出そうとしたり、力んでしまうのは音がばらついてしまうおそれが高まるので禁物です。音がばらつくと、響きが濁り、逆に伝わらなくなってしまいます。
【B】…”さがしていた”
【B】からピアノ伴奏の音型、和音がガラリと変わることを感じて歌いましょう。
次のように変わっています。
- 【A】流れるような音型→【B】力強く刻むような音型
- 【A】明るい和音中心→【B】暗い和音中心
このような変化が、歌詞とはどのように対応しているか考えたり、メンバーどうして共有し合うと、とても良いと思います。
次に、ここからは2つ以上のメロディーがずれて歌われる掛け合いの場面になっていることを意識しましょう。
例えば女声が”さがしていた”を歌うと、その後で男声が”さがしていた”と遅れて歌い始める、というふうになっています。同様に17小節からはソプラノ+男声が”きっとおわりじゃない”と歌い、アルトが遅れて”きっとおわりじゃない”と入ります。
このような場面では、それぞれのメロディーのタイミングがうまく噛み合っていることが大切です。
後から入るパートは、先に入ったパートのメロディーをよく聴いて、タイミングしっかり取りましょう。
18小節から【C】の手前、”まだみていたい”に向かってはcresc.(クレッシェンド/だんだん大きく)が書かれています。ここでじわじわと盛り上げていくことでサビの場面に向かいましょう。
【C】…”まだみていたい”
【C】からはサビの場面になります。
ここではまず「タテ」を意識しましょう。
「タテ」というのは、各パートが歌うタイミングのこと。【C】のような場面(21~23小節)は、ソプラノ、アルト、男声が同じタイミングで同じリズム・歌詞を歌うので、「タテ」がそろっているということができます。
先ほど【B】は掛け合いになっていると説明しましたが、【C】からはずれていた3パートが一体となって「タテ」がそろいます。
「タテ」がそろうと声が集まることで音量が増し、またハーモニーが生まれます。こうしてサビらしい迫力が出てきます。「タテ」がそろうことを意識することで一体感が出、f(フォルテ)がいっそう効果的なものになります。
25小節にはpiu fが書かれています。piu(ピウ)はfを強調するための記号。なのでここでは「フォルテよりいっそう大きく!」というような意味。「もういっちょ盛り上げて!」というように捉えても良いでしょう。
26小節の”いま”は大事な言葉です。16音符が短いため、サラッと歌ってしまいがちですが、そうすると言葉の持つメッセージ性が薄れてしまうので、少し強調すると良いでしょう。
28小節の”ゆうえんのかぜの”は決めどころと捉えてカッコよく。あわせて直前の4分休符は大事です。ここでブレイク(音のない瞬間)をカチッと決めると、聴いている人をハッと惹きつけることができると思います。
【D】…”ように”
ピアノの間奏がメインの場面です。
合唱は「音をどこまで伸ばすのか」が重要。アルト・男声は29小節4拍目まで、つまり次の小節に入る直前に切ります。
ソプラノは30小節3拍目まで伸ばすので、アルト・男声が消えた後も、ロングトーンが残っている必要があります。これが余韻を生むような仕掛けになっているのですね。
【E】…”かじかむおもい”
ここから2コーラス目になります。【A】と対応する場面ですので、注意点も同様です。
【E】では男声もいっしょにメロディーを歌うこと、ピアノ伴奏の形が変わっていることが【A】と異なりますので、それを感じながら歌えるとさらに良いと思います。
37小節”きごうかできない”からはアルトがメロディーです。これまでは3パートでメロディーを歌っていたのに対し、ここからは1パートでメロディーとしての存在感を出す必要があるので、しっかりめに歌いましょう。
ここでは男声はハモリのパートになります。音が比較的高いため声が大きく出やすいのですが、乱暴に歌ってしまうと主役であるアルトをかき消してしまいます。アルトのメロディーをよく聴いて、寄り添うように音量バランスに気を使って歌いたいフレーズです。
【F】…”こらえていた”
【B】に対応する場面ですので、基本的な注意点は同じです。
歌詞が変わりますので、どの言葉が大切か、どのように伝えたいかを考えて、歌に反映させましょう。
【G】…”あたらしいせかい”
同様に、【C】と対応するサビの場面です。
”えいえんはいっしゅんのストーリー”は早口言葉のようになりますので、しっかり喋って伝えられるように練習しておきましょう。
また【C】と違い、男声がいないので、頼りなくならないように堂々と歌いきってください。
【H】…”ラララ”
57~58小節は男声が音楽を引っ張ります。
marcato(マルカート)は一つ一つの音を固いタッチでしっかりと歌うようにという記号です。(ゴツゴツしたイメージ)
ピアノ伴奏の音型の変化(リズムとアクセント)も感じながら歌いましょう。
【I】…”なつかしいみらい”
【I】はピアノパートの音の数が最小限となり、アカペラに近い響きになります。
合唱のハーモニーが音楽の土台になりますので、各パートよく練習して、自信を持って正確に歌えるようにしておきたい場面です。ハーモニーを担当するアルト・男声だけを取り出して練習するのもかなり有効です。
また、ソプラノのメロディーとピアノパートの右手のキラキラしたフレーズの掛け合いも大切です。ソプラノ→ピアノ→ソプラノ→…と交互に音が動くことが分かると思います。
70小節からは【C】で解説した「タテのそろい」を意識しましょう。
【J】…”まだみていたい”
サビの繰り返しで、曲の終わりに向かうクライマックスシーンでもあります。
77~78小節のロングトーンは、弱くならないようにしっかり伸ばし切りましょう。アルト・男声は途中で”ah”になって音も変わります。この動きはアピールポイントです。
81~82小節のロングトーンもfをキープして、減衰しないように歌い切りましょう。
男声は途中で音が変わります。これによって和音も変化するので、フォルテで歌いつつも、お互いの声を聴き合いながらハーモニーも意識しておきましょう。
【K】…”なつかしいみらいへ”
ff(フォルティッシモ/fより強く)が登場し、音量的にもピークを迎えます。ここでさらに盛り上げられるよう、休符の間に準備をしておきましょう。
89小節からはdim.(ディミヌエンド/だんだん小さく)があり、次第にフェードアウトしていきます。
”oh”ははじめ2回はユニゾンで全員同じ音を歌いますが、3回目だけはハモりになっているので意識しておきましょう。ピアノ伴奏を抜きでアカペラで練習してみても良いと思います。
終わりに
最後までご覧いただきありがとうございました!
何か質問がありましたら、お問い合わせからお気軽にご連絡いただければと思います。
良い演奏ができますことを願っております!
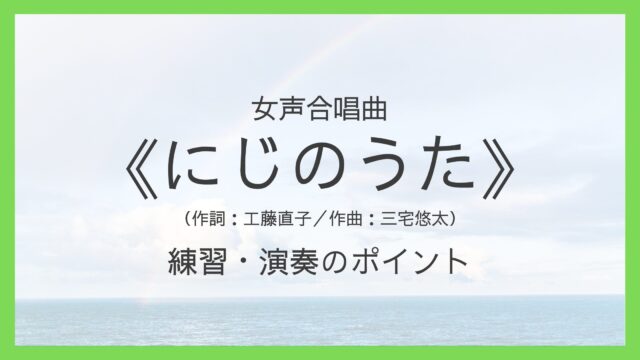
練習・演奏のポイント-68a719eb6cb59-640x360.jpg)