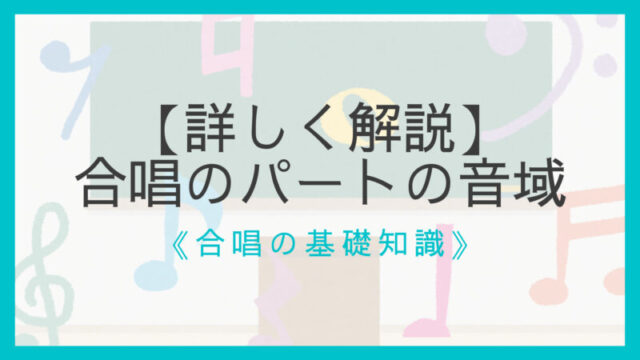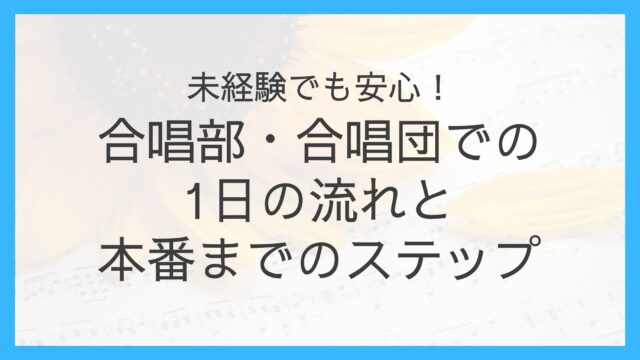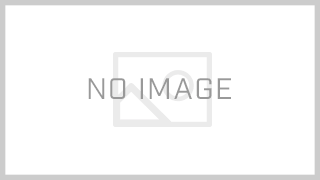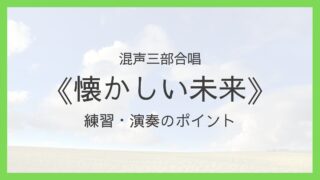【奥深い】合唱ってどんな曲がある? 6つのジャンルに分けて紹介【解説あり】
「合唱ってどんな曲があるの?」
この記事では、そんな疑問にお答えします。
合唱曲をまったく聴いたことがない、という方は少ないでしょう。
学校での入学式や卒業式、あるいは合唱コンクールで合唱を経験したことのある方も多いと思います。また、「合唱といえば年末の第九」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
ですが、実は合唱の世界には、それだけでなくもっともっとたくさんの曲があるんです。
この記事では、そんな合唱曲を次の6つのジャンルに分けてご紹介してみました。
それぞれに簡単な解説と、詳しく紹介した記事へのリンクも載せていますので、気になる曲から聴いてみてください。
初心者の方に聴いてもらうには、少々難しい曲もありますが、「どんな曲が刺さるか分からない」という意気込みでリストを作りました。
結構たくさんの曲を取り上げたつもりですが、それでも星の数ほどある合唱曲の中ではほんの一部。
この記事をきっかけに、お気に入りの一曲を見つけてみていただければ幸いです。
もくじ
- 1. 学校で歌われる合唱曲
- 2. ポップスをアレンジした合唱曲
- 3. 唱歌・民謡などをアレンジした合唱曲
- 4. 邦人作曲家による合唱曲
- 5. いろいろな言語の合唱曲
- 《MI・YO・TA》(作曲:武満 徹/日本語)
- 《My love dwelt in a Northern land》(作曲:エルガー/英語)
- 《Zigeunerleben》(作曲:シューマン/ドイツ語)
- 《Trois beaux oiseaux du Paradis》(作曲:ラヴェル/フランス語)
- 《Libiamo, ne’ lieti calici》(作曲:ヴェルディ/イタリア語)
- 《Esti dal(夕べの歌)》(作曲:コダーイ/マジャール(ハンガリー)語)
- 《AMETSETAN》(作曲:ブスト/バスク語)
- 《Bogoroditse Devo》(作曲:ラフマニノフ/ロシア語)
- 《Virta venhettä vie》(作曲:クーラ/フィンランド語)
- 《Pamugun》(作曲:フェリシアーノ/タガログ語)
- 《El guayaboso》(作曲:ロペス/スペイン語)
- 《Baba Yetu》(作曲:ティン/スワヒリ語)
- 《THE GROUND》(作曲:ヤイロ/ラテン語)
- 6. いろいろな時代の合唱曲
- 《Ubi Caritas Et Amor》(グレゴリオ聖歌/8世紀~9世紀頃)
- 《Messe de Nostre Dame: Kyrie》(マショー/1300年頃~1377年頃)
- 《Ave Maria》(ジョスカン・デ・プレ/1450年頃~1521年)
- 《Kyrie from Missa Papae Marcelli》(パレストリーナ/1525年頃~1594年)
- 《Jesus bleibet meine Freude》(バッハ/1685年~1750年)
- 《Messiah》より《Hallelujah Chorus》(作曲:ヘンデル/1685年~1759年)
- 《Dies irae》(モーツァルト/1756年~1791年)
- 《歓喜の歌》(ベートーヴェン/1770年~1827年)
- 《Richte mich, Gott》(メンデルスゾーン/1809年~1847年)
- 《Wie lieblich sind deine Wohnungen》(ブラームス/1833年~1897年)
- 《O Fortuna》(作曲:オルフ/1895年~1982年)
- 《Salve Regina》(プーランク/1899年~1963年)
- 《Agnus Dei》(バーバー/1910年~1981年)
- 《Cantate Domino》(ラター/1945年~)
- 《Lux Aurumque》(ウィテカー/1970年~)
- 《Deus Caritas Est》(作曲:佐藤 賢太郎(Ken-P)/1981年~)
- まとめ
1. 学校で歌われる合唱曲
まず最初に、一番親しみのあるジャンルとして、中学校や高校の音楽の授業、入学式や卒業式、校内の合唱コンクールなどで歌われることが多い合唱曲を紹介します。
「あまり真面目に歌ったことがない」という方も、中にはいらっしゃるかもしれませんが、実は感動的な作品の宝庫。
まずは1曲、聴いてみてください。
《大切なもの》(作曲:山崎 朋子)
卒業式などでもよく歌われる定番の曲です。
優しいメロディーとハーモニーが心にしみます。
《Let’s Search For Tomorrow》(作曲:大澤 徹訓)
中学生に大人気の作品。
輝かしいピアノの前奏と、繰り返し歌われる”Let’s Search For Tomorrow”のサビのメロディーが印象に残ります。
《マイバラード》(作曲:松井 孝夫)
こちらも中学生に人気の作品。
中盤の”心燃える歌が”のメロディーがとても熱く、かっこいい作品です。
《時の旅人》(作曲:橋本 祥路)
これまで紹介してきた曲と比べるとやや難しくなります。
ストーリー性のある歌詞が、転調という技法を用いた場面の転換で、うまく表現されています。
《怪獣のバラード》(作曲:東海林 修)
冒頭のピアノ伴奏からノリノリで、聴いても楽しい、歌ってもっと楽しい曲。
ですが、実は明るいだけでなく、”海が見たい”という部分では暗い和音も用いられているなど、歌詞に寄り添った音楽になっています。
《この地球のどこかで》(作曲:若松 歓)
私がとても好きな作曲家である若松歓さんの作品です。
語りかけるような歌い出しから、壮大な感じのするクライマックスまでのドラマ性が魅力的な作品だと思います。
《COSMOS》(作曲:ミマス)
中学生に最も人気のある合唱作品と言っても過言ではないほどの曲。
美しい歌詞とそれを表現するメロディー、繰り返されるごとに盛り上がっていくサビなど、魅力がたくさんつまっています。
《旅立ちの日に》(作曲:坂本 浩美/編曲:松井 孝夫)
卒業式の定番。歌ったことがある人も多いはずです。
ゆったりとした前半部分と、躍動感のある後半の対比が印象的な曲です。
2. ポップスをアレンジした合唱曲
ポップスを合唱用にアレンジ(編曲)した作品です。
ノリがよくキャッチーなメロディーを備えている上、もともとが知っている曲であることも多く、馴染みやすい作品群です。
原曲と比べてどのようなアレンジがされているのかも聴きどころです。
《虹》(作曲:森山 直太朗・御徒町 凧/編曲:信長 貴富)
ポップス系の合唱曲の中でもとりわけ人気の高い作品です。
美しいピアノ伴奏と、合唱らしいハーモニーのアレンジが巧みです。
終盤にあるソロパートも聴きどころです。
《手紙~拝啓 十五の君へ~》(作曲:アンジェラ・アキ/編曲:鷹羽 弘晃)
十五歳の自分と、大人になった未来の自分との間で交わされる手紙、という設定の歌詞になっています。
原曲の弾き語りっぽい感じがよく再現されているアレンジです。
《Yell》(作曲:水野 良樹(いきものがかり)/編曲:鷹羽 弘晃)
ポップス系ではやや珍しい短調(=暗い)の曲で、歌詞のメッセージ性が力強く表現されています。
合唱の醍醐味である「ハモり」が味わえる編曲になっています。
《道》(作曲:miwa furuse/編曲:若松 歓)
EXILEの楽曲です。
感動的な歌詞で、卒業式でも歌われることが多いようです。
随所にEXILEらしい、かっこいいコード(和音)が挿し挟まれています。
《Chessboard》(作曲:藤原 聡(Official髭男dism)/編曲:横山 潤子)
横山潤子さんらしい、アイディアに満ちたアレンジ。
原曲がポップスとは思えないようなストーリー性に満ちた音楽になっています。
《Jupiter》(作曲:ホルスト/編曲:松下 耕)
歌手・平原綾香さんのデビューシングル《Jupiter》より。
混声合唱らしい重厚なハーモニーと、神秘的なピアノパートが調和した、大変魅力的なアレンジになっています。
3. 唱歌・民謡などをアレンジした合唱曲
昔からある唱歌や、民謡などをアレンジした合唱曲です。ポップス以外にも、幅広いレパートリーに触れることができるのも合唱の魅力の一つです。
原曲はシンプルなメロディーであることが多いため、編曲に工夫が凝らされていることも多いジャンルです。どんなアレンジがされているか、ということにも注目して聴いてみてください。
《ふるさとの四季》(作曲:岡野 貞一ほか/編曲:源田 俊一郎)
学校で習ったことがきっとある、昔ながらの唱歌の数々を、四季の順番でメドレーにした作品です。
《鯉のぼり》、《夏は来ぬ》、《紅葉》、《冬景色》など、おなじみの曲が、全部で11曲セレクトされています。
すべて聴き終えれば、懐かしく、温かい気持ちにきっとなると思います。
《箱根八里》(作曲:滝 廉太郎/編曲:横山 智昭)
これまた有名な《箱根八里》です。
このアレンジではジャズをはじめとした様々な音楽のテイストが絶妙にミックスされており、何度聴いても聴き飽きない、エキサイティングな作品となっています。
《夕焼小焼》(作曲:草川 信/編曲:三善 晃)
誰もが幼いころに歌ったことがある《夕焼小焼》ですが、本曲は2台のピアノによる伴奏がついた、壮大かつ荘厳な編曲となっています。
《さくら》(日本古謡/編曲:武満 徹)
世界的に有名な作曲家、武満徹によるアレンジです。
和風の旋律が、とても複雑でミステリアスな和音で彩られています。
《ずいずいずっころばし》(わらべうた/編曲:信長 貴富)
わらべうたとして有名な《ずいずいずっころばし》をアレンジした作品です。
様々なアイディアに富んだアレンジで、聴いても歌っても、とても楽しい曲です。
《おてもやん》(熊本県民謡/編曲:若松 正司)
ここからは各地方の民謡をアレンジした作品を紹介します。
《おてもやん》は熊本県の民謡。迫力のある掛け声がとても印象的です。
《俵積み唄》(秋田県民謡/編曲:松下 耕)
続いては秋田県の民謡《俵積み唄》をアレンジした作品。
昔から伝わる日本的なメロディーと、ピアノパートによる現代的なリズム・和音との異質とも言える組み合わせが、独特のサウンドを醸し出しています。
テナーソロにも注目です。
《狩俣ぬくいちゃ》(沖縄県民謡/編曲:松下 耕)
最後に沖縄県の民謡です。琉球音階という独自の音階が使われ、いわゆる「沖縄っぽい」感じがする曲です。
疾走感のある場面、ゆったりと美しい場面、掛け声と手拍子が渾然一体となる賑やかな場面など、さまざまな聴きどころがある作品です。
4. 邦人作曲家による合唱曲
日本の作曲家による作品です。ここに挙げた以外にもたくさんの作曲家がおり、それぞれが数多くの素晴らしい作品を残しています。
ここでは少し難しめの曲も選んでいます。そのほうが各作曲家の個性をはっきりと味わってもらえると考えたからです。
やや難しいとは言っても、私なりに「いいな」と思ってもらえるような曲を挙げたつもりですので、身構えずに聴いて、雰囲気を感じていただければと思います。
《新しい歌》(作曲:信長 貴富)
作曲されたのは2000年ですが、タイトル通り今でも古びない魅力を持っている曲です。
フィンガースナップ、手拍子、シンコペーションを多用したメロディー、ジャジーなコードなどなど、「合唱にはこんな曲もあるんだ」と思えるような仕掛けが満載です。
《方舟》(作曲:木下 牧子)
はじめて聴いた時に魅了されたのがこの《方舟》という曲。
5/4拍子に貫かれた緊張感のあるテンポ、強烈なフォルテ、新鮮なコード進行など、非常に斬新なサウンドを持っており、1980年つまり昭和55年に初演(初めて演奏されること)されたとは思えないほど。
40年以上経った今でも、演奏される機会が非常に多い名曲です。
《雨》(作曲:髙田 三郎)
長年にわたって歌い継がれてきた名曲です。
しっとりとしたピアノと、柔らかいメロディーが大変美しい曲です。
混声合唱組曲《水のいのち》の第1曲目で、《水たまり》~《川》~《海》、そして最終曲の《海よ》と続き、「水の一生」を紡ぎます。
《花》(作曲:新実 徳英)
しっとりと美しいメロディーから始まります。
中間部の”さんさしおん!”に向かう展開は圧巻です。※さんさしおん=フランス語の「sensation」。英語ではセンセーションで「感動」の意味。
《曙》(作曲:鈴木 輝昭)
ピアノ伴奏のない合唱だけの場面から始まり、途中からピアノ伴奏が入ります。
ピアノがかっこいいので、ぜひそこまで聴いてほしい曲です。まるで宇宙を感じさせるようなサウンドです。
終盤の”ごらん ほら”からは非常に美しく、感動的なシーンです。
《ゆめみる》(作曲:荻久保 和明)
組曲《季節へのまなざし》の最終曲です。
組曲というのは、いくつかの複数の曲を組み合わせて、一つの作品として構成したもの。
《季節へのまなざし》は、《ひらく》《のびる》《みのる》、そして《ゆめみる》の4曲から成り、それぞれが春夏秋冬に対応するような構成となっています。
《ゆめみる》は単独でも圧倒的なドラマを持っていますが、4曲を続けて聴いてみると、よりその世界観を感じることができるでしょう。
終盤の変拍子の場面はぜひとも聴いてみてほしいです。
《ぜんぶ》(作曲:相澤 直人)
ここからはアカペラ(無伴奏)の作品をいくつか紹介します。
《ぜんぶ》は、『ちびまる子ちゃん』でおなじみの、さくらももこさんの詩に曲をつけた作品。
優しく包み込むような優しいメロディーとハーモニーが特徴です。
《露営のともしび》(作曲:高嶋 みどり)
女声合唱による無伴奏作品。
女声合唱ならではの透明感と、緊張感のあるハーモニーの持続が聴きどころです。
《Ⅳ(どちりなきりしたん)》(作曲:千原 英喜)
隠れキリシタンの祈りをテーマにした合唱曲です。
タイトルの「どちりな」は「ドクトリナ(教理)」、「きりしたん」は「キリスト教徒」を意味し、江戸時代の信仰の姿が音楽で表現されています。
神秘的な雰囲気から終盤の喜びに満ち溢れた音楽への展開が聴きどころです。
日本語とラテン語の両方が歌詩として歌われ、典礼用の鐘またはトライアングルが用いられます。
《Tempestoso》(作曲:松本 望)
ここからは再びピアノ伴奏つきの作品を紹介。
冒頭の激しい不協和音から10拍子による疾走と、まさに”Tempestoso(嵐のような)”な作品です。
《VocaliseⅡ》~《海辺にて》(作曲:三宅 悠太)
《VocaliseⅡ》と《海辺にて》という2つの曲が、いわばセットとして続けて演奏される形の曲です。
Vocalise(ヴォウカリーズ)とは母音(ア・イ・ウ・エ・オ)のことで、ここでは歌詩のない母音だけで歌う曲のことを指します。
《VocaliseⅡ》で詩の世界観を「音だけ」で表現した後、《海辺にて》に入っていくという構成です。
《夢の意味》~《夢の名残》(作曲:上田 真樹)
こちらも《夢の意味》と《夢の名残》2曲を続けて演奏するよう、楽譜に指示がされている作品です。
美しいメロディーと大きなスケール感を持つ《夢の意味》と、まるで夢現の間を揺蕩っているような、不思議な雰囲気の《夢の名残》の対比が見事な作品です。
《今年》(作曲:松下 耕)
谷川俊太郎さんの詩を曲をつけた作品。
平易な言葉を使いながらも、日々生きていくこと、生きていかねばならないことの希望と絶望、そして祈りが描かれます。
感動的な作品です。
《生きる》(作曲:三善 晃)
こちらも谷川俊太郎さんの詩による作品。
「生きているということ」というフレーズが、深い祈りを思わせるピアノの音型に乗せて歌われます。
《その木々は緑(ヴァイオリン伴奏付き)》(作曲:横山 潤子)
柔らかく優しいメロディーに、ヴァイオリンの伴奏がつくことで、親しみやすいだけでなく壮大なスケール感を感じられる曲になっています。
5. いろいろな言語の合唱曲
ここまで紹介してきた曲は、すべて歌詩が日本語でした。
しかし合唱は日本だけのものではありません。そこで次はいろいろな言語の合唱曲を紹介していきたいと思います。
《MI・YO・TA》(作曲:武満 徹/日本語)
まずは日本語の曲。世界的な現代作曲家、武満 徹による作品。
タイトルは、長野県御代田町(みよたまち)を指しています。
《My love dwelt in a Northern land》(作曲:エルガー/英語)
次に紹介するのは、外国語の中でも親しみやすい英語の合唱曲です。
《威風堂々》で知られるエルガーによる作品で、タイトル《My love dwelt in a Northern land》は、「かつて愛した人が、遠い北の地に住んでいた」という意味。
郷愁と物語性を帯びたこの曲は、過去の恋や別れ、あるいは死を思わせるような、
どこか哀しみをたたえた雰囲気が魅力です。
《Zigeunerleben》(作曲:シューマン/ドイツ語)
《Zigeunerleben(流浪の民)》は、シューマンの合唱作品の中でも特に知られた一曲で、ロマ(ジプシー)の自由で放浪的な暮らしを描いています。
リズミカルなピアノ伴奏に乗せて、合唱が軽やかに物語を紡いでいく構成で、民族的な情景が目に浮かぶようです。
ドイツ語特有の子音の響きや、躍動感あるフレーズも印象的で、合唱団でも人気の高い楽曲です。※子音というのは、例えば「かきくけこ(ka・ki・ku・ke・ko)」の”k”のことです。
《Trois beaux oiseaux du Paradis》(作曲:ラヴェル/フランス語)
繊細で美しい響きを持つフランス語の作品です。
タイトルは「天国の美しい三羽の鳥」。静かな中にも、ラヴェルらしい洗練された和声とメロディーが魅力の一曲です。
《Libiamo, ne’ lieti calici》(作曲:ヴェルディ/イタリア語)
イタリア語はオペラの主要な言語の一つで、母音(あ、い、う、え、お)が多く、歌うと非常に明るく伸びやかに響きます。
この曲はヴェルディのオペラ《椿姫》の中でも特に有名な一場面。
祝宴の中で交わされる乾杯をテーマにした、明るく軽やかで親しみやすい曲です。
ソロに続いて合唱が入ります。
《Esti dal(夕べの歌)》(作曲:コダーイ/マジャール(ハンガリー)語)
《Esti dal(エスティ・ダール)》は、ハンガリーの作曲家ゾルターン・コダーイが書いた、夜の祈りをテーマにした合唱曲です。
旅人が眠る前に神に安らぎと家族の無事を願う内容で、静かであたたかい雰囲気に包まれています。マジャール語(ハンガリー語)の歌詞で歌われており、民族的な響きと素朴な祈りの言葉が印象的です。民謡をもとにしたメロディは心にしみ、語りかけるような美しさがあります。
《AMETSETAN》(作曲:ブスト/バスク語)
スペイン・バスク地方出身の作曲家ハビエル・ブストによる無伴奏合唱曲です。タイトルはバスク語で「夢のなかで」という意味。
男声合唱の力強さ、女声合唱の美しいハーモニー、リズミカルな舞踊のリズム、ゆったりとした祈りの響きなど、様々な場面がメドレーのように連続して展開されます。
紹介する演奏では、楽器も用いられ、楽しい演奏になっています。
《Bogoroditse Devo》(作曲:ラフマニノフ/ロシア語)
《Bogoroditse Devo(ボゴロディツェ・ディエヴォ)》は、ロシアの作曲家ラフマニノフが書いた無伴奏の宗教合唱曲で、「アヴェ・マリア」にあたる祈りの言葉に曲をつけたものです。
言語はロシア語に近い教会スラヴ語で、深く響く発音と荘厳なハーモニーが特徴です。
静かな祈りのうちに徐々に高まり、やがて熱く訴えかけるようなクライマックスを迎えますが、最後は再び静けさの中に溶けていきます。
ラフマニノフらしい豊かな和声と深い感情が感じられ、聴く人の心に深くしみわたります。
ロシア正教の精神文化を感じさせる、静けさと力強さをあわせ持った名曲です。
《Virta venhettä vie》(作曲:クーラ/フィンランド語)
フィンランドの作曲家トイヴォ・クーラが手がけた無伴奏合唱曲。フィンランド語の詩に音楽が寄り添った作品です。
タイトルは「流れは小舟を運ぶ」という意味で、流れに身をゆだねるような自然の情景と人生のたとえが重なります。フィンランド語の柔らかくも独特な響きが、音楽に素朴で静かな力強さを与えています。
メロディは流れるように歌われ、ハーモニーは控えめながらも深い味わいがあります。フィンランドの自然や詩の感性を感じられる、繊細で印象深い合唱曲です。
《Pamugun》(作曲:フェリシアーノ/タガログ語)
フィリピンの作曲家フランシスコ・フェリシアーノによる無伴奏合唱曲で、フィリピンの言語のひとつであるタガログ語の民謡をもとにした作品です。
タイトルの「Pamugun」は「すずめ」あるいは「つばめ」のような小鳥を指す言葉で、主に女声が小鳥を、男声がハンターの役割で、追いかけっこを演じます。
独特のリズム感と擬音のような独特の歌詩が印象に残ります。
絶叫、口笛などの表現もほかではあまり聴かれない、とてもおもしろい曲です。
《El guayaboso》(作曲:ロペス/スペイン語)
キューバ出身の作曲家グイド・ロペス=ガビラン(Guido López-Gavilán)による、スペイン語作品。
タイトルの「Guayaboso」は「ほら吹き」という意味で、音楽はラテン系らしくシンコペーションを多用したリズムと遊び心にあふれています。
スペイン語の持つ軽やかさと陽気さが、音楽とぴったり重なった一曲です。
《Baba Yetu》(作曲:ティン/スワヒリ語)
アメリカの作曲家クリストファー・ティンによって作られた、スワヒリ語による壮大な合唱曲です。
タイトルの意味は「我らの父」で、キリスト教の「主の祈り」をスワヒリ語に翻訳して歌詞としています。
もともとはコンピュータゲーム『シヴィライゼーションIV』のテーマ音楽として書かれましたが、新しい合唱レパートリーとして人気が出つつある作品です。
アフリカ音楽のリズムや旋律に、オーケストラ的な広がりと荘厳さが加わり、世界の人々をつなぐようなスピリットを感じさせます。
《THE GROUND》(作曲:ヤイロ/ラテン語)
最後にラテン語の作品を紹介します。
ラテン語は日常的に使用される言語ではないものの、合唱では非常にメジャーな言語です。(次の見出し「いろいろな時代の合唱曲」もあわせてごらんください。)
タイトルは英語ですが、これはより多くの人に親しみを持ってもらえるように付けられたもの。歌詩はミサ曲の「Sanctus」と「Agnus Dei」から取られています。
ピアノと弦楽四重奏を伴って演奏され、声と弦が一体となり、穏やかで美しい祈りの世界観をつくり出します。
宗教的な作品ですが、ハーモニーやメロディーは現代的で、親しみやすい作品です。
繰り返される転調はドラマチックで、聴き終わったあとは大作映画を見終わったあとのような感覚が残ります。
6. いろいろな時代の合唱曲
今度は、時代、つまり合唱音楽の歴史という観点から、いくつかの作品をご紹介したいと思います。
ここで取り上げる曲の中には、300年以上前に作曲されたものもありますが、今なお多くの合唱団によって演奏されています。過去の「歴史的遺物」ではなく、現役のレパートリーとして生き続けているのです。こうしてはるか昔の音楽を、今も歌える・聴けるというのは、合唱の面白さのひとつです。
作品名の後に記載している()内には、作曲家の生没年を示しています。時代が変われば、音の響きや音楽の雰囲気も大きく変わっていきます。ぜひ、その違いを味わってみてください。
なお、合唱のメインストリームは西洋音楽にあり、その歴史的ルーツは宗教音楽にあります。そのため、ここでは宗教的な作品を多く紹介しています。「宗教」と聴くとつい身構えてしまいそうですが、今はあまり難しく考えずに、気軽に聴いてみてください。
《Ubi Caritas Et Amor》(グレゴリオ聖歌/8世紀~9世紀頃)
グレゴリオ聖歌と言って、合唱音楽の中でもかなり初期の形態です。斉唱、つまりパートに分かれることなく、全員で同じ旋律を歌うスタイルで、ハーモニーはありません。
メロディーも、現代の感覚からすると控えめな抑揚で、非常にシンプルです。ちょうど、お祈りの言葉と音楽のあいだにあるような不思議な響きで、「歌う」というより、「唱える」に近い印象を受けるかもしれません。
《Messe de Nostre Dame: Kyrie》(マショー/1300年頃~1377年頃)
《ノートルダム・ミサ》の中の一曲、《キリエ(憐れみの賛歌)》です。
さきほどのグレゴリオ聖歌と異なり、ハーモニーのある音楽であることが分かると思います。
ただ、私達が聴き慣れた響きとは少々異なり、「美しい」と言うよりは「古(いにしえ)」という印象を受けると思います。中世と呼ばれる時代の音楽です。
《Ave Maria》(ジョスカン・デ・プレ/1450年頃~1521年)
ジョスカン・デ・プレは、この時代の合唱音楽を語る上で欠かせない存在です。
この《Ave Maria(アヴェ・マリア)》では、”アヴェ・マリア”と歌うメロディーが、それぞれのパートによって少しずれて歌われ、進んでいきます。
こうした手法やそのように書かれた音楽を、ポリフォニーと呼びます。《カエルの歌》のような輪唱の発展形、と考えるとイメージしやすいかもしれません。
《Kyrie from Missa Papae Marcelli》(パレストリーナ/1525年頃~1594年)
パレストリーナは、ポリフォニー音楽をさらに洗練・発展させた作曲家です。
《聖マルチェルスのミサ》の《キリエ》では、メロディー同士が複雑に絡み合いながらも、言葉の明瞭さと音楽的な美しさがしっかりと保たれています。
また、この頃まで時代が進むと、私たち現代の耳にも自然に響くようなハーモニーになってきていることが感じられると思います。
《Jesus bleibet meine Freude》(バッハ/1685年~1750年)
さて、ここからは「聴いたことのある作曲家の名前」や「どこかで耳にしたことのあるメロディーの曲」を紹介していきたいと思います。
まずは、音楽史でも特に有名な作曲家、バッハです。特にこの《Jesus bleibet meine Freude(主よ、人の望みの喜びよ)》は、耳にする機会が多いのではないでしょうか。
ここまで紹介してきた曲は伴奏のないものが多かったですが、この時代以降、合唱とともに楽器(オルガンやオーケストラなど)が使われることが一般的になっていきます。
《Messiah》より《Hallelujah Chorus》(作曲:ヘンデル/1685年~1759年)
続いてご紹介するのは、とても有名なヘンデルの《メサイア》より、《ハレルヤ・コーラス》です。
この時代になると、合唱の規模がさらに大きくなり、多くの楽器が加わることで、演奏が一層華やかになってきます。
祝祭的な雰囲気を持つこの曲は、今でも多くの場面で演奏されています。
《Dies irae》(モーツァルト/1756年~1791年)
これまた有名なモーツァルトの《レクイエム》より《ディエス・イレ(怒りの日)》です。
「怒りの日」という意味を持つこの曲は、終末の日の情景を描いた非常に緊迫感のある楽曲です。
疾走感のあるリズム、緊張感のあるハーモニー、そして激しく迫ってくるような合唱の響きが、強烈な印象を与えます。
ミサ曲でありながら、劇的で、ドラマのような展開が感じられるのもモーツァルトならではです。
《歓喜の歌》(ベートーヴェン/1770年~1827年)
《交響曲第9番》より《歓喜の歌》、いわゆる「第九」です。
年末の公演などでもおなじみで、合唱曲としては最も広く知られている一曲と言えるでしょう。もはや風物詩と言っても良いくらいです。
壮大なオーケストラと力強い合唱が一体となり、人類愛や平和を高らかに歌い上げます。
紹介した音源では、13:30くらいから《歓喜の歌》が始まります。
《Richte mich, Gott》(メンデルスゾーン/1809年~1847年)
ここから「ロマン派」と呼ばれる時代に入ります。合唱のレパートリーも数多く、演奏される機会も多いです。
《Richte mich, Gott(神よ、私をさばいてください)》は冒頭の男声のユニゾンと、女声のハーモニーにまず心惹かれます。ロマン派らしく、格調高さと美しさが同居した作品です。
《Wie lieblich sind deine Wohnungen》(ブラームス/1833年~1897年)
《Wie lieblich sind deine Wohnungen(なんと愛らしいことか、あなたのいますまいは)》は、ブラームスの大作、《ドイツ・レクイエム》の中の1曲。
柔らかなメロディー・ハーモニーを持つ、美しい作品です。
《O Fortuna》(作曲:オルフ/1895年~1982年)
《O Fortuna(おお、運命の女神よ)》は、ドイツの作曲家オルフによるカンタータ《カルミナ・ブラーナ》の冒頭と終結を飾る合唱曲です。
ラテン語の詩に壮大なオーケストラと合唱が重なり、運命の無常さや力強さを圧倒的なスケールで描き出します。“Fortuna(フォルトゥーナ)”とはローマ神話に登場する運命の女神であり、人の栄光や没落をも左右する存在とされています。
《O Fortuna》はその劇的で迫力ある響きから、映画やCM、スポーツイベントなどでも頻繁に用いられています。音楽に詳しくない方でも、きっとどこかで耳にしたことがあるはずです。
《Salve Regina》(プーランク/1899年~1963年)
プーランクは、フランスの近代を代表する作曲家で、あまり聴いたことがない名前かもしれませんが、合唱界では重要な存在です。
この《Salve Regina》は、ラテン語の祈りの言葉に音楽をつけた作品で、悲しい響きながら、しなやかで透明感のある響きが特徴的です。
メンデルスゾーンやブラームスのようなドイツ・ロマン派の作曲家と比べると、印象が大きく異なることが分かると思います。
《Agnus Dei》(バーバー/1910年~1981年)
この曲は、もともと1936年に作曲された《弦楽のためのアダージョ(Adagio for Strings)》をもとに、1967年にラテン語の典礼文「アニュス・デイ(神の子羊)」を加えて合唱曲として編曲された作品です。
冒頭はソプラノによる静かな旋律から始まり、他の声部が順に加わっていきます。全体的にゆったりとしたテンポで進行し、声が折り重なるように響く美しさが特徴です。歌詞は「神の子羊、世の罪を除きたもう主よ、我らに平安を与えたまえ」と繰り返され、深い祈りの感情が静かに、しかし強く表現されています。
元となった《弦楽のためのアダージョ》は、アメリカの葬儀などでも用いられることの多い荘厳な作品であり、それに歌詞が加わることで、より人間的な哀悼や希望が浮かび上がります。合唱で演奏することで、一層の精神性や奥行きを感じられる名作です。
《Cantate Domino》(ラター/1945年~)
《Cantate Domino(主に向かって新しい歌を歌え)》は、イギリスの現代作曲家ジョン・ラターによる作品です。このあたりから、紹介する合唱曲は「現代」の領域に入ってきます。
ラターは、教会音楽や合唱音楽で高く評価されている作曲家で、世界中の合唱団で頻繁に取り上げられる人気作曲家の一人です。日本のコンサートでも非常によく歌われます。
多くの場合歌詩はラテン語の聖書詩篇から採られており、宗教的なテーマを扱っていますが、音楽自体はとても親しみやすく、明るくキャッチーな旋律と軽やかなリズムが特徴です。
この《Cantate Domino》も、合唱初心者にも「聴きやすく」「楽しく」感じられる曲のひとつです。
《Lux Aurumque》(ウィテカー/1970年~)
現代アメリカの作曲家ウィテカーによる合唱作品です。
タイトルはラテン語で、”Lux”は「光」、”Aurumque”は黄金の意味。
この記事の最初の方で、ヴァーチャル合唱団というものを紹介しましたが、ウィテカーはその創始者としても知られています。《Lux Aurumque》はその演奏で取り上げられました。
従来の4パートを超えた分厚いハーモニーが用いられており、非常に多くの音が同時に重なり合い、神秘的な世界観を醸し出しています。
《Deus Caritas Est》(作曲:佐藤 賢太郎(Ken-P)/1981年~)
最後に、日本の作曲家・佐藤 賢太郎さん(通称 Ken-P さん)をご紹介します。
この作品は、本項の冒頭で紹介したグレゴリオ聖歌《Ubi Caritas Et Amor》を題材にしたものです。
冒頭では、グレゴリオ聖歌の旋律が静かに提示され、そこから徐々にハーモニーが重なっていきます。
音楽はまるで物語のように展開していき、喜びに満ちた感動的なクライマックスが最後に待っています。
曲の随所にグレゴリオ聖歌の旋律が散りばめられているのも注目ポイントです。
まとめ
この記事では、いろいろな合唱曲を次の6つのジャンルに分けて紹介しました。
- 学校で歌われる合唱曲
- ポップスをアレンジした合唱曲
- 唱歌・民謡などをアレンジした合唱曲
- 邦人作曲家による合唱曲
- いろいろな言語の合唱曲
- いろいろな時代の合唱曲
なるべくいろいろな曲に触れていただけるよう、私の知る範囲でなるべくまんべんなく紹介しました。
しかしながら、膨大な合唱曲の中ではこれもほんの一握りにすぎず、セレクトに偏りがあることも否めません。
ぜひたくさんの曲に出会い、お気に入りの作品を見つけてみてください。