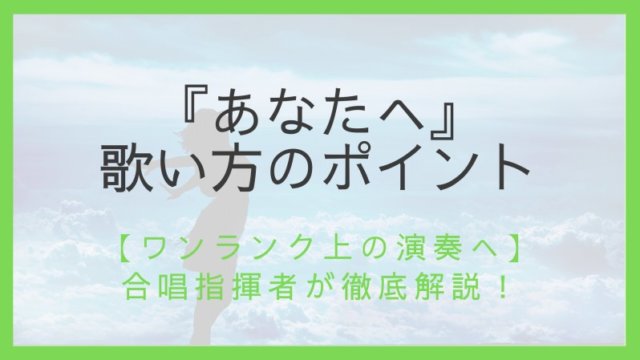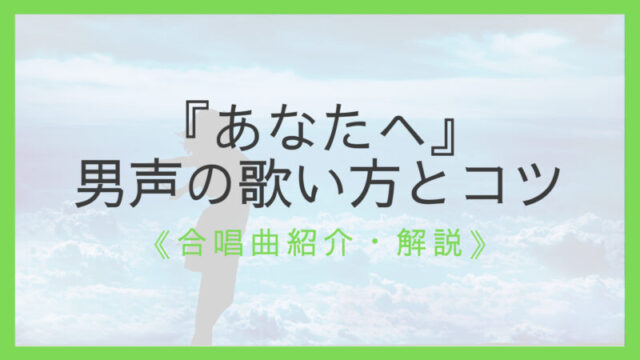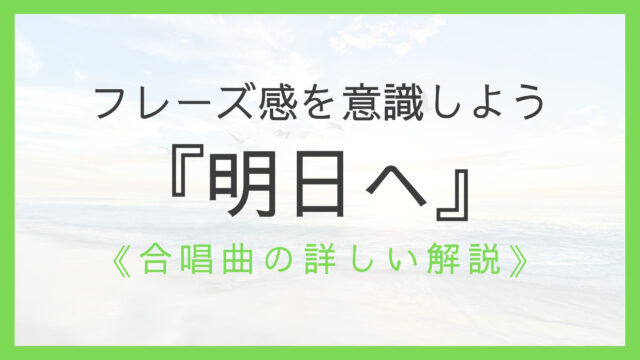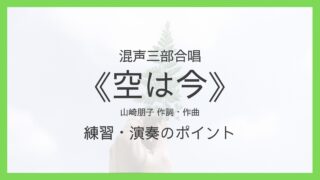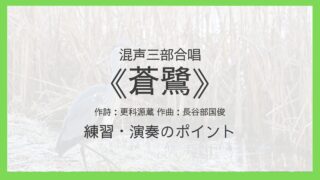【混声四部】《朝》(作詩 谷川俊太郎/作曲 大熊崇子)練習・演奏のポイント
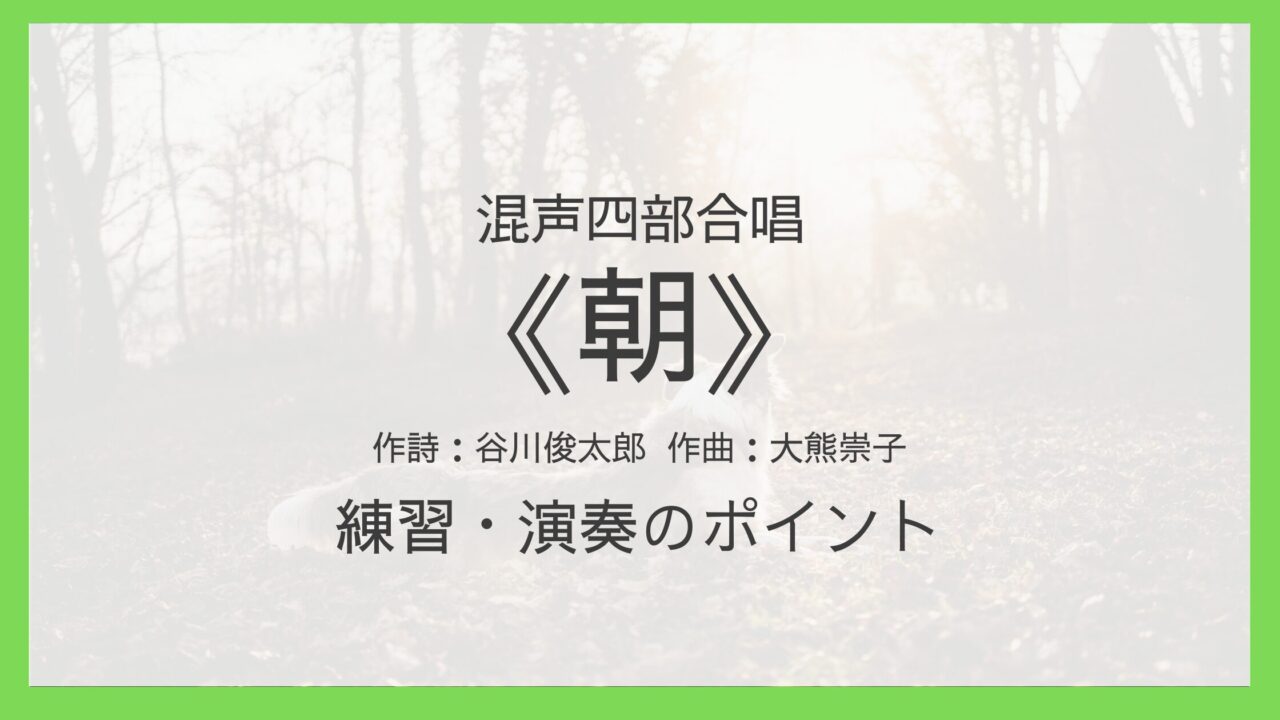
谷川俊太郎さん作詩、大熊崇子さん作曲の合唱曲《朝》は、深淵なスケール感を持ったテキストとドラマチックな音楽が魅力の作品です。
この記事では、そんな《朝》の演奏に役立つポイントを、練習番号に沿って具体的に解説しています。
この記事を参考に、ぜひ練習・演奏に挑戦してみてください。
もくじ
《朝》の練習番号
練習を始める前に、まずは練習番号(【A】【B】…)をつけておきましょう。楽譜にあらかじめつけられている場合はそのまま使ってもかまいません。
また、小節数が書かれていない場合はそちらも書き込んでおくととても便利です。
今回は以下の通りつけました。
- 【冒頭】…1小節 “(また)あさがきて”
- 【A】…4小節 “ララ”
- 【B】…10小節 “(よ)るの”
- 【B’】…16小節 “(かき)のきの”
- 【C】…25小節 “ララ”
- 【D】…30小節 “(ひゃく)ねんまえ”
- 【E】…39小節 “あたり”
- 【F】…48小節 “だ”
- 【G】…53小節 “(いつ)だったか”
- 【H】…61小節 “(それか)ら”
- 【I】…71小節 “やっと”
- 【J】…82小節 “そんなことも”
- 【K】…90小節 “ララ”
- 【L】…102小節 “(け)さ”
- 【M】…115小節 “(さか)なたちと”
※【冒頭】のアウフタクト(”また”)の小節は0小節目としてカウント
練習番号をつけることで、練習する際の指示出しをスムーズに行うことができるようになります。例えば、「次は【A】からお願いします」などのように言えますね。
また、《朝》のように様々な場面が展開するドラマチックな作品では、全体の構成感を把握することがとても大切で、練習番号はそのためにも役立ちます。
音楽の構成を分析する際は、各場面の歌詩・曲想が縦書きの詩ではどの行に対応しているのか、どこで”ラララ”の場面(【A】【C】【F】【K】)が挿し込まれているのかなどといったことに着目してチェックしてみてください。
練習のコツ・演奏のポイント
ここからは、先ほどつけた練習番号に沿って解説を進めていきます。
【冒頭】…1小節 “あさがきて”
歌い出しの”またあさがきて”では、音量に注目。いきなりfです。ユニゾンの力強さを活かして、きっぱりと歌い、インパクトのある場面を演出しましょう。
“またあ”のフレーズは音がレ→ソ→ドと一気に跳躍します。難しいのでよく確認しておきましょう。最高音の”あ”の音をあらかじめよくイメージしておくことがコツです。ゆっくりとしたテンポで練習するのもよいでしょう。
また、ここではピアノパートとのアンサンブルも大切。”あさがきて”の”あ”でタイミングよくピアノパートのコードが響くよう、息を合わせましょう。指揮者の役割も重要になってきます。
続く”ぼくは”で一気に4声になってハモります。f感をキープすることと、ハーモニーを両立することが課題です。
ハーモニーしっかり決める、ここでのコツは2つ。ひとつは音が分かれる前、”あさがきて”のユニゾンの音をしっかりそろえておくこと。もう一つは、「ここから分かれるぞ」ということを把握し、意識しておくことです。こちらもゆっくりとしたテンポで練習し、どのような響きになるのか、音符一つ一つで確認しておきましょう。
3小節目の音量はmpです。ここで一気に音量を小さく絞ります。直前のfとの対比が大切です。また、小さくなると言っても弱々しくならないこともポイントです。言葉の力強さを保ち、むしろ緊張感が高まるように歌いましょう。すこし声を潜めるようなニュアンスがあってもよいでしょう。
【冒頭】では音量・歌い方の変化を思い切ってつけることで、聴いている人をぐっと惹きつけることができる場面です。
【A】…4小節 “ララ”
【A】からはテンポアップしますので、まずはそのスピード感をつかんで、乗り遅れないようにします。
音量はpですが、シンコペーション(付点やタイで繋がれた音の組み合わせによるリズム)を活かして、生き生きと、躍動的に歌いましょう。一つ一つの音符をややはっきり目に、リズムを立たせて。また、この後にあるクレッシェンドに対する期待感を胸のうちに秘めて歌いましょう。
クレッシェンドは途中まではじわじわと、そしてすべてのパートがロングトーンに入る8小節目の後半から一気に駆け上がるイメージで。こうすることで、次の場面が目の前に開けてくるような表現ができると思います。
【B】…10小節 “(よ)るの”
【A】と同様、ピアノパートのリズムを感じながら、テンポに乗って歌いましょう。
一方で、ここからは日本語の歌詩が出てきますので、言葉のつながりを意識した歌い方にする必要があります。具体的には、”夜の間の夢をすっかり忘れてぼくは見た”までをひとまとまりにして、フレーズを大きく捉えて歌いましょう。
これを”ラララ”と同じようにリズムを立てて歌ってしまうと、言葉のつながりが失われてしまい、文字同士がバラバラに聞こえてしまいます。
【B’】…16小節 “(かき)のきの”
ここからは男声が主役。女声はハミング”Hum.”でハーモニーを作ったり、男声と掛け合いとなる、カウンターメロディー(サブのメロディー)の役割になります。
メロディーを歌うときには【B】と同様言葉のつながりを意識して、”柿の木の裸の枝が風にゆれ”を一つのまとまりで捉えます。
mpで始まりますが、これまでと同様弱々しくはならないように。むしろ言葉をしっかり伝える意識を持ちたい場面です。
クレッシェンドを経て、20小節からはソプラノがメロディーになります。この男声→ソプラノのメロディーの受け渡しが自然になるよう、流れを意識しましょう。
“犬が陽だまりに”になると、これまでずれて歌っていた3パートのタテがそろいます。「ここでタテがそろう」という意識を持っておくことが大切です。
“寝そべってるのを”は、一転ユニゾンです。場面の終わりに向かってf→mfと収束していくフレーズですので大きくなりすぎないように。デクレッシェンドもフレーズを収束させて行くために書かれています。歌い終わりをうまく処理して自然に収めるようにしましょう。
【C】…25小節 “ララ”
【A】と似た場面ですが、強弱が異なっていることに注意しましょう。
このmfは比較的しっかりと、また【A】と同様リズムを立てて歌いましょう。ただし、荒っぽくならないように気をつけます。
フレーズ最後のデクレッシェンドは重要です。少し柔らかく、フレーズを上手に収めることで、次の場面つなげます。
【D】…30小節 “(ひゃく)ねんまえ”
mpの音量自体はこれまでも出てきましたが、ここは少し静かでシリアスなニュアンスにしたい場面です。モノローグのような雰囲気で、つぶやくように歌っても良いでしょう。
ピアノパートの伴奏形が、リズミカルなシンコペーションから、長い音符を中心とした動きの少ないものに変わることも感じることも忘れずに。
36小節からはじまるクレッシェンドは、つぶやきの雰囲気からたっぷりと歌い上げるような雰囲気に変化させていきます。ここはダイナミクスレンジ(音量の差)を大きく取りましょう。
38小節の”ろう”のロングトーンはハーモニーをしっかり決めたいポイントです。男声の低めのミの音がしっかりと鳴ると響きが充実します。
【E】…39小節 “あたり”
直前のクレッシェンドから一転mpになります。subito(スビト/すぐに)的な雰囲気で、予想を裏切るかのようにぐっと音量を絞ることで、聴き手を惹きつけることができる場面です。
なんとなくの散漫な弱声になることなく、むしろ集中力を高めて、緊張感のあるユニゾンを歌いましょう。”あたり前な所のようでいて”、”思いがけない”という歌詩に対応させた表現ができると思います。
44~45小節のソプラノと男声の”きっと”のフレーズは、幅広い跳躍(離れた音へ跳ぶこと)があり難しいです。上がった先の音をしっかりと見据えて歌いましょう。男声は上がった先でソプラノと同じ音になります。
46~47小節の”思いがけない場所なんだ”では少しテンポを緩め、言葉を噛みしめるように歌ってみましょう。
【F】…48小節 “だ”
48小節は、合唱にとっては【E】のフレーズの終わりとなっていますが、ピアノパートはここから次の音楽が始まっています。直前のrit.を引きずらずに、a tempoに戻すことが大切です。
ここは”ラララ”で歌う場面なので【A】や【C】と同じようですが、リズムに注目してみると、4分音符が主体となっており、シンコペーションが主体だった【A】【C】とは少し様子が異なります。そのため、【F】の”ラララ”は全体的にレガートに(なめらかに)歌ってみても良いと思います。
なぜこのような変化をつけるかというと、続く【G】の場面がこれまでと大きく雰囲気を変えるからです。【G】では転調があり、この曲ではじめてpの音量が出てきます。また、テンポも少し遅くなります。そこに向かって雰囲気を整えていくのが、この【F】の場面の役割なのです。52小節にあるデクレッシェンドとrit.も同様、【G】への準備です。
【G】…53小節 “(いつ)だったか”
先ほども触れましたが、【G】はこれまでと音楽がガラリと変わります。変化する要素をまとめておきます。
- ト長調からニ長調へ転調
- 四分音符=144から104へスローダウン
- はじめてpが登場
- ピアノパートの音域が高音中心に
合唱はテンポが緩むことに注意して、急がずに。またpではより丁寧に言葉を伝えることを意識しましょう。
56小節あたりからの”ちいさな”とずれて入るところは、入りの”ち”を少し強調して、旋律の絡みをアピールします。このとき大きくなりすぎずにpをキープすることと、言葉のレガートな流れを失わないことを意識しましょう。
“たまごだった”で3パート合流しますが、ここで不自然に盛り上がらないように、少しセーブするのが良いと思います。(音型に合わせて自然に盛り上がる程度ならOKです。)
【H】…61小節 “(それか)ら”
この【H】の場面は、曲全体の中でも最も大きく音楽が動きます。転調を何度も繰り返しながら、同時にaccel.(アッチェレランド/だんだん速く)していき、クレッシェンドも加わるドラマチックな場面です。
まずは”それから”、”ちいさな”、”さかな”、”とり”などの言葉、特に語頭を少し強調して歌いましょう。こうすることでメロディーのずれや絡み合いがアピールでき、音楽に立体感が出ます。
65小節では♭系の調へ、69小節では♯系へと転調します。♭系や♯系へと切り替わるところは音が取りにくいので、境目のところの音はしっかり確認しておきましょう。
【H】の後半から、【I】のfに向かってクレッシェンドしていきます。”それから”、”それから”と続いて、”やっと”とゴールを迎えるようなダイナミックなクレッシェンドにしましょう。ダイナミクスレンジを大きく取りたい場面ですから、【H】の前半で大きくなってしまわないよう我慢して、クレッシェンドが始まるまで小さめの音量をキープすることがコツです。
【I】…71小節 “やっと”
まさに”やっと”という感じでfが登場します。このfは単に盛り上がるだけでなく、Grandioso(グランディオーソ/雄大に)的な雰囲気があっても良いでしょう。豊かな息でたっぷりと歌ってください。
74小節に登場する、meno fの「meno」は「より少なく」の意味。つまり、meno fは控えめなfという意味になります。mfでないのは、あくまでf的な音楽をキープしながらも、歌詩の哲学的なニュアンスを出して、印象的に歌ってほしいというような意図を読み取ることができます。
79小節ではffを迎えます。【H】の場面のクライマックスシーンとなります。
【J】…82小節 “そんなことも”
82~85小節では、メロディーがソプラノ→男声→アルトと引き継がれながら歌われます。”そんなこともぼくらふくしゅうしなきゃ”、”いままで”という歌詩の流れを意識して、それぞれのフレーズが途切れ途切れにならないようにしましょう。
“よしゅうばっかり”はMeno mossoでテンポが遅くなります。ピアノパートの鳴らすコード(和音)をよく感じながら歌いましょう。クレッシェンドは音型の上昇に合わせて自然に。デクレッシェンドは語感を活かすように。
“しすぎたから”はつぶやくように歌います。ソとファには♯がつくことに気をつけましょう。ロングトーンに入ってからのデクレッシェンドでうまくフレーズを収めます。
【K】…90小節 “ララ”
【A】【C】【F】に続いて4回目の”ラララ”の場面です。ここはpで始まり、accel.しながらmf、そしてさらにその先にあるfまで見据えてクレッシェンドしていきます。
94小節は♭系の調へ転調しています。その前93小節のバスパートが上昇音型をともなって全体をリードするイメージで。
99小節のmpはsubito的な雰囲気で、ぐっと音量を絞り、その後のクレッシェンドで一気にfまで持っていきます。
【L】…102小節 “(け)さ”
前半の【B】と対応する場面です。同様に言葉のつながりを意識して歌いましょう。
111小節の“(おしえ)る”のロングトーンは、決めるのが難しい複雑な和音(E♭mM7)です。練習するときは、最初はソプラノを抜いて、マイナーコード(E♭m)を確認しておきましょう。その後でソプラノに入ってもらいます。
続いて112~113小節の和音の切り替わり(E♭mM7 → D)も練習しておきたいポイントです。アルトは楽譜上ソ♭ → ファ♯へ変わりますが、実際に歌う音は同じなので注意しましょう。ここでは男声の音が変わることで全体の和音が変化します。同じ音を伸ばし続ける女声もそれを感じながら歌うとハーモニーが良くなります。
【M】…115小節 “(さか)なたちと”
最後の場面です。アウフタクトの”さか”はrit.してたっぷりとタメて。
【M】に入ってからはゆっくり目のテンポで堂々と。ただし、アクセントっぽくならずに、あくまで言葉に沿ったレガートで歌いましょう。連続した8分音符が拍節的(4拍子がはっきりと出すぎる)にならないように気を付けて。
“ころすかもしれぬ”というフレーズは言葉の持つ冷たいニュアンスを出したいところです。”ころす”のkの子音を「こする」ことでそのニュアンスを表現できると思います。直前のデクレッシェンドで、それを匂わせることもできるでしょう。
121小節はffでフィナーレです。”わかちあいたい”コードをしっかり決め、ラストを飾りましょう。このあたりは、練習の段階ではピアノパートなしでハーモニーの練習をしておくとよいと思います。
122小節からのロングトーンを例に取ります。まずはバスのソの音をしっかりと安定させましょう。これが和音を支える土台になります。次にソプラノ・テノールのレの音がそろっていることを確認します。最後に、アルトはこれらの音をよく聴きながら中に入り、和音を完成させます。ピアノと合わせるときは、ピアノの音もよく聴きながら歌いましょう。
終わりに
最後までご覧いただきありがとうございました。
この記事を参考に、良い演奏ができることを願っております。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。