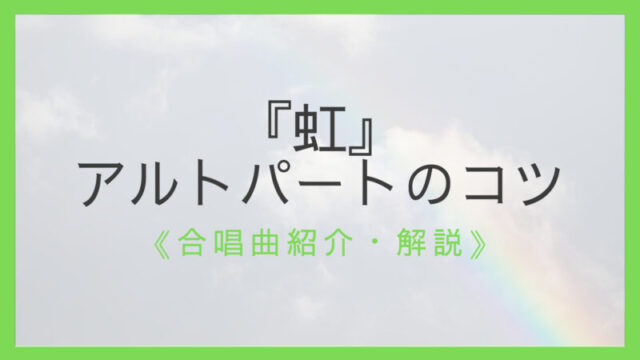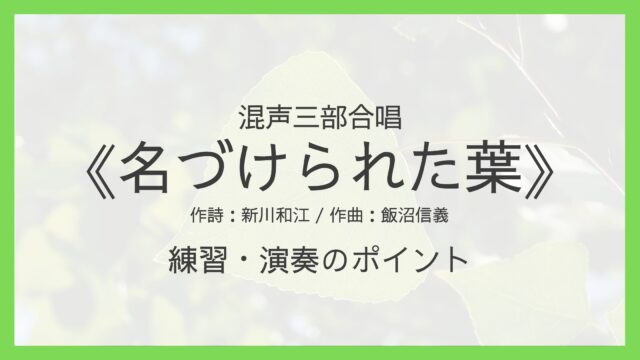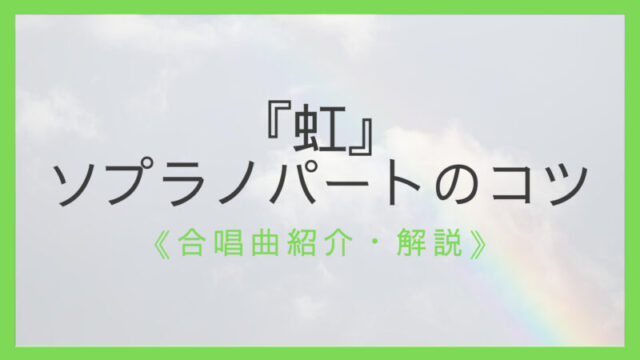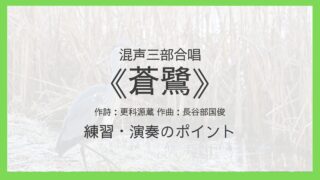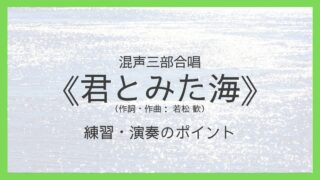【混声四部】《虹》(作詞・作曲:森山直太朗 御徒町凧 編曲:信長貴富)練習・演奏のポイント
練習・演奏のポイント-68a719eb6cb59-1280x720.jpg)
中学校でも人気の高いレパートリーである《虹》。Nコンの課題曲として書かれた混声三部合唱が有名ですが、四部バージョンも書かれています。
この記事では《虹》(混声四部)の演奏に役立つポイントを、練習番号に沿って具体的に解説しています。
この記事を参考に、ぜひ練習や演奏に取り組んでみてください。
練習・演奏のポイント
楽譜に記載されている練習番号に沿って、解説を進めていきます。
【Intro】(1小節~)
冒頭の5小節分については楽譜には練習番号がありませんが、ここでは【Intro】と呼ぶことにします。
ピアノの前奏にはrubato(ルバート/自由に)と書かれていますので、テンポはある程度自由に感じながら、自然に緩んだり、巻いたりしながら進めましょう。なお、指揮者がここで4拍子をしっかり振ってしまうと、ピアニストを過度に制限してしまいます。そうならないために、はっきりと示す箇所はしぼって(例えば、各小節1拍目など)、全体としてはゆるやかに振るようにすると良いと思います。
前奏でピアノパートに細かく書かれているクレッシェンドやデクレッシェンドは、「風のように」であるだとか「光がきらめくように」だとか、何かしらのイメージを持って解釈すると良いと思います。
合唱は4小節目から入ります。指揮者はソプラノに対してキュー出しをしても良いでしょう。その後、男声→アルトと順に入っていきます。Hum.の流れが自然に受け渡されるよう意識してください。特に、男声からアルトに移る「ド」の音、ソプラノからアルトに移る「シ♭」の音は確認しておきましょう。
合唱が入って以降は、ピアノとのアンサンブルも大切です。クレッシェンド~デクレッシェンド、そしてリタルダンドのタイミングをお互いに感じながら演奏しましょう。
【A】
【A】の入りはpとなっていますが、弱々しくならないように、メロディーとしての存在感はしっかり保ちましょう。“ひろがる” の h の子音は少し長めに歌い、言葉が伝わるように。
【A】のフレーズはユニゾンから始まり、”おもいはせ” でハモります。音が分かれることで各パートが頼りなくならないよう、存在感をキープしましょう。
この7小節あたりでは音が高くなりますが、pを保とうとして無理に抑制する必要はなく、音型に従って自然に盛り上がっても構いません。その場合、8小節のロングトーンの中で少し落ち着かせると良いと思います。
【B】
“きらめく”のフレーズは男声 → アルト → ソプラノの順に入っていきます。パートどうし聴き合いながらタイミングよく入りましょう。kの子音を早めに出し、母音がオンザビートで鳴るように意識してください。ただし、言葉を強調しようとしてkがきつくならないようにしましょう。
また、パート間でのタテのそろいも意識しましょう。15小節の”ゆびをたて”では全パート、16小節の”ゆびを”は内声、17小節は低声などがそろっています。
【C】
【C】からは4パートでタテがそろいますので、ハーモニーを確認しておきましょう。”よろこび”の”よ”の音で伸ばし、和音を確認しておくと良いと思います。ソプラノとテノールの「ラ♭」が和音の根音、ベースの「ミ♭」が第5音、アルトの「ド」が第3音となります。
次にメロディーを見ていきます。”よろこびとかなしみ”のように8分音符が主体のメロディーでは、歌い方が拍節的になってしまいがちです。「拍節的」というのは、一つ一つの音符がバラバラで途切れ途切れに聞こえたり、”よろこびとかなしみ“のように、表拍のところで変にアクセントが付いてしまうような歌い方です。そうなってしまわないよう、言葉の流れを意識して、レガートに歌うことを忘れないようにしましょう。
24小節の”(と)きがあり”はコードが難しいので、一音ずつハーモニーを確認しておくと良いでしょう。特に臨時記号がつけられた音に注意してください。跳躍音程を丁寧に歌うことも意識しましょう。
26小節はメロディーの上行形にうまく乗ってクレッシェンドします。次にmpが出てきますが、それよりも大きくしておいてsub.(スビト/急に)的な音量差を作りましょう。ふっと小さくすることで、聴衆をひきつけるような効果が生まれます。このメロディーはアルト単独になりますので、メロディーとしての存在感を失わないように、主役の意識を持ち、音量を落としつつもある程度しっかり歌うことは必要です。
その後【D】のサビに向かってクレッシェンドして盛り上げていきます。文字で書かれたクレッシェンド(cresc.)では内面的な高まりを感じながら。
【D】
【D】はサビの場面です。4パートでハモるところからはじまります。
混声三部版とはパートに割り振られた音が異なっており、四部合唱ならではの厚い響きが生まれます。ここでは【C】と同じく、”ぼ”で伸ばしてみて、和音を確認しておくと良いでしょう。ソプラノとバスの「ミ♭」が根音、テノールの「シ♭」が第5音、アルトの「ソ」が第3音となります。
続いて33小節のように内声で”よんだ”と歌うフレーズは、アルトとテノールがしっかりそろってハモるようにしましょう。ここでより目立つべきはアルトです。テノールの音は飛び出して聞こえやすいので、バランスによっては控えめに歌うことも必要になると思います。
41小節の”きみのことを”はやはりsub.的にmpとなります。単純に音量の変化をつけるだけでなく、言葉のニュアンスを活かし、歌い方に柔らかさ・優しさを出せるとよいと思います。ただし、kの子音を強く出すときつい響きになり、かえって言葉の雰囲気を損ねてしまいます。子音を強調するときは、強さより長さを意識しましょう。
【E】に入る直前のテノールの「ド♭」はやや取りづらいです。「ド♮」で入るフレーズ(11小節など)と混同しないようにしましょう。音を頭に明確に思い浮かべてから入れるように練習が必要になるかと思います。
【E】
ピアノパートによる間奏の場面です。
ソプラノ・ベースのフレーズ終わりのロングトーンは、ピアノパートの音をよく聴き、響きを溶け込ませていくようにしましょう。
47小節のrit.は【F】からの雰囲気に繋がるようイメージして。
【F】
【F】を練習する際には、メロディーを歌うパート(テノール)と和音を担当するパート(ソプラノ・アルト・ベース)に分けて確認し、その後全体で合わせるという順番で行うと良いと思います。
テノールは49小節”(ひ)びのくうはくを”で比較的高い音が出てきますので、このあたりときれいに歌えるように、重点的に練習しておきましょう。音量はあくまでmpなので、声を張り上げることなく、パートで1つの声にまとまるよう意識してください。さらには、ピッチを正しく歌うことだけでなく、言葉のつながりも意識できると良いと思います。例えば、”かぜになったひびのくうはくを”というフレーズでは、小節線に気を取られて”かぜになったひ”と”びのくうはくを”などと途切れてしまわないように。
一方の和音を担当するパートを練習する際は、コード進行を確認しておくとよいと思います。「A♭add9 → B♭7/A♭ → Gm7 → Gm7-5 →C7」のように進みます。Hum.はスラーで書かれているとおりに2小節単位でフレーズを捉えます。動きをつけたい場合は、フレーズの中心を、少し膨らませるような息の使い方をしても良いと思います。
【G】
基本的にはサビの【D】と注意点は同じになります。後半は歌詞が変わりますので、言葉の流れ、語感に気をつけてフレーズを歌いましょう。
69小節の”にじがかかっている”のクレッシェンドにはmolto(モルト/いっそう)がついています。ここでは音量による迫力というよりは、サウンドの広がりを持ったクレッシェンドにしましょう。空の広がる情景をイメージして。
当然ながらロングトーンは練習のポイントです。純粋なハーモニーを作ること、その透明感を保ちながら美しくデクレッシェンドし、【H】のソロの場面を導くことを意識しましょう。
【H】
ソロは72~73小節の、”だれかが”から”わかれ”へのオクターブ跳躍がポイントとなりそうです。
また、ピアノパートとのアンサンブルを意識することも大切です。自分だけのテンポ感で進めるのではなく、ピアノパートの動きも感じながら歌いましょう。
77小節の”きみ”からはじまるフレーズは、よりいっそう優しいニュアンスで歌い、締めくくりに向かいましょう。
79小節のロングトーンは、ピアノパートの弾く和音をよく聴いて、そこに溶け合わせることを意識しましょう。ここでのコードはE♭sus4となっています。
sus4(サス・フォー)というのは第3音が「釣り上げられた(=suspended)」和音のこと。E♭sus4での構成音は「ミ♭・ラ♭・シ♭」となっており、ラ♭が「釣り上げられた」音です。この音が半音下がって「ソ」に降りることで和音が解決します。79~80小節のピアノパートを聴いてみると、E♭sus4 → E♭と進行したときの響きが分かりやすいと思います。
80小節目の合唱パートは休みになっていますので、合唱はsus4のところだけを歌い、ピアノパートによって和音を解決させる、という作りになっています。
「釣り上げられた」音を担当するのはベースです。音取りをした段階では違和感のある音かもしれませんが、ピアノパートと合わせた際、よく聴いていると流れがつかめると思います。
終わりに
最後までご覧いただきありがとうございました。
本記事が、練習や演奏のヒントとして少しでもお役に立てば幸いです。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。