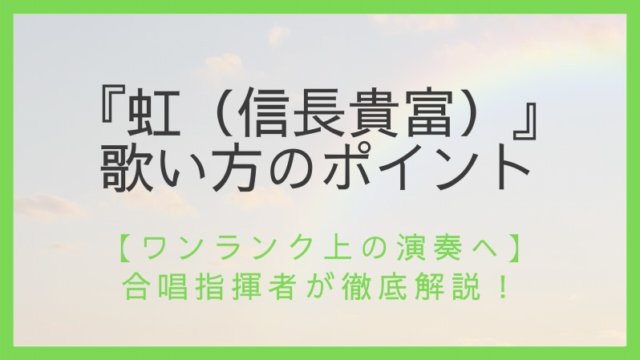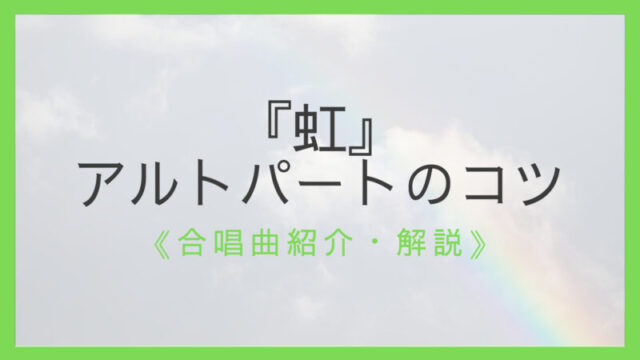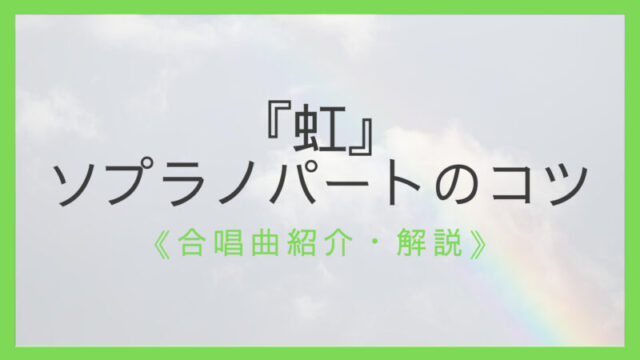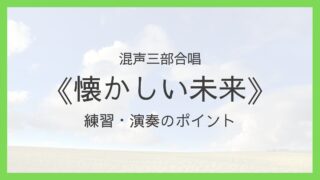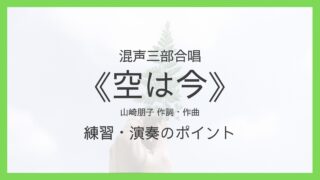【混声三部】《名づけられた葉》(作曲:飯沼信義)練習・演奏のポイント
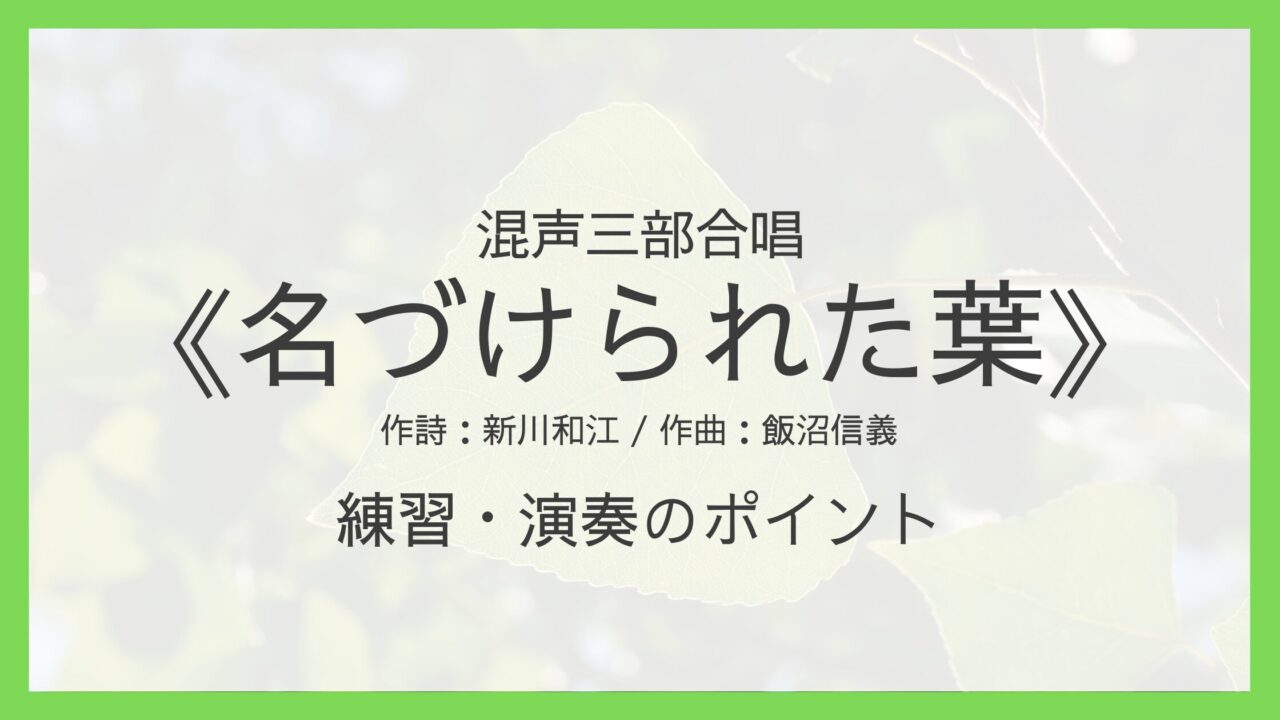
この記事では《名づけられた葉(混声三部合唱)》(作曲:飯沼信義)の、練習・演奏のポイントについてまとめています。
《名づけられた葉》は、中学校で歌われる混声三部合唱のレパートリーの中では比較的難しいですが、充実した内容を持った名曲です。堂々たるクライマックスは感動的で、校内合唱コンクールでは、上位入賞も狙うことができる作品となっています。
ぜひ参考にしていただければ幸いです。
もくじ
練習番号について
練習を始める前に、まずは練習番号(【A】【B】…)をつけておきましょう。
練習番号をつけることで、曲全体の構成の見通しがよくなります。《名づけられた葉》のように大きなドラマのある曲では、今歌っている場所が、曲全体の中でどう位置づけられるのか、という音楽の構成も意識することが重要です。
また、練習する際の指示出しもスムーズに行うことができます。例えば、「次は【A】のアウフタクトから」のように言えますね。
今回は以下の通りつけました。
- 【A】…5小節 “ポプラのきには”
- 【A’】…13小節 “いっしんにひらひら”
- 【B】…21小節 (間奏)
- 【C】…25小節 “(わ)たしも”
- 【D】…33小節 “(にん)げんの”
- 【E】…43小節 “(わ)たしは”
- 【F】…51小節 “ルル”
- 【G】…59小節 “だからわたし”
- 【G’】…65小節 “(せい)いっぱい”
- 【H】…72小節 “(だか)ら” “(な)づけられた”
- 【I】…78小節 “(どん)なに”
練習・演奏のポイント
ここからは、先ほどつけた練習番号に沿って解説を進めていきたいと思います。
【A】…5小節 “ポプラのきには”
歌い出しの場面ですが、いきなりf(フォルテ/強く)から始まります。なので、ここではまず一人ひとりがしっかりと声を出して、力強くメロディーを歌いましょう。
その上でユニゾンであることも知っておきたいポイントです。”ポプラのきには”~”めをふいて”までは、ソプラノ、アルト、男声の3パートがすべて同じ音を歌っています。これがユニゾンです。
ユニゾンでは全員がピタッと同じ音で歌えるよう意識しましょう。音の高さだけでなく、歌い方や声の質もそろえられると、より強い一体感や力強さが生まれます。
特に歌い出しの”ポ”に集中してしっかり狙いをさだめ、どんな音・声で歌いたいかを明確にイメージして歌い始めることが肝心です。
音量に関しては、3小節目の”なんぜん”ではmf(メゾフォルテ/少し強く)、10小節目の”て”ではmp(メゾピアノ/少し弱く)のように、fと比べて小さくなるところがあります。音量的には小さくなっても、歌詩・言葉の力強さは失わないよう、意識してみてください。
【A’】…13小節 “いっしんにひらひら”
【A’】の”いっしんに”からは男声がメロディーになります。
【A】では3パートのユニゾンでフォルテを作っていたのに対し、ここでは1パートになってしまいますから、頼りない印象にならないよう、より自信を持って堂々と歌いましょう。
“させても”はmfになります。極端に小さくする必要はありませんが、<>(クレッシェンド&デクレッシェンド)を上手に利用して、フレーズの真ん中をふくらませるように歌います。また少し柔らかく、語りかけるような歌い方にしてみるなど、記号の解釈を工夫できるところです。
17小節ではff(フォルティッシモ/とても強く)が使われており、【A】【A’】という序盤の山場となります。ここまでで1つの大きなまとまりを締めくくるつもりで歌いましょう。
なお、【A】の11~12小節、【A’】の19~20小節などで男声が2つに分かれていますが、この2つの音(特に低い方の音)がしっかり鳴ると、和音が非常に充実してきます。低い音を歌うのが得意な人はぜひ挑戦してみてください。
【B】…21小節 (間奏)
ここで短い間奏が入ります。【A】【A’】と【B】以降の中間部分を橋渡しするような場面です。この間、調号(ト音記号・へ音記号についている♭)は変化しませんが、ヘ短調から変イ長調、つまり暗い調から明るい調へと転調しています。
ピアノは左手で弾く高音部・低音部のメロディーが呼びかけ合いになるように意識して弾いてみてください。
【C】…25小節 “わたしも”
【A】【A’】はポプラの木や葉の描写について、そして【C】からはポプラの葉に例えた自分自身について述べるシーンになっています。それにあわせて、【B】でも触れたように転調しています。
【C】からはmpとこれまでより音量的に小さくなっていますが、代わりにespr.(エスプレッシーヴォ/表情豊かに)という記号がつけられています。メロディーや言葉を情感豊かに歌ってほしい、というような意図でつけられる記号です。
とはいっても、具体的にはどう歌えばよいのか難しいと思います。ここでは他の記号をヒントにしてみましょう
例えば25~26小節にかけての”いちまいの”には<>(クレッシェンド&デクレッシェンド)がつけられています。これをうまく利用して、フレーズの真ん中(”まい”あたり)をふくらませるようにすると、エスプレッシーヴォ感が出てきます。”すぎないけれど”も同様です。
30~32小節の”じゅえきをもつ”もクレッシェンド&デクレッシェンドがありますが、”いちまいの”、”すぎないけれど”よりも大きな山をイメージすると良いでしょう。”も”あたりを頂点に膨らませてみてください。
また、少し戻って26小節の”は(葉)”はキーワード。大事に歌ってほしい、ということでテヌートがつけられています。テヌートは「音の長さを保って」というような意味ですが、ここでは「たっぷりと、少し強調して」のような意味で捉えて大丈夫です。
【D】…33小節 “(にん)げんの”
【D】からmfとなります。”にんげんのれきしというみき”という壮大さを感じさせる歌詩に音楽が応じています。【C】と比べてワンランクアップすることを明確に。
また、【C】ではしばらくユニゾンが続きましたが、ここから3パートに分かれて一気にハモります。こういった箇所では「ここからハモる」ということを意識しておくだけでも音は変わってきます。
36小節では男声が2つに分かれます。【A’】で触れたように、こういった箇所で低音が鳴ると混声合唱ならではのハーモニーがよりいっそう充実します。
39小節から再びmpになります。“しがみついたおさない”という歌詩の意味と、ハーモニーを繊細に感じながら歌いましょう。
【E】…43小節 “(わ)たしは”
男声のメロディーはmpからはじまりますが、これは【D】の”しがみついたおさない”で出てきたmpとは表情・ニュアンスが異なります。
ここでのmpは、クレッシェンドしてmf、f、そしてffにまで続く、大きな期待感をはらんだmp。弱々しくならず、音量は小さくとも力強さを感じさせるようなイメージで歌ってほしいと思います。
46~47小節にかけて、先ほど触れたようにffが出てきます。これが中間部(【B】~【E】)の大きな山となります。加えて、その後のmf~デクレッシェンドで場面を収め、締めくくることも大切です。
47小節のテヌートのつけられた“な(名)”という言葉は、”は(葉)”とならんでキーワードになります。
【F】…51小節 “ルル”
【F】では”ルルル”以外の歌詩はなく、間奏的な場面に見えますが、音楽的な比重はかなり大きく、重要な場面になります。
ここではまず、ffがつけられたピアノパートは音楽を引っ張っていく存在です。ピアノの動きやメロディーを感じながら、ソプラノ~アルト~男声と入っていきましょう。
以降も、どのパートが音楽を引っ張っていくか(ピアノパートを含む)ということは、強弱やアクセントなどの記号がヒントになります。よく読み込んで演奏に反映させてください。
58小節のロングトーンの和音は、次の場面の調(イ長調)を導く印象的な響きです。
【G】…59小節 “だからわたし”
先ほど触れたように、ここから半音上がったイ長調になります。
音が上がることで全体的なテンションやボリューム感がアップしていきます。前の調を引きずらないよう、クリアに音が上がれるようにしておきましょう。
また、ここでの歌い方としては8分音符のメロディーはたっぷりと豊かに、16分音符の細かなメロディーは言葉をしっかり伝えるように意識すると良いでしょう。加えて強弱のつけ方もダイナミックに。
【G’】…65小節 “(せい)いっぱい”
【G】に引き続き、力強い音楽となっています。
68小節で拍子が変わります。リズム・音ともに難しいので、よく練習しておきましょう。言葉を畳み掛けるように歌う、迫力のあるシーンです。
【H】…72小節 “(だか)ら” “(な)づけられた”
ここから曲のクライマックスに向けて最後の盛り上がりになります。
【H】の主役は男声のメロディー。ffですが、荒々しくなることなく、堂々と豊かに。
女声の”だから”は男声のメロディーを感じながらタイミングをはかって入りましょう。
76小節の直前でいったんmfになりますが、ここは弱々しくならず、特に言葉の力強さをキープして。77小節の”ならない”という義務を表す言葉でクレッシェンドし、再びffを作り直します。
【I】…78小節 “(どん)なに”
ここからは最後まで豊かな音量で歌い切ることが求められます。
82小節以降の“どんになにかぜがつよくとも”のフレーズは、音量・アクセントを全力で表現したいところです。
また、85小節からのロングトーンは絶対に途中で弱くならないように。息が続かない場合は、途中で分からないように息継ぎをするカンニングブレスを利用します。
カンニングブレスでは、
- 一人ひとりが息継ぎのタイミングをずらす
- 慎重に抜ける
- 慎重に入り直す
ことがポイント。こうすることで、全体では息継ぎをしていないように聞かせることができます。
ロングトーンをカットするタイミングは、ピアノパートとも息を合わせましょう。
ここを表現しきれば、間違いなく感動的な演奏ができるはずです。
終わりに
最後までご覧いただきありがとうございました。
なにか質問がありましたら、お問い合わせからお気軽にご連絡いただければと思います。