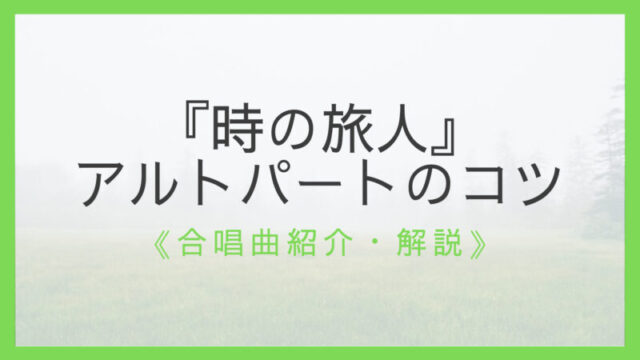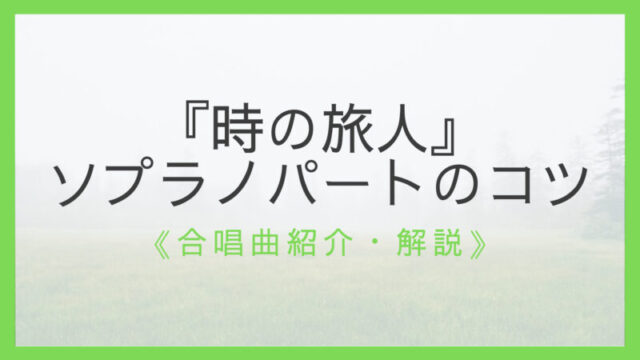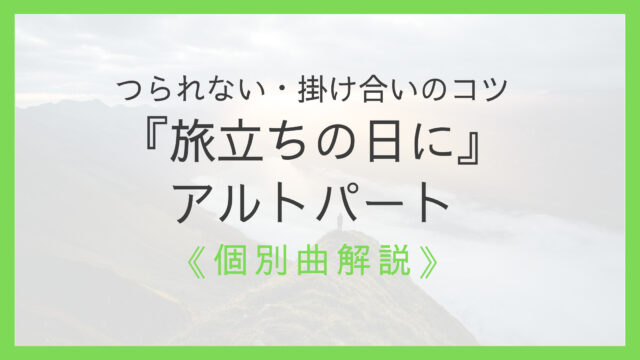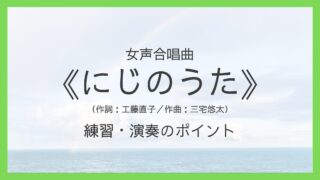《河口》(混声合唱組曲『筑後川』より)練習・演奏のポイント
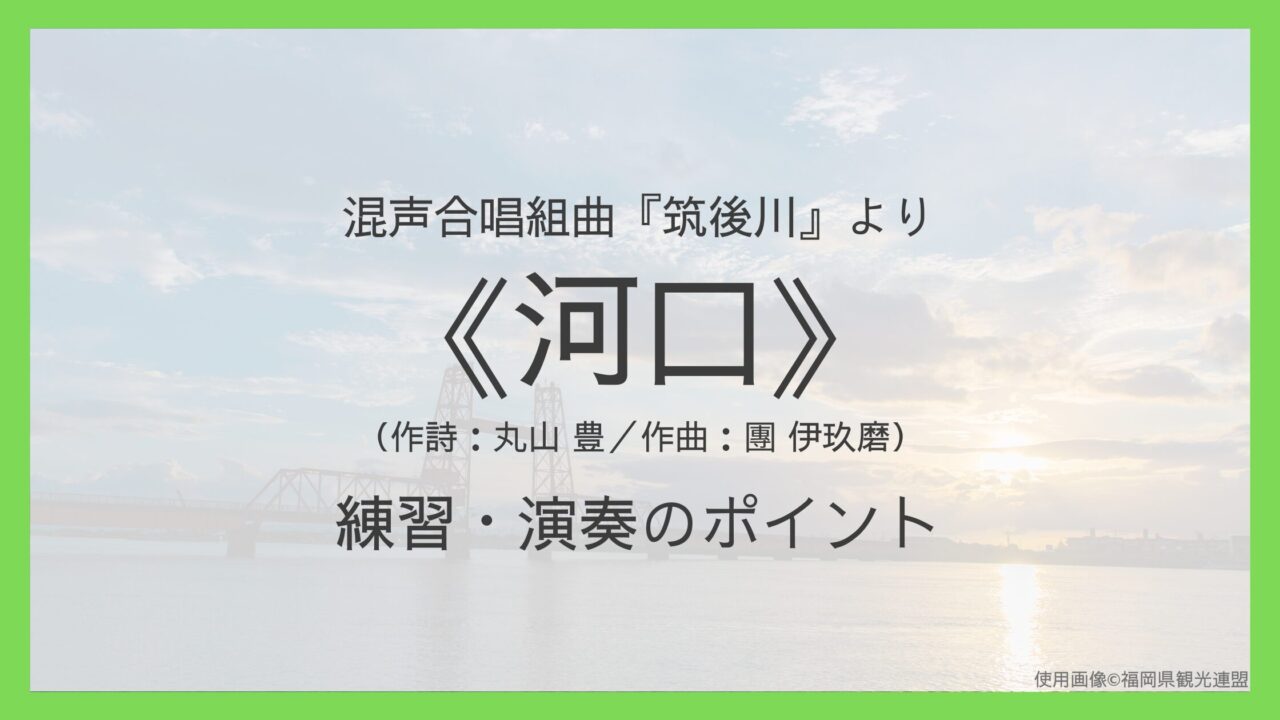
丸山豊 作詩、團伊玖磨 作曲による『筑後川』は、九州を流れる大河「筑後川」をテーマにした合唱組曲。
《河口》はその中の終曲で、”終曲(フィナーレ)を”という歌い出しが印象的な、壮大な作品です。
この記事では《河口》の練習・演奏でのポイントをまとめました。お役に立てば幸いです。
もくじ
組曲『筑後川』と《河口》
 筑後川昇開橋02©福岡県観光連盟
筑後川昇開橋02©福岡県観光連盟冒頭でも触れたとおり、《河口》は混声合唱組曲『筑後川』の最後を飾る曲です。
組曲とは、複数の曲や楽章を組み合わせて一つのまとまりとして演奏する形式の作品のこと。合唱の場合、多くは4~5曲ほどで構成され、全体を通してテーマが設定されていることが多くあります。
『筑後川』を構成するのは次の5曲です。
- 《みなかみ》
- 《ダムにて》
- 《銀の魚》
- 《川の祭》
- 《河口》
その名の通り九州を流れる大河「筑後川」を題材としたこの組曲は、川の最上流を描く《みなかみ》から始まり、さまざまなドラマをたどりながら、終曲《河口》で大きな流れの結末を迎えるという構成になっています。
この《河口》は教科書にも掲載されることがあり、『筑後川』の中でも特に広く知られている作品です。本来であれば組曲全体を通して演奏することが想定されていますが、作品の規模が大きいため、時間的・技術的な都合から《河口》だけを取り出して演奏されることも少なくありません。
とはいえ《河口》はあくまで組曲全体の締めくくりの曲ですから、ぜひ、その意識を持って練習・演奏しましょう。より深みのある表現につながると思います。
可能であれば、一度は組曲全体を通して聴いてみることをおすすめします。
《河口》の練習番号
練習を始める前に、楽譜に小節数および練習番号(【A】【B】…)を書き込んでおきましょう。
小節数と練習番号をつけることで、練習の際にどこから始めるかをスムーズに伝えることができますし、それだけでなく、場面のつながりを整理することができるようにもなります。
今回は次のようにつけました。
- 【前奏】…1小節~
- 【A】…3小節~ “(フィ)ナーレを”
- 【B】…13小節~ “(みな)そこの”
- 【C】…25小節~ “(くれ)ないの”
- 【D】…35小節~ “(ち)くごへいやの”
- 【E】…44小節~ “(ちく)ごがわ”
練習のコツ・演奏のポイント
ここからは、先ほどつけた練習番号に沿って解説していきます。
【前奏】…1小節~
指揮の振り方
【前奏】では指揮の振り方にコツがありますので、まずはそれに触れておきたいと思います。いくつかあるので、順を追って説明します。
1. アウフタクトを示す
曲を始める際、まずアウフタクト、つまり小節からはみ出した1拍分を示します。
テンポ感をイメージし、心のなかで「サン、ハイ」と唱えながら振るとやりやすいと思います。「ハイ」のタイミングで腕を跳ね上げ、同時にGrandioso(グランディオーソ/壮大に、堂々と)をイメージしたブレスを取ります。
また、このアウフタクトではテヌート(音の長さを気持ち引っ張って、長めに)を意識して、少しタメて振れるとなお良いと思います。
2. 5拍子の振り方
2小節目は5拍子になりますので、5拍子図形で振ります。あるいはピアノパートの音符が3拍と2拍に分けて書いてあるため、3/4拍子+2/4拍子とみなして、それぞれの図形で振っても良いと思います。やりやすい方を選択すると良いでしょう。
Grandiosoであり、すべての音にテヌートがつけられていますので、急がないように、また音が軽くならないようにイメージを持って振れるとなお良いと思います。
なお、この前奏のメロディーは組曲の第1曲目《みなかみ》の歌い出し”いまうまれたばかりのかわ”、および終盤で歌われる”未知のくにぐにへのりょこうが”というフレーズの再現となっています。
小さな源流として生まれた川が、さまざまな旅してきて成長し、雄大な大河にまで至るというストーリーを感じさせる、重要なフレーズです。
3. 合唱の入りを示す
5拍目裏で合唱が入りますので、それに対してキュー出しをします。5拍目の表拍でやや鋭く腕を振り上げるような動きで、裏拍を引き出しましょう。
また、ここでもブレスが重要です。腕の動きと連動して、指揮者自身が”フィナーレを”と歌い出すようなつもりで、深いブレスを取りましょう。このとき、ブレス自体はもっと早くから取り始めてもかまいません。
【A】…3小節~ “(フィ)ナーレを”
語頭を豊かに
【A】ではまず、”フィナーレを”の”フィ”をしっかりと響かせることが大切です。
語頭、つまり言葉の頭がクリアになると、歌詩が伝わりやすくなるからです。
音が低いのですが、よく狙いを定めて、正確なピッチで歌えるように練習しましょう。
メロディーの跳躍
先ほど触れた”フィ”から”ナーレ”へは、跳躍音程と言って、離れたところまで音が飛びます。「シ♭ → ソ」では6度の幅となっています。
跳躍はメロディーを魅力的なものにする一方で、歌うのが難しいため、注意が必要です。
まずは上がった先の音が低くならないように気をつけましょう。離れた音まで上がるためにはかなりのエネルギーが必要になるため、体全体を使った発声が必要になります。
次に、上がった先の音に丁寧に着地すること。乱暴な歌い方にならないようにしましょう。
4小節目のソプラノのメロディーは、幅が先ほどよりさらに広い8度(=1オクターブ)の跳躍です。歌うのもいっそう難しくなるわけですが、それによってさらに音域が広がり、壮大さをますます高める効果を発揮しています。
ユニゾンからハモリへ
最後にハーモニーの面を見てみましょう。
“フィ”の音は、実は全員が「シ♭」で同じ音を歌っています。つまり、この音だけを見ればユニゾンということです。そして”ナーレを”で一気に音が分かれ、ハモります。
このような場合、まずユニゾンとなる「シ♭」の音を徹底的にそろえることが大切です。そして「”ナーレを”でハモるぞ」ということを知っておきましょう。ハーモニーを良くするために意識しておきたいことの一つです。
なお、このように「ユニゾン → ハモリ」というパターンは四部合唱ではよく登場します。《河口》でも他の箇所で何回か出てくるので、見つけてチェックしておくとよいでしょう。
臨時記号に注意
7小節”かわは”からは臨時記号が付く音に気をつけましょう。例えば、7小節目アルトの「ミ♮」、9小節目テナーの「ラ♮」などです。
臨時記号では音を取るのが難しくなりますが、代わりにハーモニーに色彩の変化をもたらしてくれます。
特に9小節目のテナーは、「シ♭ → ラ♮ → ラ♭」と半音ずつ音が降りていきます。こういったフレーズでは、気を抜くと音が下がりすぎてしまいやすいので、お腹でしっかり声を支えながら歌うと良いと思います。
【B】…13小節~ “(みな)そこの”
雰囲気の変化を感じて
【A】は堂々とした長調(明るい調)でしたが、【B】からは短調(暗い調)となり、雰囲気が変化します。いろいろな川の生き物・景色に別れを告げていく、少し切ない場面です。
mp、pといった音量の表現も、そういった雰囲気を感じながらできるとよいと思います。
リズムをあわせて
【B】ではこれまでと比べると16分音符の細かいリズムが出てきます。
これらがばらついてしまわないよう、しっかりタイミングを合わせられるよう練習しましょう。
言葉を喋る
リズムが細かくなっている分、言葉を伝えるのにも工夫が必要です。
歌い上げるというよりは、語る・喋るようなイメージで。細かいリズムははしょらず丁寧に。重要な子音は長めに発音すると良いでしょう。
[重要な子音の例]
- “みなそこの”…m子音
- “かわいい”…k子音
- “さかなたち”…s子音
メロディー・歌詩の受け渡し
【B】は最初に女声が歌い、それを受けて男声、そして再び女声…というように、女声・男声が交互に歌うような構造となっています。
このメロディー・歌詩の受け渡しがスムーズに、自然に進んでいくよう、直前のパートの歌い方や声の音色・音量をよく感じ取りながら歌いましょう。
強弱に気持ちの揺れを乗せて
19~22小節にはクレッシェンド・デクレッシェンド(<>)の記号が多く書かれています。
ここで繰り返される”さよなら”には、フィナーレを迎えることができた誇らしさや、一方で名残惜しさといったような複雑な心情が現れているように思います。
そのような気持ちの揺れを乗せて、クレッシェンド・デクレッシェンドを表現してみると良いと思います。
20小節の”さよなら”の繰り返しはpでエコーのように。
同じ音をピタッとそろえる
22小節の4拍目は、全パートが「シ♭」で同じ音にそろいます。
こういった箇所では、一つの音にまとまるように集中力を高めましょう。
前もって「シ♭」で伸ばしているテノールを聴いて、音をあわせると良いと思います。
【C】…25小節~ “(くれ)ないの”
細かな違いを見つけよう
【C】はおおむね【B】の繰り返しとなっている場面です。したがって基本的な注意点は【B】と同様です。
一方で異なる点として、次の3点を挙げたいと思います。
[【B】と【C】の違い]
- 歌詩
- 強弱
- ピアノパート
「2. 強弱」に関しては、pだったところはmpに、mpだったところはmfにと、全体的にワンランクアップしています。【B】で解説したような「気持ちの揺れ」が、よりいっそう大きな振幅となっている、というように解釈ができると思います。歌詩との対応を考えてみても良いでしょう。
「3. ピアノパート」については、25小節4拍目の右手のように、装飾的なフレーズが追加されています。
このように似ている場面では「どこが同じなのか」「どこが異なるのか」という点を整理しておくことが大切です。微妙な違いには、作曲家が表現したいことが込められています。
【D】…35小節~ “(ち)くごへいやの”
アウフタクトからのハーモニー
35小節からの”(ち)くごへいや”のフレーズでは、アウフタクトの”ち”で全員が同じ「シ♭」の音を歌います。そして”くごへいや”からは4パートに分かれてハモります。
つまり【A】で解説したのと同じく、「同じ音で入って、一気にハモる」というパターンとなっています。同じ音をそろえること、ここからハモると意識することが大切です。
また、ここはffの豊かな音量で堂々と歌い上げる場面です。混声四部合唱ならではの、重厚なハーモニーを響かせましょう。
アカペラ、つまりピアノパートなしでも十分に聴き応えのある場面ですので、練習の際は、合唱だけの響きを感じてみるのが効果的な練習となります。
男声はハーモニーの土台となります。そこでまずはテノール+ベースだけを取り出して練習してみましょう。このとき、「ミ♭」の音でオクターブユニゾン(オクターブ離れて同じ音になること)となることが多いので、その音がしっかり合っていることを確認しておきましょう。
それができたら次はアルトを加え、メロディー以外のハーモニーはどうなっているのか聴いてみるのも面白いと思います。
もちろん、他のパートの組み合わせ(ソプラノ + アルト、ソプラノ + ベースなど)を試してみても、新たな発見があると思います。
なお、【D】のフレーズは、組曲の第2曲《ダムにて》の終盤で現れるメロディーの再現となっています。
1度目のクライマックス
41~42小節が、この曲でのクライマックスです。
fffの豊かな音量で歌うことが求められますが、声を張り上げて乱暴な発声にならないよう気をつけましょう。またハーモニーへの配慮も必要です。
42小節では、冒頭のメロディー、すなわち組曲の第1曲《みなかみ》のメロディーが再現されます。
合唱は4拍目の頭で音を切りますので、しっかりそろえること。指揮者が音を切る動きも重要です。
【E】…44小節~ “(ちく)ごがわ”
最後のクライマックスへ
【E】からは2度目のクライマックスに向かいます。アンコール的な繰り返しとなりますので、本当にこれが最後というつもりで歌いましょう。
【E】の入りはffです。これまではfffだったため、ここではいったん音量を落とすことになります。
この意味は、一番最後のffに向かい、再度盛り上がりを作っていくための準備です。いったん音量を絞ることで、その後に控えているクレッシェンドやfffがよりいっそう際立つという仕掛けです。
会場に響きを行き渡らせて
46~48小節のロングトーンは、《河口》、ひいては組曲『筑後川』を締めくくる最後の音です。
良い発声、ハーモニーを忘れずに、豊かな音量で歌い、会場に響きを行き渡らせましょう。
音を切る際は、会場に響きを解き放つようなイメージで。
終わりに
最後までご覧いただきありがとうございました。
この記事を参考に、みなさんの演奏がより豊かで実りあるものとなれば幸いです。
《河口》は単独でも十分に感動的な作品ですが、組曲全体の流れを意識すると、より深い表現につながります。もし時間があれば、ぜひ《筑後川》全曲を通して聴いてみてください。
音楽の背景や物語性を知ることで、練習や本番での表現も大きく変わってくるはずです。
ご不明な点や記事へのご意見がありましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。