【混声三部】《蒼鷺》(作詩:更科源蔵 作曲:長谷部国俊)練習・演奏のポイント
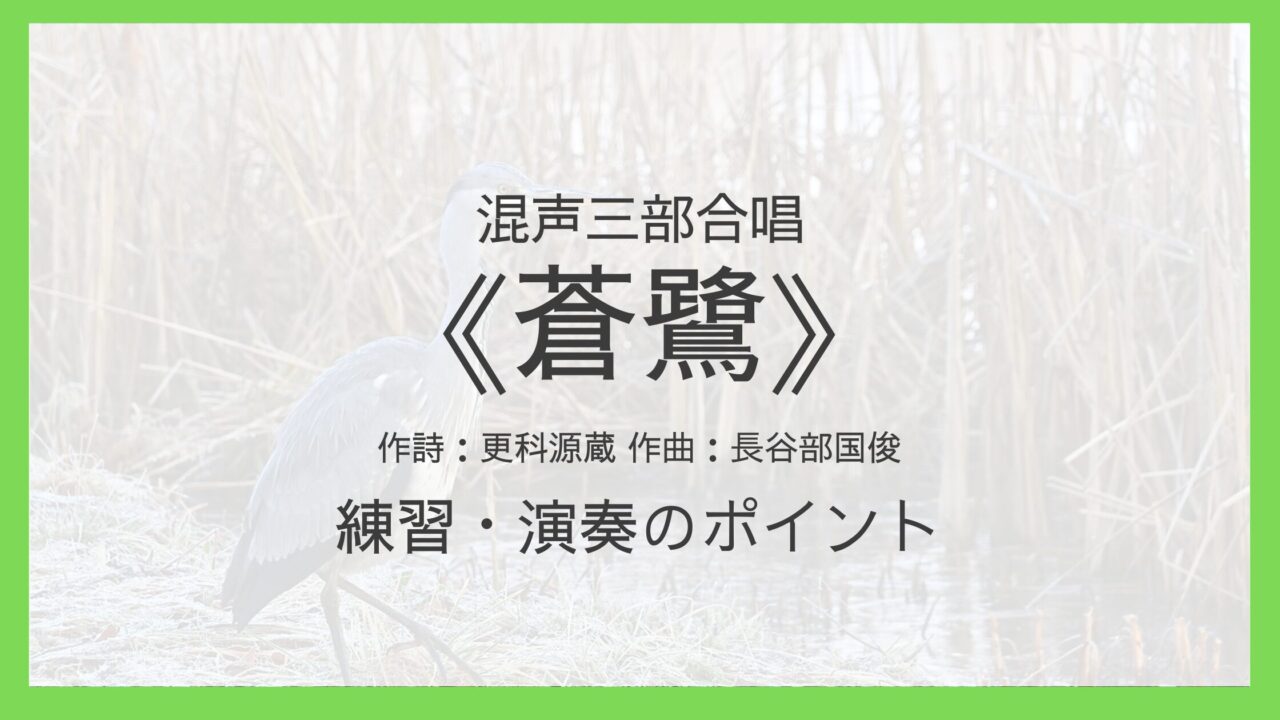
《蒼鷺》は北国の厳しい寒さと、その中で生きる蒼鷺の姿を歌った作品です。
この記事では、《蒼鷺》の演奏に役立つポイントを、練習番号に沿って具体的に解説します。
この記事を参考に、ぜひ練習・演奏に挑戦してみてください。
この記事を参考にコンクールに挑戦された方からコメントをいただきましたので、紹介させていただきます。
“蒼鷺で最優秀賞を受賞することができました。

練習番号
練習を始める前に練習番号(【A】【B】…)をつけておきましょう。楽譜にあらかじめつけられている場合はそのまま使ってもかまいません。また、小節数が書かれていない場合は、それも書き込んでおくと便利です。
今回は以下の通りつけました。
- 【A】…3小節 “えぞはるに”
- 【A’】…11小節 “あおいかげが”
- 【B】…17小節 “(あ)おさぎ”
- 【C】…25小節 “(か)ぜは”
- 【D】…36小節 “(みみ)げ”
- 【E】…43小節 “むなげをふるわす”
- 【E’】…51小節 “むなげをふるわす”
- 【F】…59小節 “(それと)も”
- 【F’】…62小節 “あおぞらへの”
- 【G】…70小節 “(かぜ)は”
- 【H】…74小節 “(だが)あおさぎは”
- 【I】…78小節 “(おく)の”
- 【J】…86小節 “(やせほ)そり”
- 【J’】…90小節 “(こおっ)た”
- 【K】…95小節 “えぞはるに”
- 【K’】…103小節 “あおいかげが”
練習番号をつけることで、曲全体の構成の見通しをよくすることができます。また、練習する際の指示出しもスムーズです。例えば、「次は【A】のアウフタクトから」のように言えますね。
以降の解説も、練習番号に沿って行います。
練習のコツ・演奏のポイント
【A】…3小節 “えぞはるに”
《蒼鷺》はニ短調(=「レ」の音を主役にした暗い調)で始まります。
合唱の歌い出しは、ソプラノ・アルト・男声すべてが「レ」の音。針の穴に通すような集中力で、この音をよく狙って入りましょう。音量はp(ピアノ/小さく)です。そこから徐々に音が分かれ、広がっていきます。【A】に入る前の2小節の前奏の間に、イメージを高めておくのが大切です。
7小節からは音量が一団上がってmpになります。p系ではありますがこれまでより少し積極的に歌いましょう。
【A’】…11小節 “あおいかげが”
この場面は、メロディーを歌うソプラノと、ハーモニーを作るアルト、テノール、バスの3パートに分けかれています。練習の際にも、分けて確認すると効果的です。
ここではハーモニーのパートに「ミ♭」の音が出てきていることに注目しましょう。臨時記号の♭が入ることによって、和音の響きが変わり、”あおいかげがのびる”という歌詩に応じるかのように色が深くなります。
14小節のrit.(リタルダンド/だんだん遅く)ではテンポが緩んでいきます。テンポが変わるときには、全員でそのテンポ感を共有し、お互いの声・音を聴き合わないとずれてしまいます。特にここで聴いてほしいのはアルト。“かげがのびる”の“び”の8分音符のタイミングをつかむのがコツです。
【B】…17小節 “(あ)おさぎ”
【B】に入り、音楽に少しずつ変化が出てきます。具体的な要素として次の3つを挙げておきたいと思います。
1つ目はト短調へと転調していること。2つ目はテンポの変化。【B】に入る直前のaccel.からの流れでテンポアップしています。3つ目はピアノパートの伴奏形です。これまでは流れるような音型でしたが、【B】からは8分音符を刻むような動きになっています。
これらによって音楽にこれまでにはなかった「動き」が出てきており、詩の情景の変化に対応しています。合唱パートはその変化を感じながら、mf(メゾフォルテ/少し大きく)でこれまでよりさらに積極的に、”あおさぎはかたあしをあげ”を歌います。<>(クレッシェンド&デクレッシェンド)も十分表現しましょう。
続いて21小節のアウフタクト(アルトの”しずかに”)は一転してp系の音楽へ。ここで“しずかに”のsの子音で、”静かに”という言葉の雰囲気を出すようにしましょう。
【C】…25小節 “(か)ぜは”
【C】に入ると再びピアノパートの伴奏形が変化します。3連符によるアルペジオ(和音を分けて弾くこと)で、よりダイナミックな音楽の流れが生まれています。これもやはり風やそれに吹かれる葦といった情景を表現しているように思えます。
最初はソプラノとアルトだけで歌われます。男声がいない状態でのmfなので、【B】よりもさらにしっかり目に歌う気持ちがあっても良いと思います。女声合唱ならではの響きを作りましょう。
29小節からは男声が合流します。低音が強化されることで、ハーモニーに厚みが出てきます。全体の響きや、和音の中での自分の役割・立ち位置を感じながら歌いましょう。そうすることでよくハモるようになります。
さらに32小節では男声がテノールとバスに分かれ、全体で混声四部合唱の響きを作ります。男声の人数が半分になってしまうのですが、この「ド」と「ソ」の音をしっかりと鳴らすと、四部合唱らしい重厚なハーモニーが生まれます。重要な聴かせどころの一つです。
【C】では女声二部→混声三部→混声四部というように、徐々に声部が増え、響きが厚くなっていくように作られているということに気がつくかと思います。風が徐々に強くなってきて、葦を大きく揺らすようになる……そんな情景が浮かびます。そして34小節での和音の変化と、dim.(ディミヌエンド/だんだん小さく)で”さっていく”というわけです。
【D】…36小節 “(みみ)げ”
【D】からはホ短調になります。
歌い出しは緊張感のあるpで。言葉を伝えることをしっかり意識しましょう。弱々しくならず、むしろこの先にある激しい展開に対する期待感を持って歌い進めましょう。accel.(アッチェレランド/だんだん速く)に従って、その緊張感を徐々に高め、切迫していきます。
41小節のロングトーンに入ったら加速度を高めて。ピアノパートは8分音符を刻んでテンポを煽るようなイメージで。
【E】…43小節 “むなげをふるわす”
【D】からのアッチェレランドの流れでかなりテンポアップします。乗り遅れないように。
ここでのf(フォルテ/強く)は、雑な歌い方にせずに、深い音色をイメージして歌いましょう。アルト、バスの”Oh”も深い響きで。
口の奥の方(軟口蓋)を上に上げて空間を広げ、頭蓋骨を響かせるようなイメージで歌うと、深い音色を作りやすいです。ただし、力んでしまっては良くないので、自然に歌える範囲で行いましょう。
【E’】…51小節 “むなげをふるわす”
最初は【E】の繰り返しになりますが、漫然と歌わずに、再度fを作り直すようなつもりで入りましょう。
55小節からは音が異なるので注意しましょう。ここから【F】にかけて、和音が目まぐるしく変化しながら音楽が展開していきます。非常に激しく難しいフレーズです。
基本的な音取りの精度を高め、和音の変化を鮮やかに決められるよう、重点的に練習しておきたい場面です。♭系のフレーズから♯系のフレーズに移る58小節から59小節のつなぎは要注意です。
【F】…59小節 “(それと)も”
前述のとおり、【E’】から【F】へのつなぎの音が非常に難しいのでよく練習しておきましょう。
“どよめく”という歌詩ではdの子音を強調することで迫力が出ます。
【F’】…62小節 “あおぞらへの”
中間部のクライマックスシーンになります。ff(フォルティッシモ/とても強く)で、アクセントをしっかりつけて、迫力のある場面にしましょう。
“ねつじょうか”を3連発しますが、ここは拍子の変化に注意しましょう。3拍子+3拍子+2拍子です。特に2拍子のフレーズは直前のブレスをしっかりと取り、少し重たく、アクセントをしっかりつけて歌います。指揮者は2,3,4拍子図形の切り替えをスムーズに行えるように練習しておきたい場面です。
また、ロングトーンでは和音もしっかり確認しておきましょう。
【G】…70小節 “(かぜ)は”
【F】【F’】ではかなり熱く盛り上がりましたが、ここからは一転、静かな場面に入ります。冷静さを取り戻して、再び冷たい風をイメージして歌いましょう。ピアノパートの音型を感じつつ、レガートに(なめらかに)。
“かぜは”のkの子音、”ふきすぎる”のfの子音を少し強調すると歌詩が伝わりやすく、パートの掛け合いがきれいに決まります。
【H】…74小節 “(だが)あおさぎは”
ここで再び音楽ががらりと変わります。“だが”という逆接の接続はきっぱりと。
さらにクレッシェンドしていき、“うごかぬ”のアクセントはしっかり、断固とした表情で。
16分音符のフレーズは言葉が伝わりにくいので、しっかりと喋る意識を持って歌うと良いでしょう。
【I】…78小節 “(おく)の”
【H】でマルカート(固く、はっきりと)的な歌い方をしたのに対し、ここからはレガートな歌い方に切り替えると美しいです。音量はfですが、力まず、たっぷりとしたブレスを取って歌いましょう。
【J】…86小節 “(やせほ)そり”
アウフタクトの”やせほそり”は「ファ♯」から高い「ファ♯」への跳躍(音が大きく跳ぶこと)があります。1オクターブも音が離れていてとても難しいフレーズです。
なぜ作曲家はこのようなメロディーを書くのかと言うと、音と音とが離れていればいるほど、聴いている人に強いエネルギーを感じさせるからです。それと同時に、歌い側にも大きなエネルギーが必要とされるわけですが、この2つの音はぜひとも切れずに歌いたいフレーズです。
また、フレーズ終わりのデクレッシェンドも重要で、これによって次の【J’】へとつなぎます。
【J’】…90小節 “(こおっ)た”
直前のデクレッシェンドの流れを引き継いで、”こおった”、”うごかぬ”の意味のニュアンスを表現しましょう。音量は小さくなりますが、集中力を緩めることもなく、むしろ緊張感がより高まっていくように。pで歌う92小節の“うごかぬ”が《蒼鷺》の詩、ひいてはこの曲の核心部分と言ってもよいでしょう。
【K】…95小節 “えぞはるに”
【A】を再現する場面です。
転調のため、【A】よりも音が上がっていますが、フレーズの山で盛り上がりすぎないように、抑制した表現で。静けさをキープして歌いましょう。
【K’】…103小節 “あおいかげが”
【A’】と同様、メロディーを担当するソプラノと、ハーモニーを作る3パートに役割が分かれます。
後のロングトーンの和音も集中して決めましょう。デクレッシェンドがあり、音の切り際ではタイが次の小節に掛かるように書かれていますので、109小節のピアノパートのアルペジオに溶け込んでいくようなイメージで、消え入るように音を切ります。
終わりに
最後までご覧いただきありがとうございました。
この記事を参考に、良い演奏ができることを願っております。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。
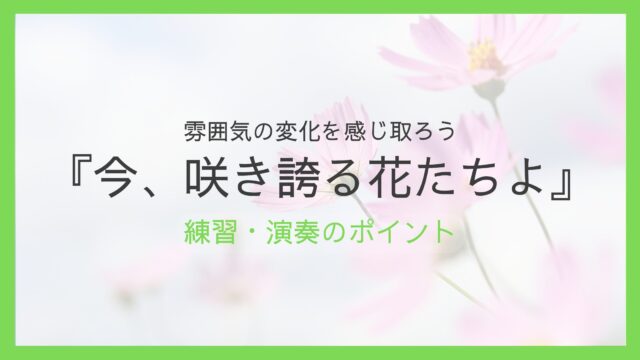
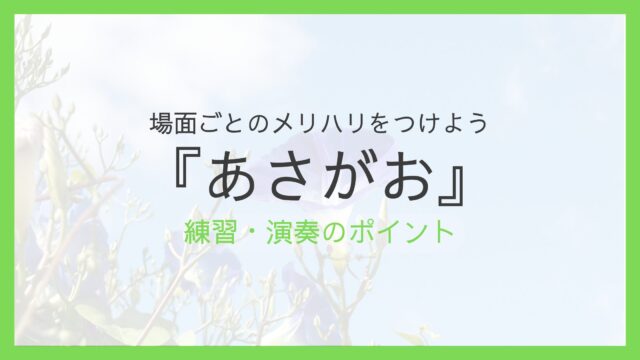
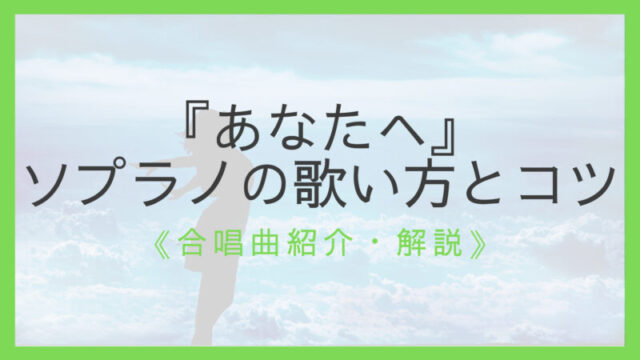
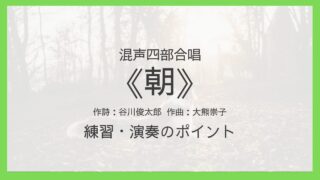
練習・演奏のポイント-68a719eb6cb59-320x180.jpg)
