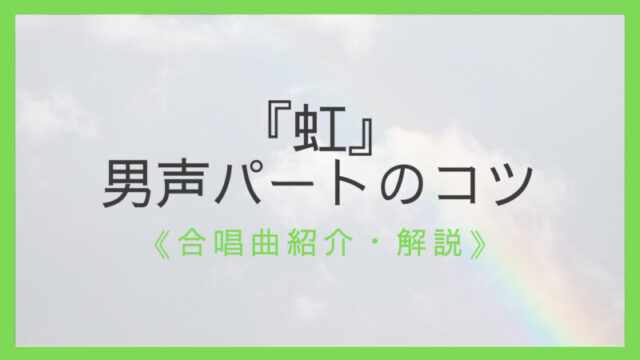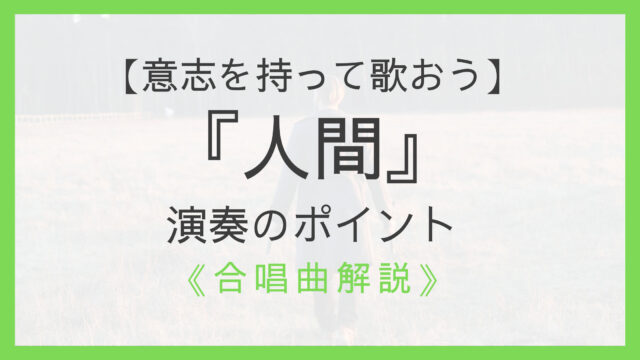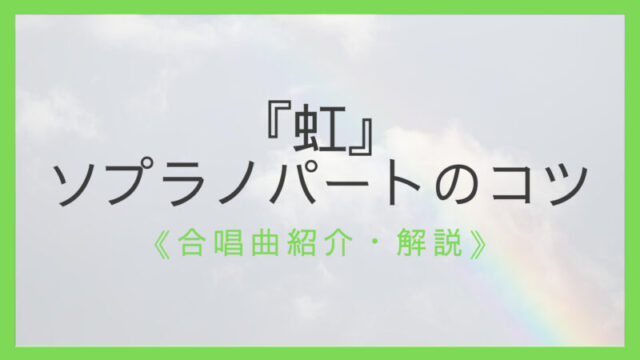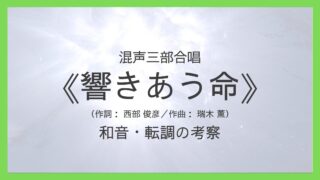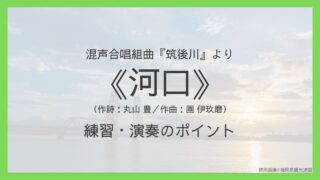【女声合唱】《にじのうた》(作詞:工藤直子/作曲:三宅悠太)練習・演奏のポイント
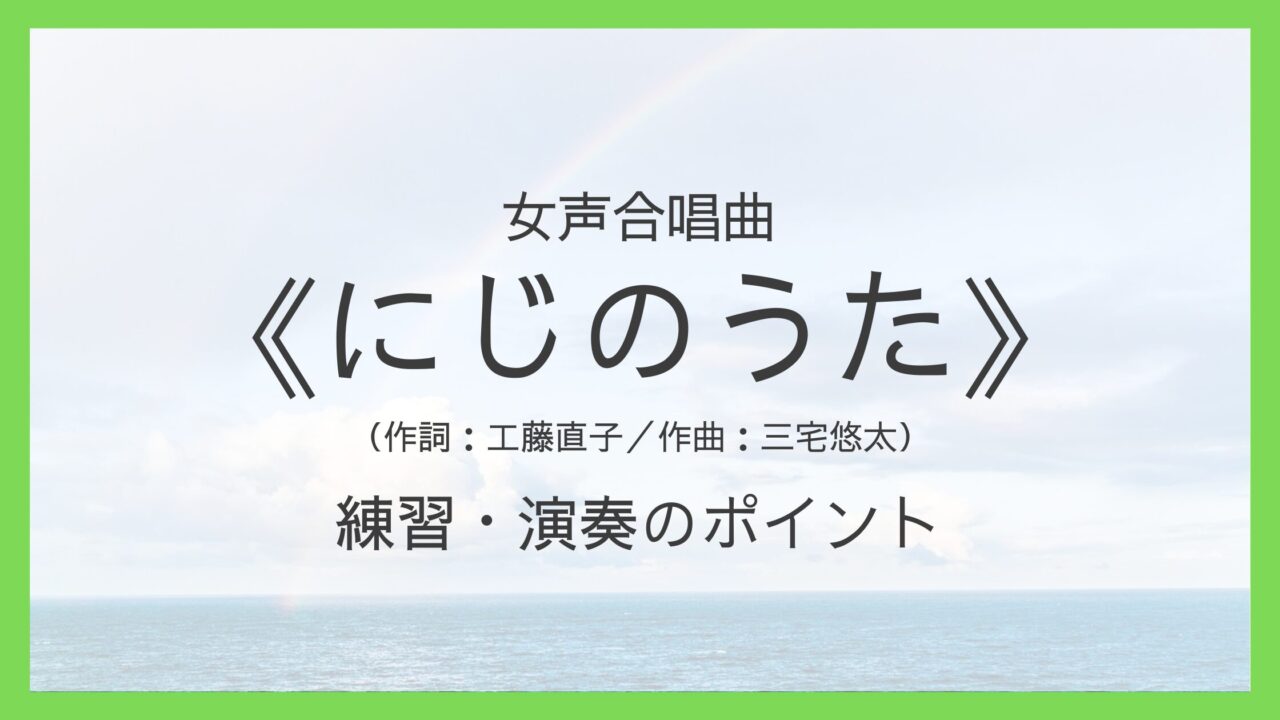
《にじのうた》は三宅悠太さんによるピアノ付きの女声合唱曲。和声やリズムの工夫がいたるところに施され、色とりどりの場面が次々に描かれていく、素敵な作品です。
テキストは工藤直子さんによるものです。ひらがなで書かれていて、一見可愛らしい内容のようですが、壮大な祈りが込められているように思えます。
この記事では《にじのうた》の演奏に役立つポイントを、練習番号に沿って具体的に解説しています。
この記事を参考に、ぜひ練習・演奏に挑戦してみてください。
もくじ
練習のコツ・演奏のポイント
練習番号(【A】【B】…)に沿って解説していきます。
なお、解説のために、1~8小節を【イントロ】としています。
【イントロ】…1小節~ “そらは”
語頭の子音と母音を意識しよう
冒頭のフレーズでは、”そらは”の”そ”には<>のアクセントが付けられています。息のスピードに勢いをつけ、sの子音を歌うことで、”ハッとして、鮮やかに!”と書かれているような表情を乗せることができると思います。
次に2~3小節にかけて短いクレッシェンドがあり、”てんののはら”というフレーズに続きます。”て”にはテヌートが書かれていますので、ここをフレーズの山としてとらえ、そこに向かって息の流れを持っていきましょう。eの母音は響きが平板になりやすいので、しっかりとタテに開くことを意識してください。
メロディーの追いかけっこ
4小節ではアルト(第2声部)が”のはら”のフレーズを繰り返します。直前のフレーズと同じ音を歌うため、まるで「こだま」のような動きです。
ここでは単に歌詞がずれるだけでなく、ソプラノが伸ばしている音とぶつかることで音の陰影が生じます。それを感じながら歌ってみましょう。
fに向かうクレッシェンド
5小節からは”cresc. poco a poco”が書かれています。このような長いクレッシェンドを表現するときには「どこに・どこまで向かうのか?」という方向感・距離感が大切になります。
このクレッシェンドは【A】のfに向かいます。そこまでの持って行き方、盛り上がりのイメージを明確に持つこと、それを歌い手全員で共有しておくことが大切です。
【A】…9小節~ “(かけ)よう”
虹の和音
【イントロ】では2パートでの追いかけっこのようなフレーズが主でした。それに対して【A】の最初のフレーズ、”(かけ)よう”は、3パートのタテがそろいハモります。一気に音が広がるような印象のフレーズです。
ここでの和音はB(=H-dur「シ・レ♯・ファ♯」)です。♯がたくさんつき、きらびやかな印象のあるこの和音は、《にじのうた》において「虹の和音」として位置づけられているように私は感じます。
【イントロ】でクレッシェンドしていくうちから、この和音の響きの広がりを思い浮かべておくことが、ハーモニーを決めるポイントの1つとなると思います。
また、”う”に音が降りたところでデクレッシェンドが始まりますが、すぐに小さくしてしまわず、少しの間ボリューム感を保ち、その後引いていくのが良いと思います。
切り際の歌い方
【イントロ】の7小節や、【A】の10小節では、スラー(タイ)が休符に向かうように書かれています。この曲では多く見られる手法ですが、こういった場合切り際に余韻を持たせるようなイメージで表現しましょう。続くフレーズやピアノパートの響きに溶け込ませていくようなイメージでも良いでしょう。
逆に、切り際にスラー(タイ)が書かれていない場合、スパッと音をカットするような歌い方が望まれます。
メロディーを魅力的に歌おう
“きんいろのうたが”から【A】のメロディーが始まります。espr.(エスプレッシーヴォ/表情豊かに)を表現し、メロディーを魅力的に歌いましょう。そのためには、やはりフレーズの抑揚、言い換えれば山と谷が大事になってくると思います。
まずはmfからはじまり、すぐにクレッシェンドが出てきます。このクレッシェンドの向かう先、”うたがひびきわたる”の二拍三連がフレーズの山となります。”うたが”のテヌートは、語頭でもあるのでU母音にしっかり響きを乗せましょう。
その後のデクレッシェンドでフレーズを収めていきます。そうすることで、次にソプラノが歌う”そんな”という次なるフレーズを導くことにも繋がります。
ソプラノのフレーズも同様に、”はなやぐ”の二拍三連に向かってクレッシェンドし、フレーズの山を作りましょう。<>はA母音を明るく、また少し弾むようなバウンド感の息遣いがあっても良いと思います。
和音の変化を感じながら
《にじのうた》では和音の使い方を工夫し、色とりどりの場面を展開させているところが印象的です。特に14~17小節あたりはダイナミックに和声が展開されますので、その響きをよく感じながら歌ってみてください。
14~17小節のコードネームと和音の構成音をまとめておきます。♮の音を含むものはロ長調に本来含まれない和音で、色彩感を高める効果を発揮しています。
- 14小節…G「ソ♮・シ・レ♮」
- 15小節…C「ド♮・ミ・ソ♮」
- 16小節…C♯m7「ド♯・ミ・ソ♯・シ」
- 17小節…F♯「ファ♯・ラ♯・ド♯」
【B】…19小節 “てつだってくれる”
つぶやきと「間」
【A】がメロディーを歌いあげて盛り上げる場面だったのに対し、【B】はまるで語りかけるように歌う場面となっています。
細かくクレッシェンド・デクレッシェンドやテヌートがつけられていますが、これは語りかけるときの言葉の抑揚に沿ってつけられていると考えると良いでしょう。
22小節の”ともだちは”のあとの休符には、響きの余韻をよく感じて、音楽の「間(ま)」を作りましょう。
【C】…25小節~ “くもからとびおりた”
【B】からのつながりを意識して
【C】の歌詞は”くもからとびおりた”からスタートしますが、流れとしては【B】の”てつだってくれるともだちは”からつながっています。その点を忘れずに意識しておきましょう。
3拍子の拍感を感じて
これまでは2拍子系の音楽でしたが、【C】からは6/4拍子になるため、音楽の感じ方を変える必要があります。
6/4拍子は3/4拍子を2つつなげた複合拍子ですから、3拍子的なキャラクターを持っています。この拍感をつかみ、フレーズをおおらかに、大きく感じて歌いましょう。
2つのフレーズのキャラクター
【C】には主に次の2つのフレーズから構成されています。
- “あめのつぶと”…4分音符のおおらかなフレーズ
- “おひさまからとびだした”…8分音符が中心の弾むようなフレーズ
これらのフレーズのキャラクターの違いをつかみ、少し際立たせて表現すると面白いと思います。
また、ここではメロディーの追いかけっこになっていることに注目しましょう。音が折り重なるように歌われ、雨と光のイメージが音画的に表現されます。
たっぷりと豊かに、余裕を持って
32小節~は天空の広大さ、雄大さを感じさせる場面です。espr.が書かれていますが、フレーズの山を作ることに加え、スラーを意識すると表現しやすいと思います。
音量がpoco fとなっています。ここには、しっかりと盛り上げるよりは、espr.的な表現をより強調して欲しい、という意図があるように思います。また、少し音量をしぼったところからフレーズを始めることで、その後のクレッシェンドを際立たせることもできるでしょう。
36小節のアルトパートのテヌートは、動きをしっかりアピールしましょう。ただし、アクセントの記号ではないので、柔らかいアタック感で歌えると良いと思います。
【D】…37小節~ “まぶしい”
輝きのある声でユニゾンを歌おう
“まぶしいまぶしいあめのつぶ”のフレーズはユニゾン、つまり全員が同じ音を歌います。
“輝いて!”とあるとおり、単なるfではなく、輝くような響きが欲しいフレーズです。明るい母音で歌うこと、そしてピッチをよく統一して歌うことを意識しましょう。
明るい母音を意識する際、単に口を大きく開けてしまうと、開きすぎた平板な響きになってしまいますので、共鳴を同時に意識するのが良いと思います。
フレーズの変化を感じ取って
41小節~の”いちめんちらばって”は、歌詞がずれて歌われる「掛け合い」のフレーズとなっており、先ほどのユニゾンとは大きく印象が変わります。
このような場面ではまず言葉の頭をクリアに入ることが大切です。そうすることで「掛け合い」の効果がきわ立ち、言葉がキラキラときらめくような表現ができます。
それと並行して、41小節の入りでは直前のデクレッシェンドを引き継ぎ、少し小さく入るようにしましょう。言葉のクリアさを両立するために、少し声をひそめて「しゃべる」ような表現も可能だと思います。
その後のクレッシェンドで43小節のfに持っていけば、コード進行の効果も相まって非常にダイナミックでカタルシスのある場面にできそうです。
続く二拍三連の連発のメロディーは、まさに”そらのカーテン”のような印象のメロディーとなっていますね。
41~44小節の和音では、【A】で触れたような「♮入り」の和音が使われており、色彩感の変化をもたらしています。個人的には少しブルー系が入るイメージです。
その後44小節の”なれ“で再び♯系の和音(A)に戻ることで、「カタルシス」が生じるような気がしています。
【E】…58小節~ “にぎやかな”
思い切ったタメを
58小節アウフタクトの”にぎやかな”には”molto riten.”が書かれていますので、ここのタメは思い切って大きく作るのが良いと思います。
そして、それによって蓄積したエネルギーを”にぎやかな”のフレーズで弾けさせるように歌ってみましょう。非常に印象的な場面を作れると思います。
ただし、>のアクセントではないので、乱暴な表現にはならないようにしましょう。
オクターブユニゾンに集中
60~62小節はオクターブユニゾンとなっています。ピアノパートが休みになることもあり、非常に緊張感が高まる瞬間です。集中して音を狙い、よくそろえて歌いましょう。
【F】に入った後のロングトーンも、気持ちをゆるめず、張り詰めた音を持続するのが良いかと思います。
【F】…62小節~
高音部をキラキラと
【F】はピアノパートによる間奏となります。
“brillante”(ブリランテ/輝くように)が書かれていますから、特に高音部のパッセージはキラキラと、”ひかりのつぶ”をイメージして。
【G】…65小節~ “「にじ」は”
メッセージを大切に伝えよう
【G】はピアノパートのトレモロによって導かれた合唱が、まるで語りかけるように歌う場面です。【C】と同じく、拍子の変化にも注意しましょう。
その中でも特に大切な”「いのち」”という言葉には<>のアクセント、”「つぶ」”にはテヌートが付けられています。これはただ単純に強く歌えば良いというものではなく、言葉の抑揚を活かして音楽的に表現して欲しいと思います。
イメージをつかむために、詩を朗読してみるといった練習方法を取り入れるのも良いでしょう。
68小節からはじまる”cresc. poco a poco”も、ただ単に大きくしていけばよいというのではなく、内面的な気持ちの熱さが必要です。【H】に向かって、祈り、あるいは願いの気持ちを高めていきましょう。
【H】…72小節~ “せかいが”
テンポに乗り遅れず、期待感を高めて
【H】からはテンポが急激に早くなりますので、それに乗り遅れないようにしましょう。
また、これまでは2拍子でフレーズを大きく捉えて歌う場面が多かったのに対し、ここでは4拍子になっています。関連して、フレーズをこれまでと比べ、小さいまとまり(2小節単位)で感じることが必要になってくると思います。ピアノパートの刻む8分音符(エイトビート)も感じながら歌いましょう。
ただし、メロディーを歌うときの基本はレガートですから、アクセント的な歌い方になりすぎないほうがよいと思います。
【H】では、ピアノパートの左手・低音部がずっと「ファ」の音をキープし、一方の右手・高音部が奏でるコードが変化していくことで、走り出すような期待感が表現されています。
コードネームは次のとおりです。
- FM9 → G7/F → Fm7 → B♭/F
【I】…76小節~ “にっこりと”
主役のメロディーをアピール
ここから再び2拍子になりますから、【H】とはフレーズの捉え方を変え、広がりを感じて、おおらかに歌いましょう。
“にっこりとほほえむ”のところに書かれている”en dehors”は「浮き立たせて」という意味。最上声・最下声がfで歌う「ソ」のロングトーンに埋もれることなく、このメロディーがしっかりとアピールできるように歌いましょう。歌詞に応じて明るい母音で歌うと良いと思います。
79小節の”ほほえむ”ではタテがそろうことを意識し、充実したハーモニーで。
音のない瞬間を作ろう
83小節はブレイク。ここで音のない瞬間を作るのが大切です。
無音の時間というのは緊張感が走ります。ピアノパートだけでなく、歌い手も気を抜くことがないようにしましょう。
84小節から再開する際は、fをくっきりと鮮やかに。
【J】…85小節~ “La la la”
“生き生きと!”
【J】のメロディーに書かれた”生き生きと!”は、【D】のような輝きを持ったユニゾンで歌うことが大切です。
それに加えて、これまでと同様にフレージングも意識すると良いでしょう。基本通り、フレーズの真ん中に向かって息を回していき、膨らませていくイメージです。こうすることで生命感・躍動感が出てきます。
具体的にはスラーでつながれた85~88小節の4小節間をひとまとまりで捉え、87小節あたりを頂点とするのが良さそうです。より細かく作るなら、87小節1拍目を最も大きな山として、その後、88小節1拍目に向かって、もう一度小さな山を作ってみましょう。
87小節1拍目を(大)、88小節1拍目を(小)とする根拠は、ここがだいたい真ん中であることや、聴いたときの印象からも分かりますが、もう一つ、和音とメロディーの関係からも見抜くことができます。
87小節1拍目のコードはGM7(「ソ・シ・レ・ファ♯」)ですが、それに対し、メロディーは「ド♯」を歌っています。これはGM7のルートである「ソ」に対しては11度にあたり、強くぶつかる音です。このぶつかりによるエネルギーの高まりが緊張感をよりいっそう高め、メロディーを生き生きとしたものにしています。(ハモリパートの「ラ」は9度で、これもまたぶつかっています。)
一方、88小節1拍目のコードはD/F#、メロディーは「ラ」です。「ラ」の音は和声音(和音の中に含まれる音)ですが、最下声の「ミ」が9度でぶつかっており、先ほどと比べればソフトではあるものの、緊張感を生じさせています。この「ミ」の音は、3拍目で「レ」へと解決することで、Dm/Fの和音の中に解決していき、メロディーを収束させる効果を担っています。デクレッシェンドもありますね。
このように、メロディーの形だけでなく、和音とメロディーの力関係を利用して、フレーズの山をつくるという作曲テクニックも用いられているのです。
「虹の和音」で会場を満たそう
89小節は少し小さく入り、クレッシェンドしていきます。その先、91小節で登場するのは、【A】でも触れた「虹の和音」です。ここはデクレッシェンドせずに、ffの豊かな響きをキープしましょう。「虹の和音」で会場を満たすようなイメージで!
91~92小節のピアノパートの音型はまるで本当に「虹」のアーチのような形になっていますね。合唱の声量を突き抜けて、キラキラとした音の粒が会場に降り注ぐように響かせられると、とても素敵です。
【K】…93小節~ “あおぞらよ”
祈りのコラール
【K】のピアノパートはほとんどずっと同じ音を鳴らしているだけ。そのためアカペラに近いような雰囲気です。テンポもゆっくりになるため、祈りのコラールのような場面にも感じられます。
“ゆらいで”と指示がありますが、これは「言葉の抑揚に合わせて、少しテンポを伸び縮みさせて」と読み取ることができると思います。クレッシェンド・デクレッシェンド、テヌートが細かく付けられていますが、これも言葉の抑揚に合わせたものと捉えましょう。
クレッシェンドではフレーズの頂点に向かって息を回すようなイメージで、少しテンポを巻き(速めて)ます。逆にデクレッシェンドではテンポを緩め、フレーズを落ち着かせます。こうすることで、気持ちのこもった日本語を、自然に表現できると思います。
クライマックスシーンへ
100小節からはクライマックスシーンに向けて盛り上げていきましょう。
sosten.が書かれているところからは、音が軽くなってしまわないよう、また決して急がないように。一つ一つの言葉を噛みしめるように、強く願いを込めて歌いましょう。
102小節からのクレッシェンドは、ダイナミクスレンジを大きくつけると、堂々とした曲の締めくくりにつながります。
104小節ではデクレッシェンドが書かれていますので、ロングトーンの音量を一旦絞りましょう。これによってピアノパートのパッセージが生き生きと浮かび上がってきます。
105小節からのクレッシェンド・アラルガンドはピアノパートのクレッシェンドとも息を合わせて。
透明感のある和音
104~106小節の和音はEadd9、つまり「ミ・ソ♯・シ」に9度「ファ♯」が加わった和音です。
通常なら9度となる音は他の音と直接ぶつからないよう、離れたところに置かれますが、ここでは隣の音どうし、直接ぶつかる場所に置かれています。透明感のある女声合唱らしいボイシングです。
隣り合う音のことを「ぶつかる」とか、ときには不協和音と呼びますが、ここでの9度は美しい響きとして用いられています。複雑で難しい音にはなりますが、しっかり決められるようによく練習しておきましょう。
9度(実際には2度)となる「ファ♯」の音は、高めを意識すると純正な響きに近づきます。
終わりに
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
《にじのうた》は色彩豊かな響きと深いメッセージを持つ作品です。この記事が練習や演奏のヒントとなり、それぞれの団体らしい表現につながれば嬉しく思います。
ご不明な点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。